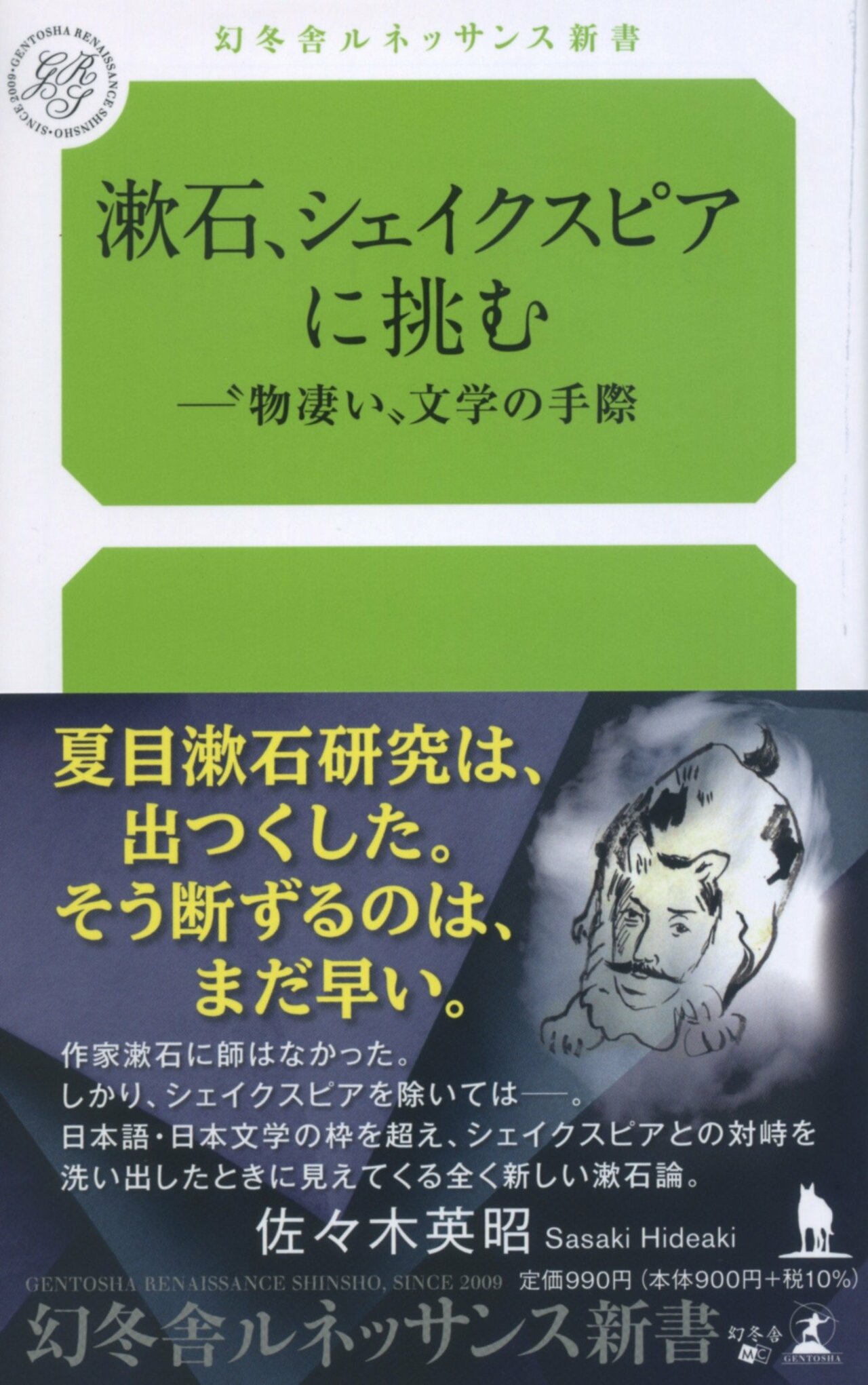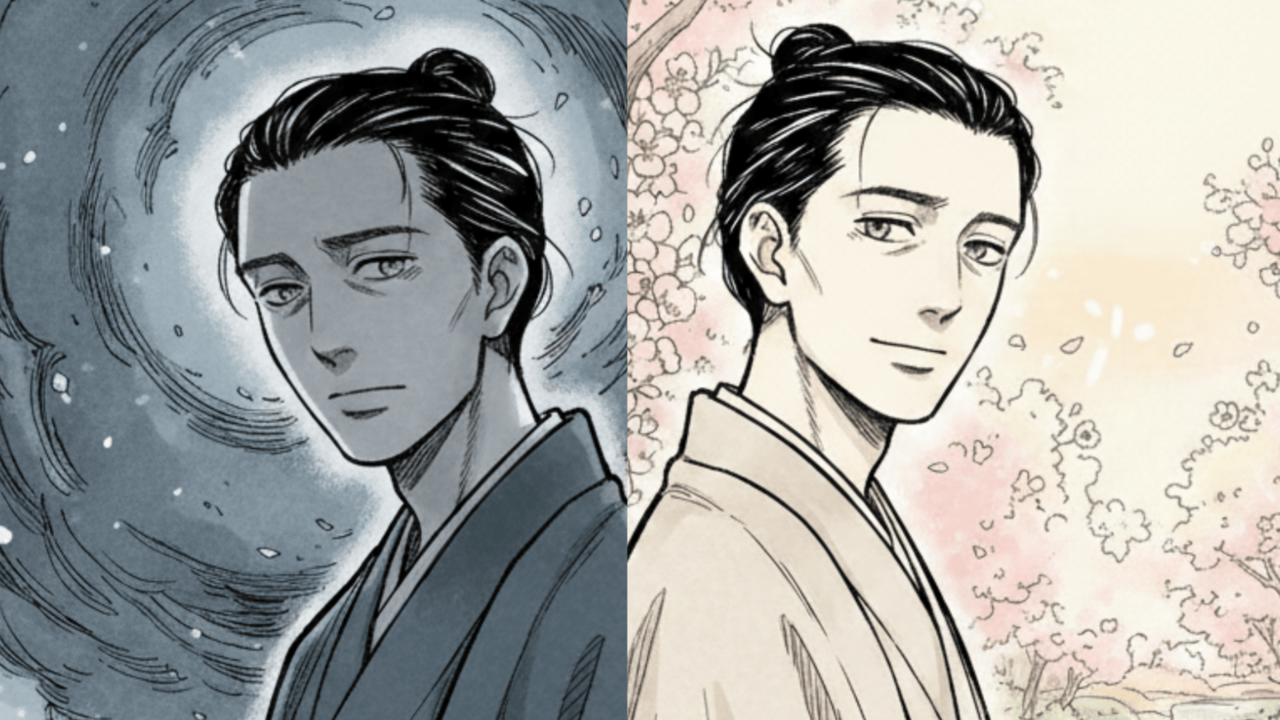文学理論としての「則天去私」
ところで、「物には両面がある」という認識は、そのいずれか片方の「面」にへばりついている人間には得られないものである。空間的比喩で語れば、「両面」をともに見渡せる上空に浮揚することが条件になる。
右に引いた『こころ』(下 五十一)の先生は「運命の冷罵」を感じて暗然としていたが、漱石の作品でこの「運命」あるいは「神」「天」「自然」などの概念が、「冷罵」などする多少とも擬人化された超越的存在として導入される場合には、語り手の意識もそれらに付着して上空から「両面」を眺めやるという構造が発生することになる。
このような意味での上空浮遊の感覚というか、その「手際」にシェイクスピアから吸収した部分があるのかもまた、にわかに決められない微妙なところではあるのだが、ともかく一九〇七年春、ついに大学を辞して朝日新聞社員となった漱石の連載小説第一作『虞美人草』は、作者が中空にいてヒロインを生かすも殺すも俺の一存――小宮豊隆宛書簡で表明(第七章参照)――という姿勢で取り組まれた、『アントニーとクレオパトラ』(推定執筆年 一六〇七年)を明白な下敷きとする小説であった。
これに類した作品はその後は書かれず、シェイクスピアへの直接的な言及も減るが、折にふれて書き残された「断片」類を検討すれば、この文豪がつねに作家漱石の頭脳の一角を占めていたことが、いよいよ明らかになる。
そして忘れてならないのは、『明暗』(一九一六[大正五]年)未完のまま死を迎えるほんの一、二か月前のこと、のちに漱石の代名詞とさえなる標語、あの「則天去私」を説いた際に、これを実現しえているほぼ唯一の作家としてシェイクスピアの名を挙げたという事実である。
この「則天去私」が初めて漱石の口をついて出たのは例の木曜会でのことで、後年、一部の弟子によってその倫理的・宗教的な解釈が喧伝されて漱石神話の一つとなった次第だが、古参の弟子の一人である森田草平によれば、その第一義はあくまで文学上の議論に限定されていた。
すなわち漱石いわく、「ゴッドのネーチュア〔神の自然〕」の域まで来ているトルストイも「まだ神になり切れない」でいるが、それは「作中の人物が人物自らの意志によつて動かないで、作者の意志によつて無理に動かされてゐる所がある」から。
これがシェイクスピアの場合は「毫も『私』を出さない、作中の人物は人物自らの意志によつて、神の摂理に従つて動いてゐる」と。「則天去私」はこのような文学手法を指す標語として出てきたもので、自分もそのように「書きあらはしたいと、折に触れて云つてゐられた」と森田は確かな口調で伝えている(『夏目漱石』〔甲鳥書林、一九四二〕九頁)。
【イチオシ記事】「私を抱いて。貴方に抱かれたいの」自分でも予想していなかった事を口にした。彼は私の手を引っ張って、ベッドルームへ…