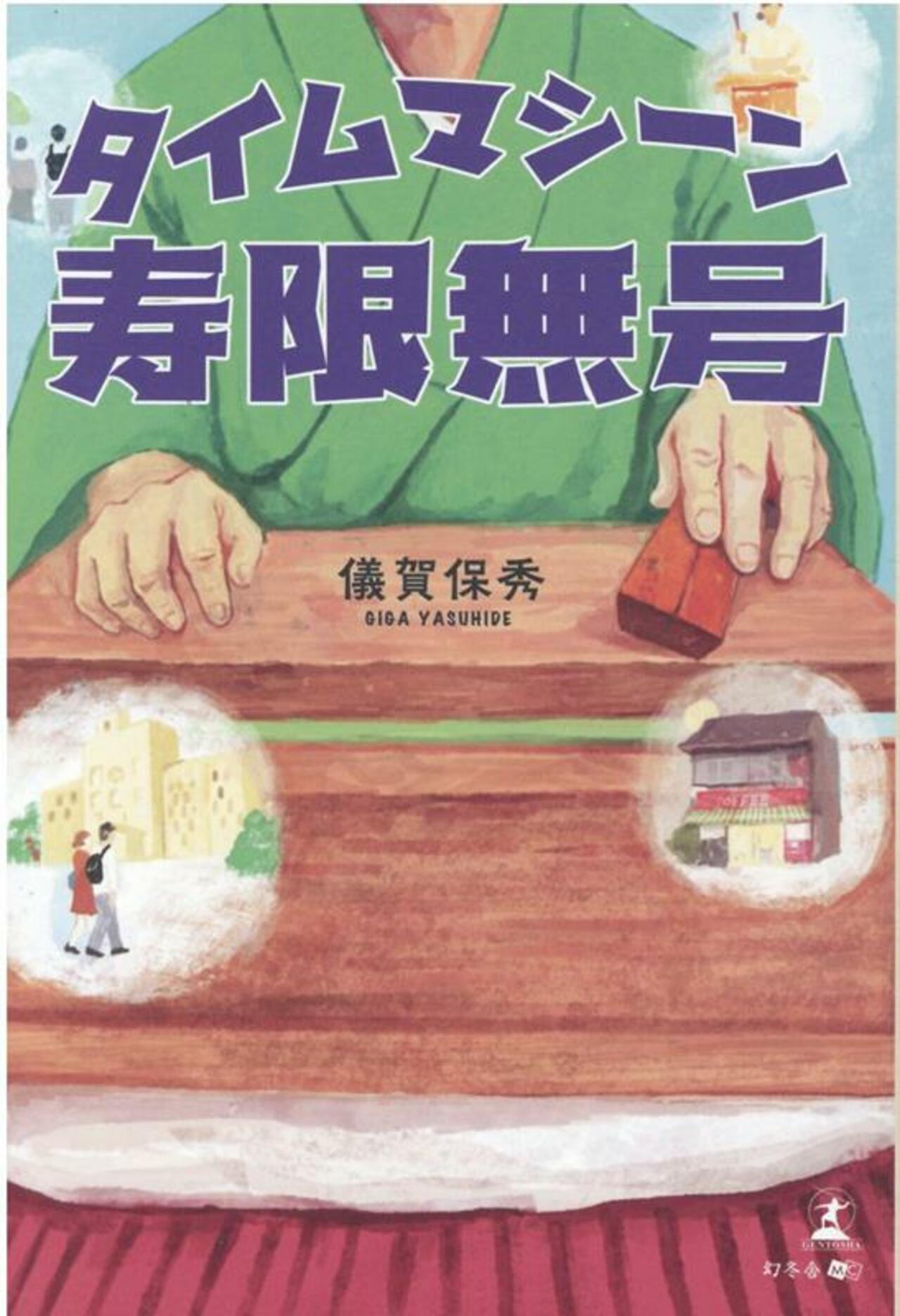そう言った祐斗の表情が一変し、急にスイッチが入った。
──定吉、定吉、定吉はいてますかいな?
──へい、旦(だん)さん、なんぞ御用で?
どんどん話し出す。うまいことはうまい! だが、どこか一人芝居を思わせる喋り方だ。
その場で聞いている喜之介のほうが恥ずかしくなってしまい「あ、もう結構です」そう言って、祐斗を止めた。
「ダメですか?」
落語の実力の評価について聞いてきた。
「いや、ダメというか、そういうことではなく、だいたい君の実力が分かったんで」
「どうでしたか?」
祐斗は気になるようで喜之介に質問する。
「うん。まあまあや」
「そうでしょうね」
評価が低いと捉えているようだ。
「ですから、喜之介師匠に弟子入りして、もっともっと落語がうまくなりたいんです」
どこまでも前向きなイケメン好青年。好青年というには少し年がいき過ぎている気もするが、こんな人物が落語の世界に入ってきたら話題になるに違いない。
現在も二枚目の落語家はいるにはいるが、生来のスター性を兼ね備えている者はいない。
その点、祐斗は違う。芸能の世界で注目を集める存在になる予感がする。
そうすれば、その逸材を見出し、育てた師匠である自分も評価されるだろう。それもええなあ。
やっぱり、この男を弟子にしたほうが何かと得策だ。
喜之介は勝手にそこまで想像の翼を広げたが、自分にそんな眼力があるのかと冷静になって考えたところで、皮肉の笑みがこぼれた。
【イチオシ記事】「抱き締めてキスしたい」から「キスして」になった。利用者とスタッフ、受け流していると彼は後ろからそっと私の頭を撫で…