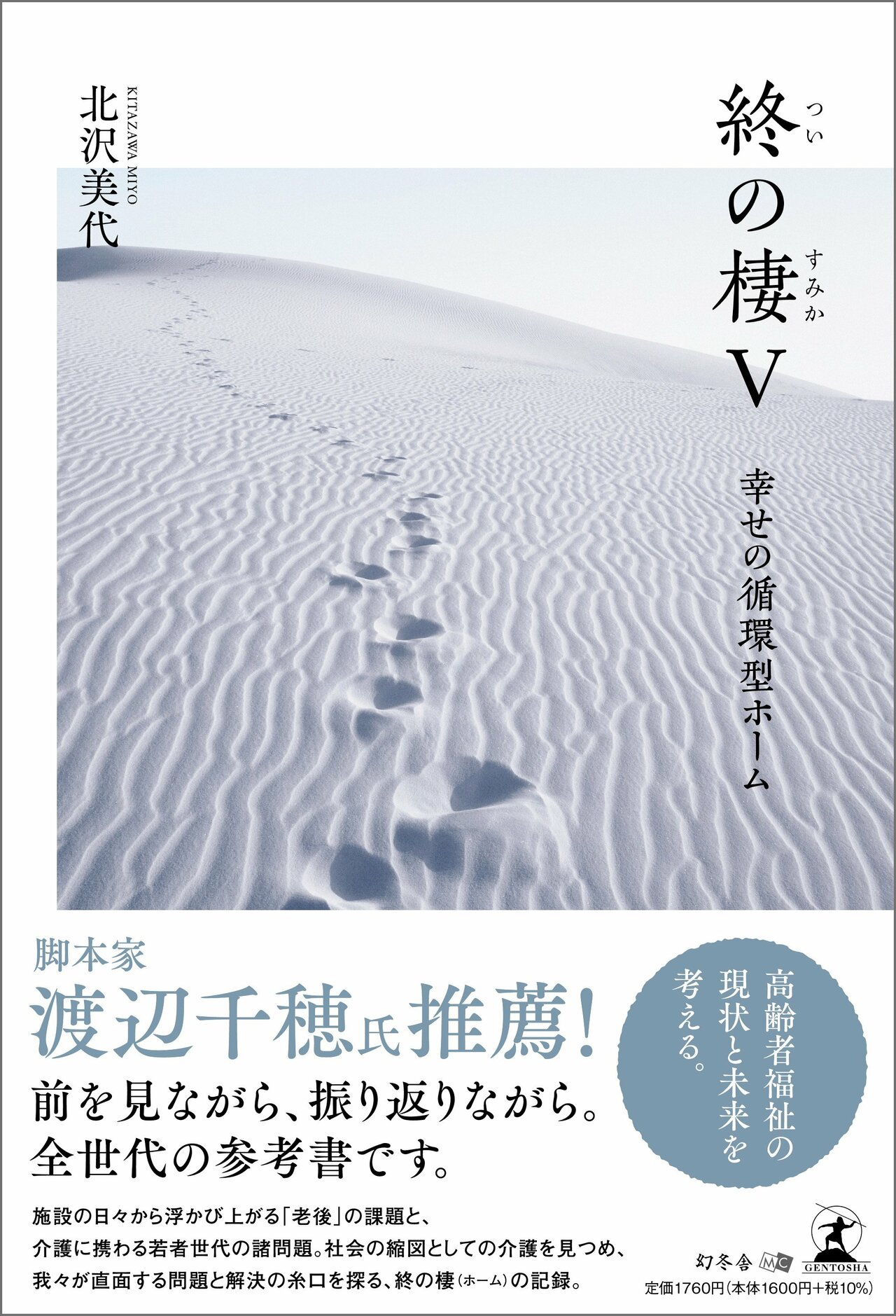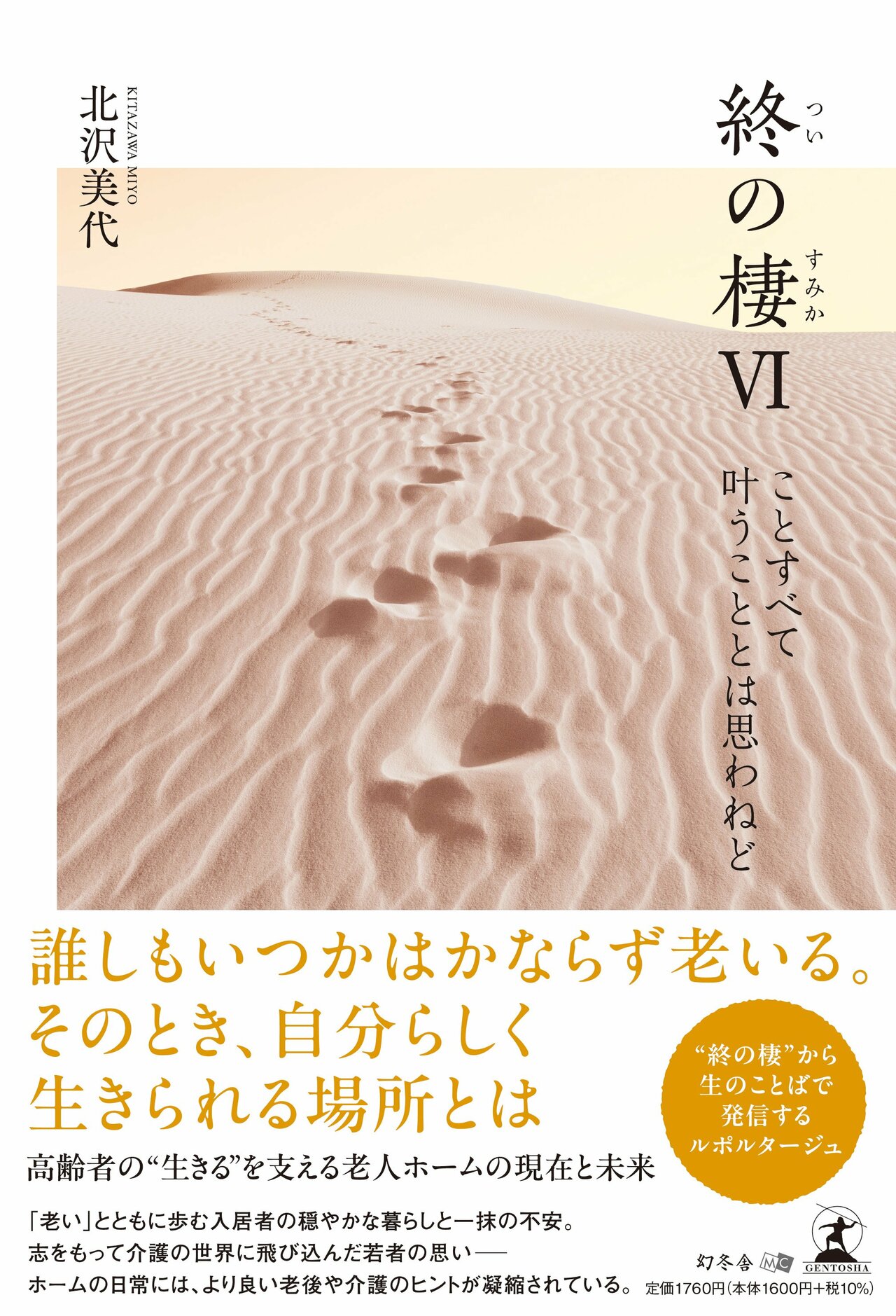第三章 老人ホームを終の棲に決めたのは
ひとりの思いから
私が老後を考えた時すでに「介護」は老人ホームと決めていたがその理由をしっかりわかっていたわけではなかった。ただ、漠然と周囲から入る情報で「介護は大変だ」と思っていたのと、もう一つ姑が「私はあなたに介護を頼まないわよ。老人ホームに入るから」と公言していたことが大きく影響していたのは確かだ。
しかしその姑も入浴中の脳卒中で突然死してしまったので「老人ホーム」を選択していた理由は聞かず終いになってしまった。
私の入居は七十八歳。入居してみると他の人たちは私より年長者ばかりだった。ひとり、私と同年、昭和十六年生まれの入居者がいたが彼女は脳梗塞の後遺症があって半身不随ですでに車椅子を使っていた。
私は「介護」といえば紙オムツ程度の知識しか持っていなかったし、情報を得ようとさえ思っていなかったので当然といえば当然だった。
「人生最後の大きな買物」と私が今発信していることから考えるとおかしな話である。
確かに早過ぎる老人ホーム入居には違いなかったが、これは私にとって非常にラッキーな選択だった。
集団生活の苦手な私は個室の中で老後の生活を考えればいい位に思っていた。介護する人間と介護される人間しかいないホームの生活も考えてみれば不自然な世界である。その違和感、危惧さえ「家族に介護をさせないでホームの居室を得る」ことを考えていた私にはそれを考える余地さえなかった。
私の一作目『終の棲 ホームの日々』にはNoを入れていない。それは徒然に書いたエッセイだったからだ。しかし二冊目からはNoを入れた。ここに明らかに私の変化を見ることができる。
『終の棲Ⅱ 老いと共に歩む』『終の棲Ⅲ ─社会性を持った大きな家族─』『終の棲Ⅳ ─ありがとうと言ってくれてありがとう─』。これらのタイトルはすべてこのホームで出会ったスタッフとホーム長の「介護」「老人ホーム」に対する熱い理念、彼らの言葉がそのままタイトルになっている。
「本」という形で社会に発信したいと思ったのは私自身であるがこれも彼らの言動に感動し、背を押されての行動である。心身の衰えは私自身がいちばん知っている。しかし彼らに感動する心とそれを書いて社会に発信したいという気力がまだ残っていたことが私の早過ぎたと思われるホーム入居をラッキーと言った由縁である。
心身共に弱ってからの入居だったら私だって一方的な介護に任せるしかなかったろう。「人はここまで人の手を借りなければ生きていけないのか」という私の実感は私も例外でなくそのひとりなのだから。
前置きが長くなってしまったがこの章の本題に戻ろう。
ホームの生活が長くなるにつれ、何の疑問もなく家族の介護よりも老人ホームを選んでいた自分に対し、もしかしたら家族による介護を支持する人たちがいて当然だし、その人たちの考えを聞きたいという思いがつきまとっていた。
【イチオシ記事】「抱き締めてキスしたい」から「キスして」になった。利用者とスタッフ、受け流していると彼は後ろからそっと私の頭を撫で…