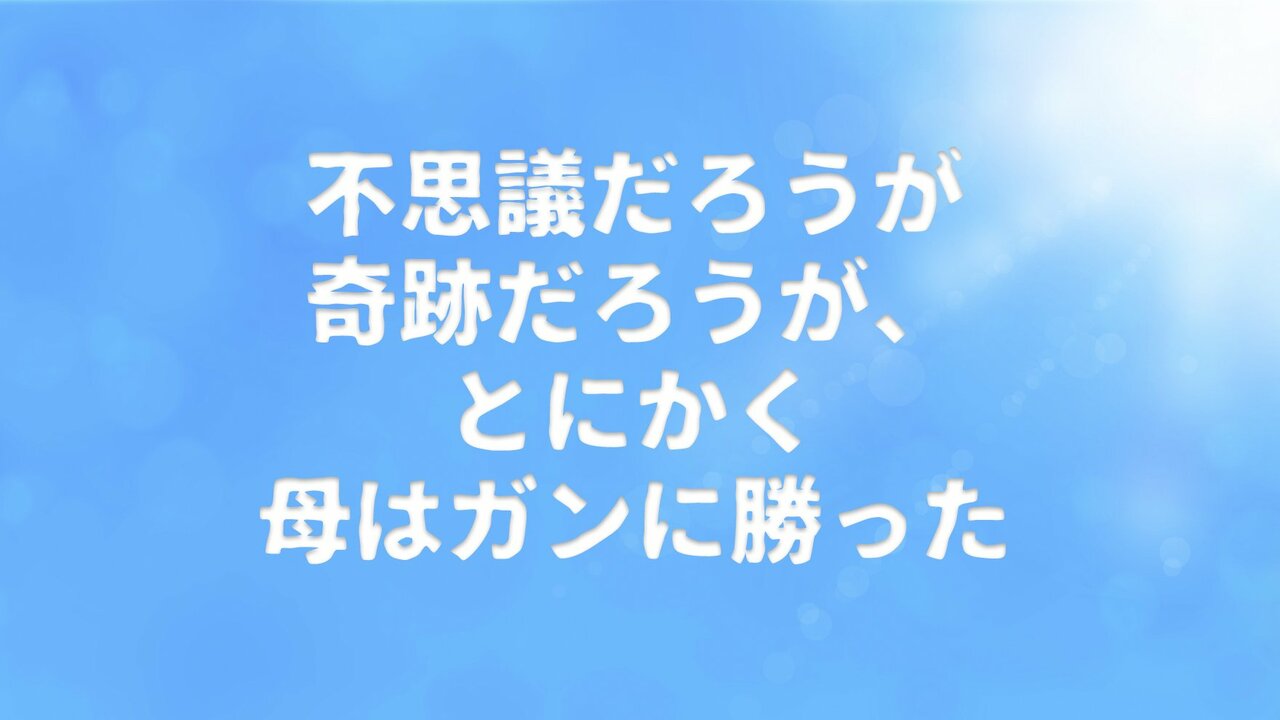第一章 青天霹靂 あと377日
二〇一六年
一月十六日(土)
「あの着物どうしようか……。セツコさんにあげるって言ってたの、まだ何枚かあるんだよ……」
ふと思い出したように母が言った。セツコというのは私の唯一の女友達で、初めて逢ってからかれこれ八年にもなるが、今もって恋人未満の関係を脱しない。
よく笑う明るい女でありながら、竹久夢二の美人画のような憂いを隠し持つ彼女は、未だかつて恋愛感情というものを誰にも持った事がないという特異な性質だ。会えば必ず喧嘩となるのに、しばらくすると再びケロリと現れ、我が家のロフトに十日ほど住みついてはまたふらりと出ていく。
一昨年夏の九州旅行の時も、母親の実家である福岡へ帰省していた彼女を連れ出し、旅の半分ほどを三人で車中泊したという妙な仲である。思えば、家庭を持つ縁に恵まれなかった私であるけれど、それを諦めかけていた母に、擬似家族のような経験をさせてあげられたのはいい事だったかも知れない。
いつだって、カメラをかまえるのに夢中な私に代わり母の手を引き、温泉の湯殿では杖となってくれた。きっと、母もさぞ気丈夫であり嬉しかっただろうと思う。
それにしても、あの旅は楽しかった。行き当たりばったりの性分である私の運転に、ガイドブックを手にしたセツコが「あっちへこっちに」と甲斐甲斐しく案内をした。「悠久の自然と神々の故郷」と、音に聞いた宮崎の“高千穂峡”では、大瀑布のマイナスイオンを全身にあびつつ吹き出す汗の退く思いを得て、「こりゃ良い冥土の土産になるわい……」と、母は笑った。
大分の“岡城跡”では、「グッドニュースだよ! 開園前の時間なら上の御殿跡広場まで車で登れるんだって……」と、早朝の散歩に出ていたセツコが跳び帰り知らせてくれた。