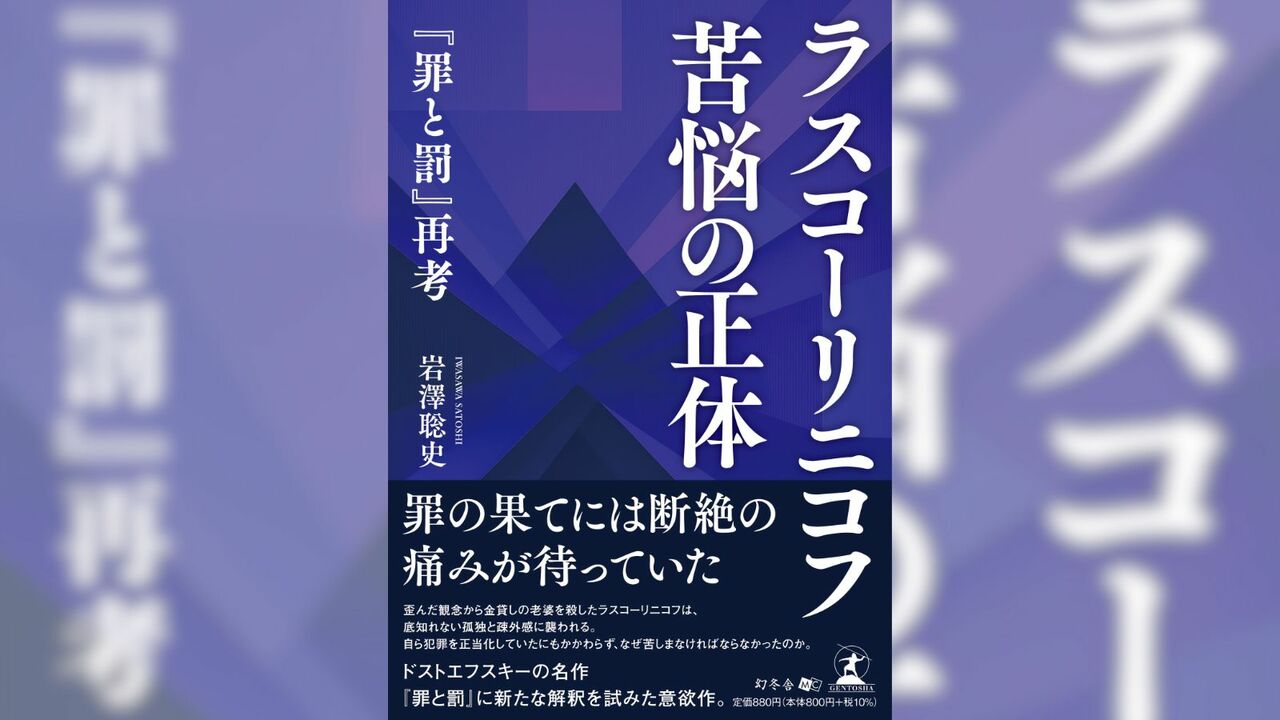【前回の記事を読む】殺人の後、自責の念は全く無く「あの汚らわしい、貧乏人の生き血を吸っていた婆ァを殺したことが、それが罪なのかい?」
第二章 様々な解釈
ラスコーリニコフは金貸しの老婆を殺害した直後から、地上のいっさいのものや人間から切離されてしまったような「無限の孤独と疎外」の感覚に襲われる。
生涯で初めて体験するほどの、この苦しい「感覚」は、決して善悪の観念に基づく悔恨や自責の念などではなかった。彼の犯行は「選ばれた非凡人は法の枠をふみ越え、流血を犯すことが許される」という思想によって正当化されたものであったのだ。
だとすれば、ラスコーリニコフに耐えがたいほどの苦痛を与えるこの感覚は、いったいどのような由来で生じたものなのだろうか? この「謎」を解くことが『罪と罰』を理解するための重要な鍵であるに違いない。
『罪と罰』で提起されたこの「謎」、この「感覚」について、著名な研究者・批評家はどのような解釈をしているだろうか。
以下では、この「感覚」に対して注目し、あるいはなんらかの解釈を行っている先行研究の事例として、文芸評論家の小林秀雄(一九〇二‐八三)、ロシアの宗教哲学者であるニコライ・ベルジャーエフ(一八七四‐一九四八)、ロシア系ユダヤ人の哲学者レフ・シェストフ(一八六六‐一九三八)、ロシア文学者の江川卓(一九二七‐二〇〇一)の四人の議論をごく簡単に紹介する。
小林秀雄
小林秀雄は、『罪と罰』に関する前述の難解な評論において、この「感覚」に特別な注意を払っている。小林は、ポルフィーリイ予審判事の追及等により、いよいよ自分の犯行が露見しようかというところまで追い詰められた際のラスコーリニコフの心理を描いた次の一節に注目する。
「実に奇怪な話で、誰もそんな事を信じないかも知れないが、彼は現在目前に迫った自分の運命について、ほんのぼんやりとした微(かす)かな注意しか払っていなかった。何かそれ以外にずっと重大な、並々ならぬものが彼を悩ましていたのである――
それは彼自身の事で、ほかの誰の事でもないけれども、なにか別の事で、何か重大な事なのである。それについて、彼は限りない精神の疲労を感ずるのであった。」(第六部三 日本語訳は小林の評論による)(1)
犯行が露見する惧(おそ)れ以上にラスコーリニコフを悩ませていたものとは、先に述べたように犯行後の主人公を突然襲った「恐ろしい感覚」のことにほかならない。