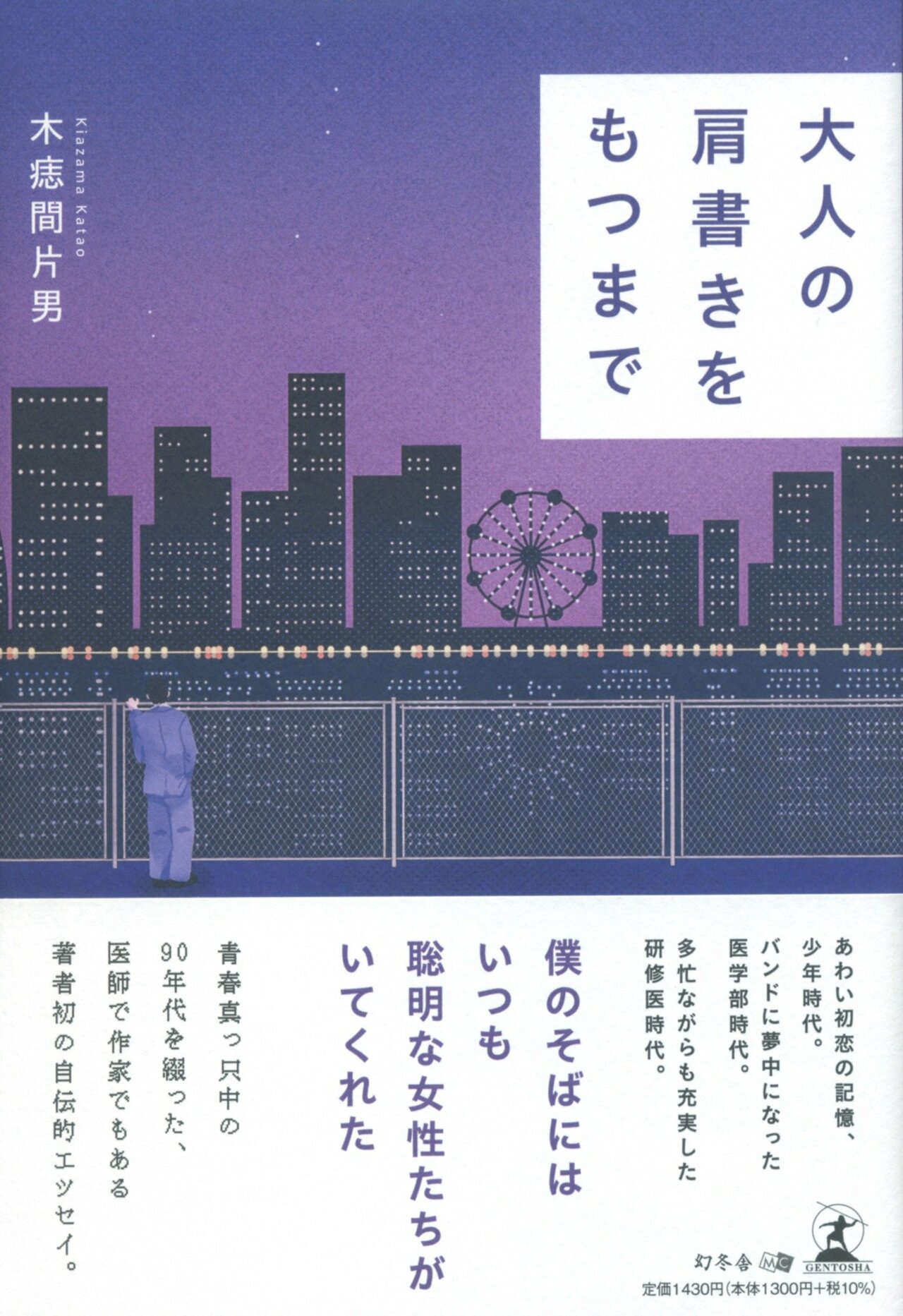だがまあこういうのも慣れである。最初はしどろもどろだったが、徐々に「いらっしゃいませ~♪ ドーナツいかがッスかぁ~♬」くらいは普通に叫べるようになった。
そのうち、「どこから来たの? 何高校?」なんていう単純な質問までなら、なんとかできるようになった。まあまあ、そこそこがんばったとは思う。僕の呼び込みが売り上げの一部に貢献したのは間違いなかった。
さて、営業が終わりかけたころ、教室の前に3~4人の女子がいた。作業をするふりをして、何気なく教室から出ようとしたときだった。
「あの~、すいません…… これからちょっと時間ありますかぁ?」
んっ、僕ですか!? 信じられないことって起こるものだ。なんと、その女子高生らは――後で知ったのだが、1年生――、僕を目当てに出待ちをしていたってことだ。途端に上から目線になって申し訳ないが、はっきり言ってそれは必然的なことだった。
高校生活における最後の最後のチャンス、僕は、この日のために時間に時間をかけて入念に準備を重ねてきた。
まずは髪型を変えた。散髪決行の日は友人と一緒に入店したのだけれど、地元の床屋からいわゆる美容院へと切り替えた。いまで言うところの〝アップバング〟だ。ヘアーカタログを見せながらカットしてもらった。
それから、以前は眼鏡をかけることが多かったけれど、コンタクトレンズに統一した。さらに学生ズボンは、当時流行っていたノータックのスリムラインのものを新調し、シャツは白シャツであればなんでもいい校風だったので、カジュアル感のあるものをメンズショップで購入した。
そして、最後に革靴を買った。布製のデッキシューズを履いていたのだが、学生にとっての最高級ブランド、〝リーガル〟のローファーに変更した。
しかもダーク・ブラウン。さらにさらに当日は、月桂樹のロゴで知られるロンドンの服飾ブランドのストライプカーディガンを羽織るという離れ技をやってのけた―これは叔父さんから以前にもらったものだ。
トークは、前述のように慣れてくればなんとかなった。いざとなれば流行の音楽の話題なら、けっこう自信がある。
あとは持ち前の高身長を活かし、切り札として〝医学部志望〟という、そんな万全な体制を敷いての文化祭だった。努力って報われることもあるんだなぁ、そう思った瞬間だった。