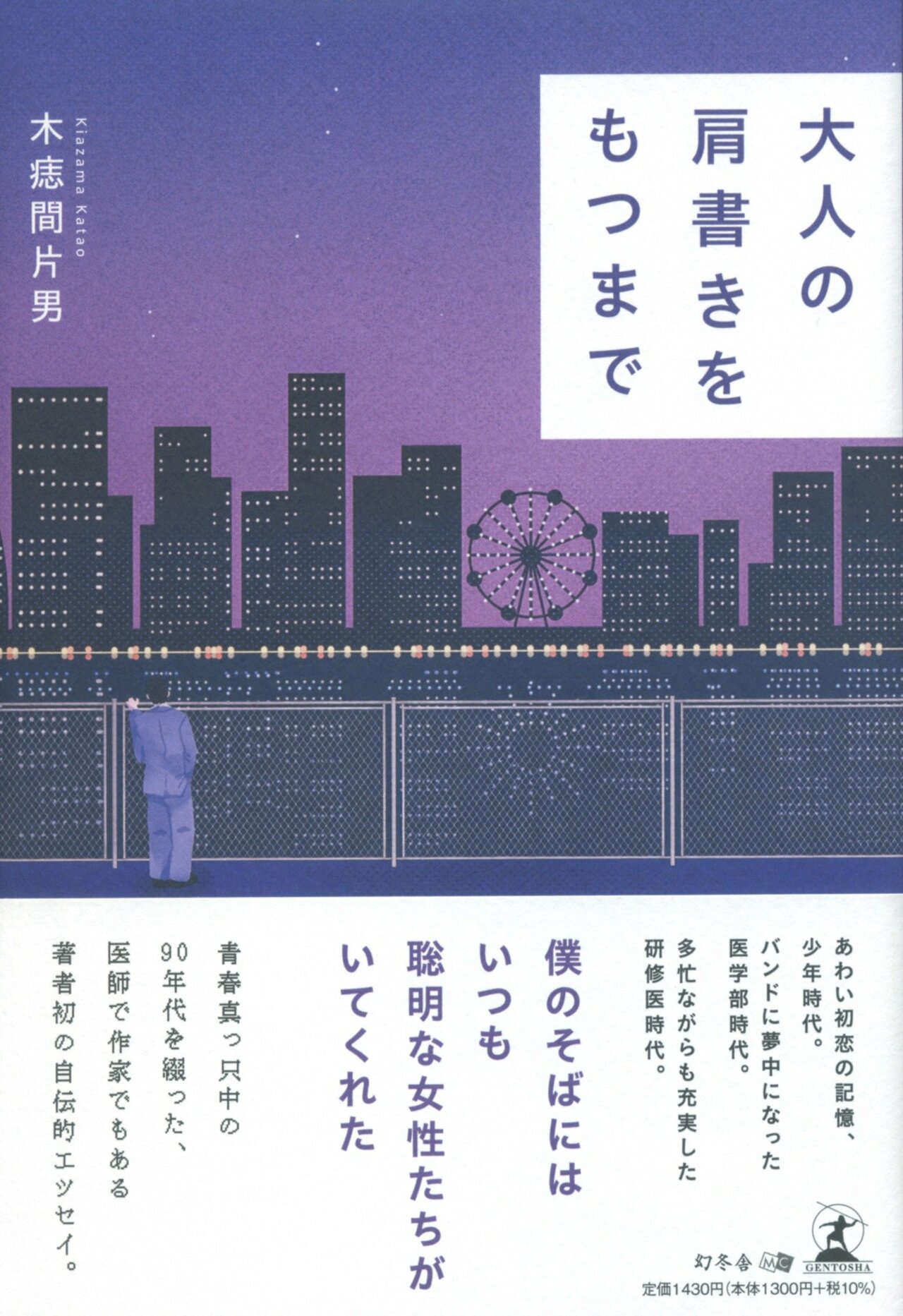【前回の記事を読む】「あんまり、他の男子とは遊んだりしないよ」いつまでも記憶に残る言葉。高校生活を惰性で送る僕の心をわし掴みにしたのは…
第1章 中学・高校編
きっかけはインドア派芸術女子 「放課後も一緒にいたいから同じ塾に通って」
当時の自分は、他人から見れば無気力世代の典型だったのではないかと思う。繰り返して申し訳ないが、何の情熱ももたないただの子供だった。
それでもひとつ言えることは、恥ずかしい言い回しになってしまうけれど、あれもひとつの青春の形だった。冴えないどこにでもいるような、マンガとアニメと音楽とを嗜むことくらいしかなかった平凡な男子高校生が、年に2回とはいえ女子友だちと会って遊ぶ、これだけでも高校を過ごしてきた価値がある。
成績が下がろうが、運動が苦手になろうが、発言の機会がどんどん減ろうが、「木痣間くんは背が高いから、がんばればもっとカッコ良くなるよ」と言われた、たったその一言が僕の高校生活を支えていた。
冒頭から暗い過去を明かしてしまったが、高校の想い出を語る理由は、僕の女子に対する原点がこの期間にあり、このころの記憶をなんとかきれいな形で残しておきたいという葛藤、もっと言うと願望があるからだ。
と、そんな感じの高校生活であったが、このままでは惨めなまま終わってしまうので、名誉挽回、男子校時代の最後に一瞬のきらめきを放った、僕にとっての一度だけの〝ハイスクール・ドリーム〟を語らせてもらう。
大学受験に対してお尻に火の付きはじめた時期ではあったが、それは高3の文化祭だった。毎年9 月下旬に行われ、男子校生が女子と触れ合うことのできる、年に1回のチャンスだ。
こんな僕にとっては、楽しみでもある一方、ツラい2日間でもあった。すなわち、期待したことが何も起こらないということを繰り返した、過去の2年間だったからだ。
クラスがまとまっていたせいもあってか(どうかは定かではないが)、喫茶店を出店しようということになった。システムは簡単である。地元のお菓子屋数件から当日の朝、大量にドーナツとケーキを購入し、それをちょっと加工して売りさばくという、至ってシンプルな横流し商法である。
コーヒーやジュースも、ペットボトルをただコップに移すだけ。まあ、高校の文化祭なんてそんなものだ。
教室の改装を整え、当日、僕に与えられた担当は客の呼び込みだった。口下手でシャイな人間にそんな役割をさせるのもどうかと思ったが、そこはお互い様だった。
快活な生徒や運動部の連中は、運営に関わる作業やら、クラブでの催しやらに借り出されていたから、要は帰宅部のような連中しか残っていなかったというわけだ。