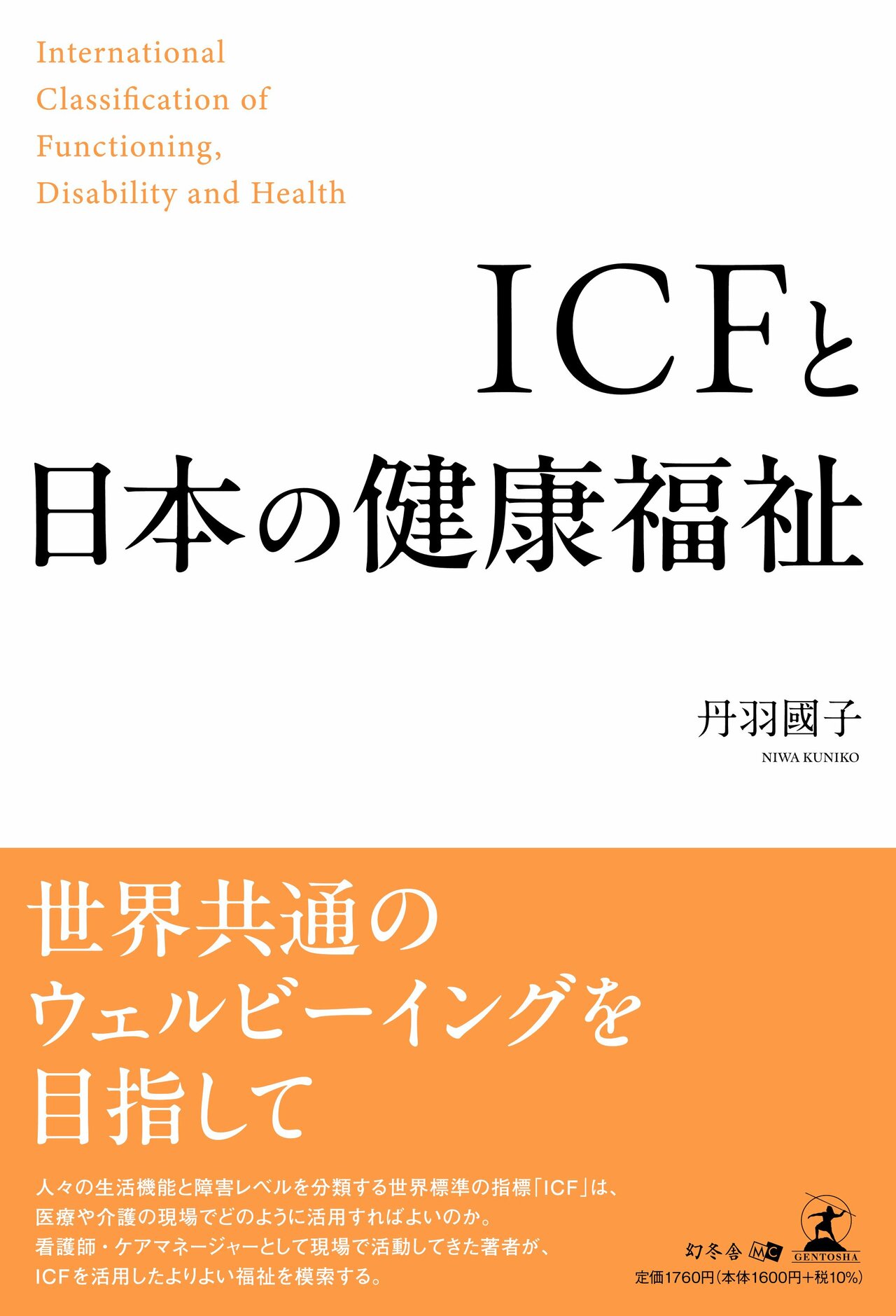第4節 今日の日本の様相
近代日本には、わが子を朝・夕の賄い付(=食事付き)で健康管理にまで気を使う家主の部屋に下宿させて、高等学校を受験させる親もいました。また夏目漱石の「坊っちゃん」の清さんのようなお手伝いさんを雇い、わが子の健康と自立を見守るケースもありました。
しかし、これらの親の行動規範と家庭の伝統や文化は、第2次世界大戦終戦(1945年)後、日本国憲法第24条「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」を基本として、戦前の「家制度」を公式に否定し、核家族を世帯にして以来、日本人の行動規範や生活様式は一変しました。
その歴史過程で失ったもっとも大切なものは、次の世代に引き継ぐべき「良い食習慣」や「人との交わりのマナー」「良い生活習慣」「生活の智慧」です。
これらは憲法第25条に規定された「健康で文化的な最低限度の生活」の基盤である人間の躰の宿命と発達・退行のメカニズムに応じた健康な生き方習慣を獲得するために欠かせないものです。自助(セルフケア)や他者へのケアである地域における共助(ボランティア)にも深い関係があります。
つまり、「ハビリテーション(=Habilitation:人間の衣を着せる意:転じて、健康な生き方の習慣を纏う意)」不足の人間を育て、その人たちが親となり、後天的遺伝である世代間伝達を次の世代に引き継いでいることです。
精神障害に至る過程には生活習慣が大きく影響することが知られています。ストレス管理、運動、睡眠、食生活などが精神的な健康に重要な役割を果たします。
諸外国では、第2次世界大戦後に公立病院内に生活訓練施設を設けて、入所者5- 7人のチームで一人ひとりが生体リズムに合致した生活リズムを習得するため、早寝・早起き・たっぷり朝ご飯と散歩・労働・睡眠のできるスケジュールをチームカンファレンスで話し合って分担し、
担当した労働を交代しながら繰り返し、カンファレンスで評価をし、生活習慣を築く訓練をして就職という方法で、一人ひとりの生活機能の自立と自律を協働生活訓練によって確立して社会人になり自律して行きます。