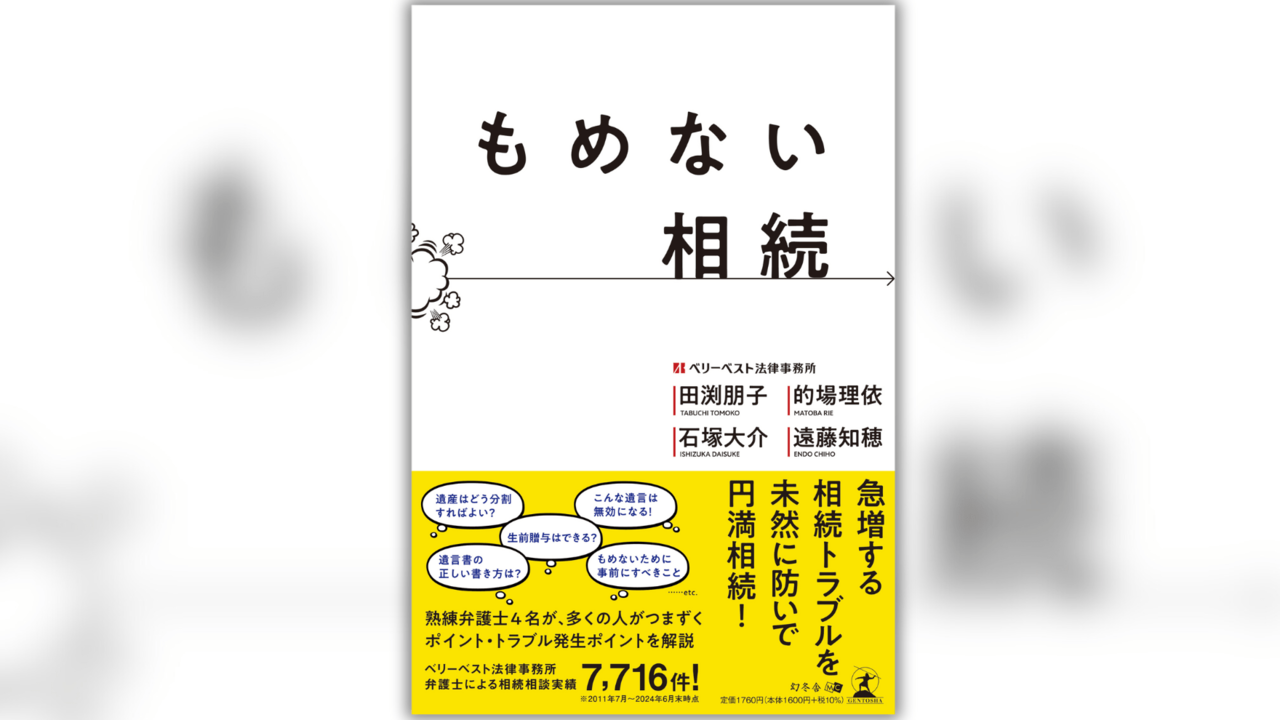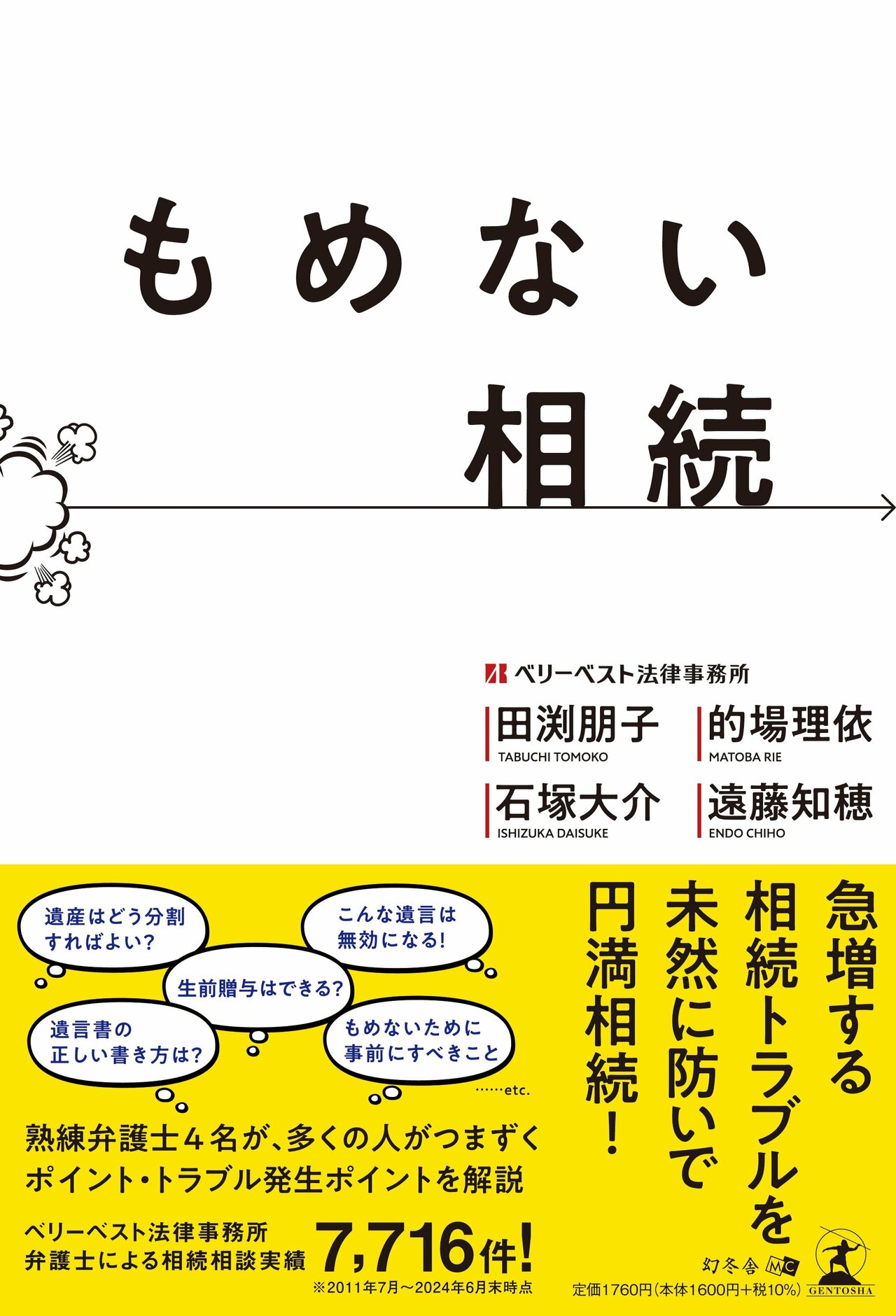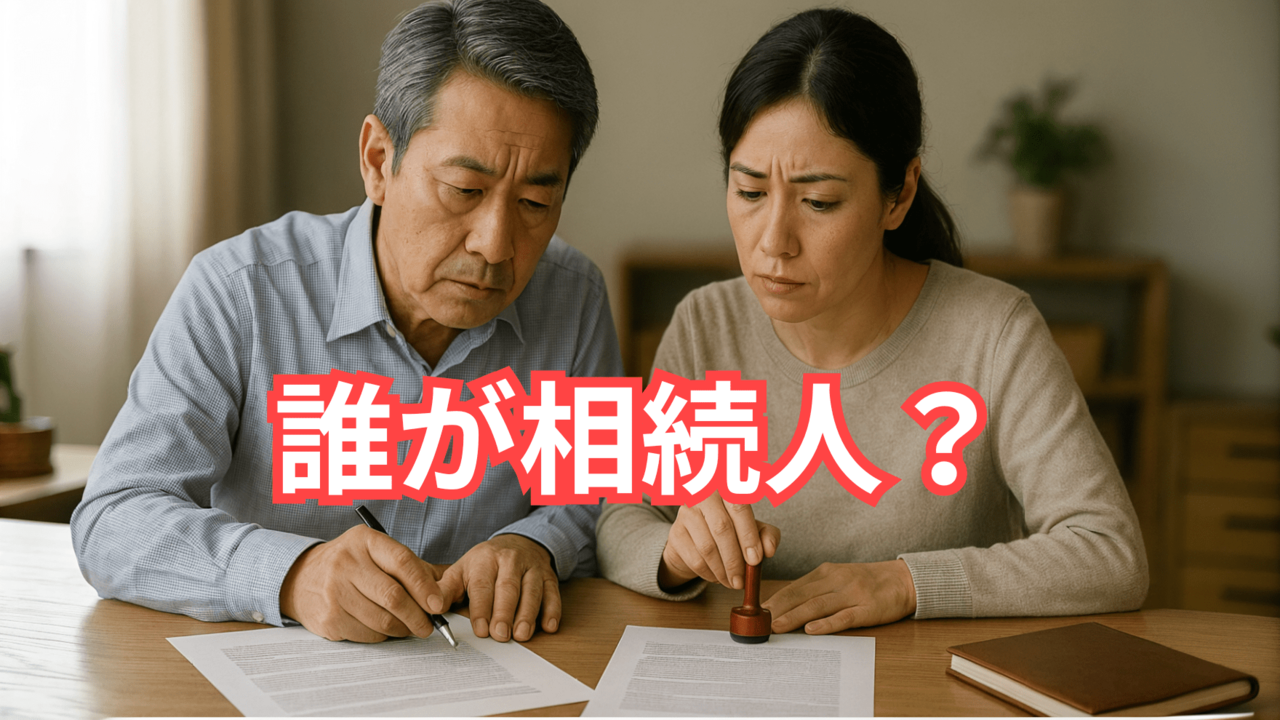【前回記事を読む】「誰が相続人?」で困らないために! 遺産分割協議書の書き方や印鑑の押し方まで丁寧に解説
第1章 遺産分割(石塚大介弁護士)
2 相続人の範囲
(4) 相続人について注意すべき点
①意思能力・行為能力に問題がある場合
相続人に認知症の人がいる場合など、そのまま協議を進めてしまうと、後に無効となってしまう可能性がありますので、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をする必要があります。
なお、すでに成年後見人がついているが、その成年後見人も相続人である場合には、以下で述べる特別代理人の選任を申し立てる必要があります。申し立てることができるのは、成年後見人と利害関係人です。
ただし、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人が被後見人を代表するため、特別代理人の選任は不要です。
②胎児がいる場合
民法は胎児について「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす」(民法第886条1項)という規定を設け、相続に関して胎児の権利能力を認めています。そのため、相続開始時に胎児である場合も、相続人になります。これは無事に生まれてきた場合だけで、死産となった場合には、はじめから相続人ではなかったということになります。
そのため、胎児を無視して遺産分割をしてしまうと、胎児が無事に生まれてきた場合に、参加させるべき相続人を除外して遺産分割をしたこととなってしまいます。出産前に遺産分割協議をしても、出産後に協議をやり直すこととなってしまうため、出産してから協議をした方がよいでしょう。
③未成年
相続のルールを定める民法において18歳未満の方は未成年者とされ、単独での契約締結などの一定の法律行為をすることは制限されています。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効とされますが、その一方で遺産分割協議は財産の移転に関する権利を生じさせる法律行為であるため未成年者が単独で参加することができません。
そのため、相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議をすることができませんので、未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする、もしくは、未成年者の法定代理人が遺産分割協議をするという手段を選ぶ必要があります。