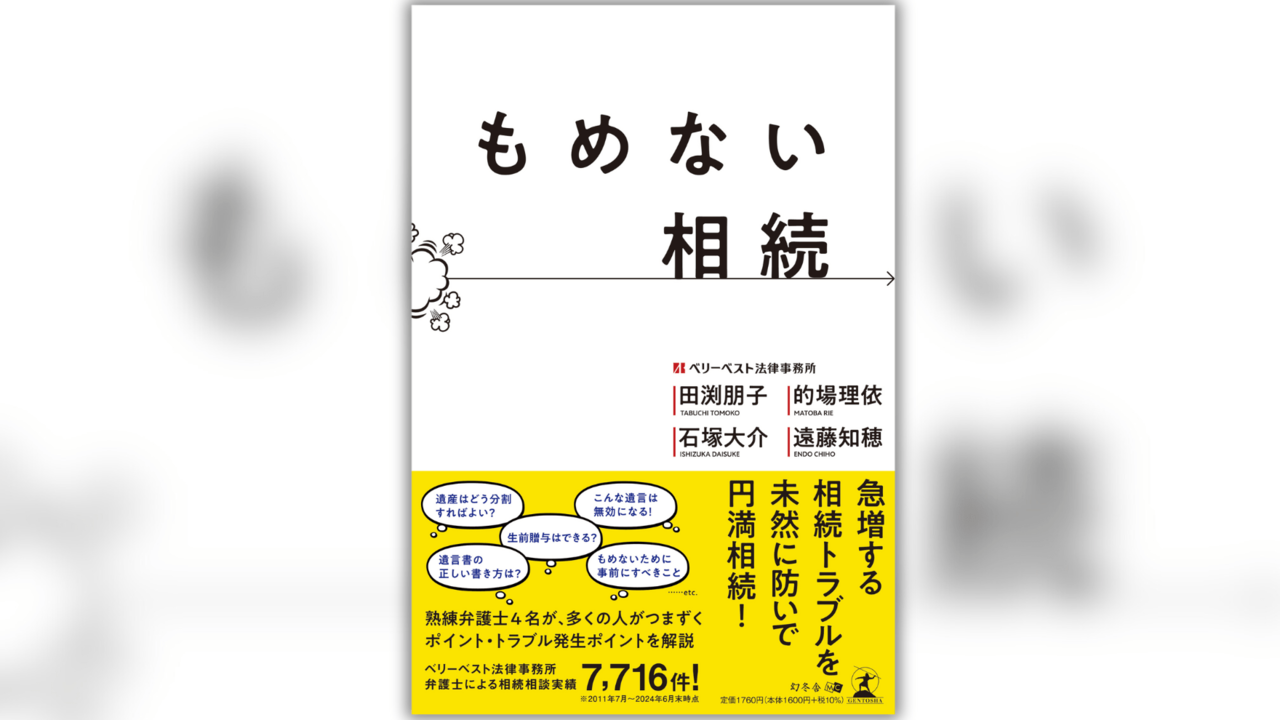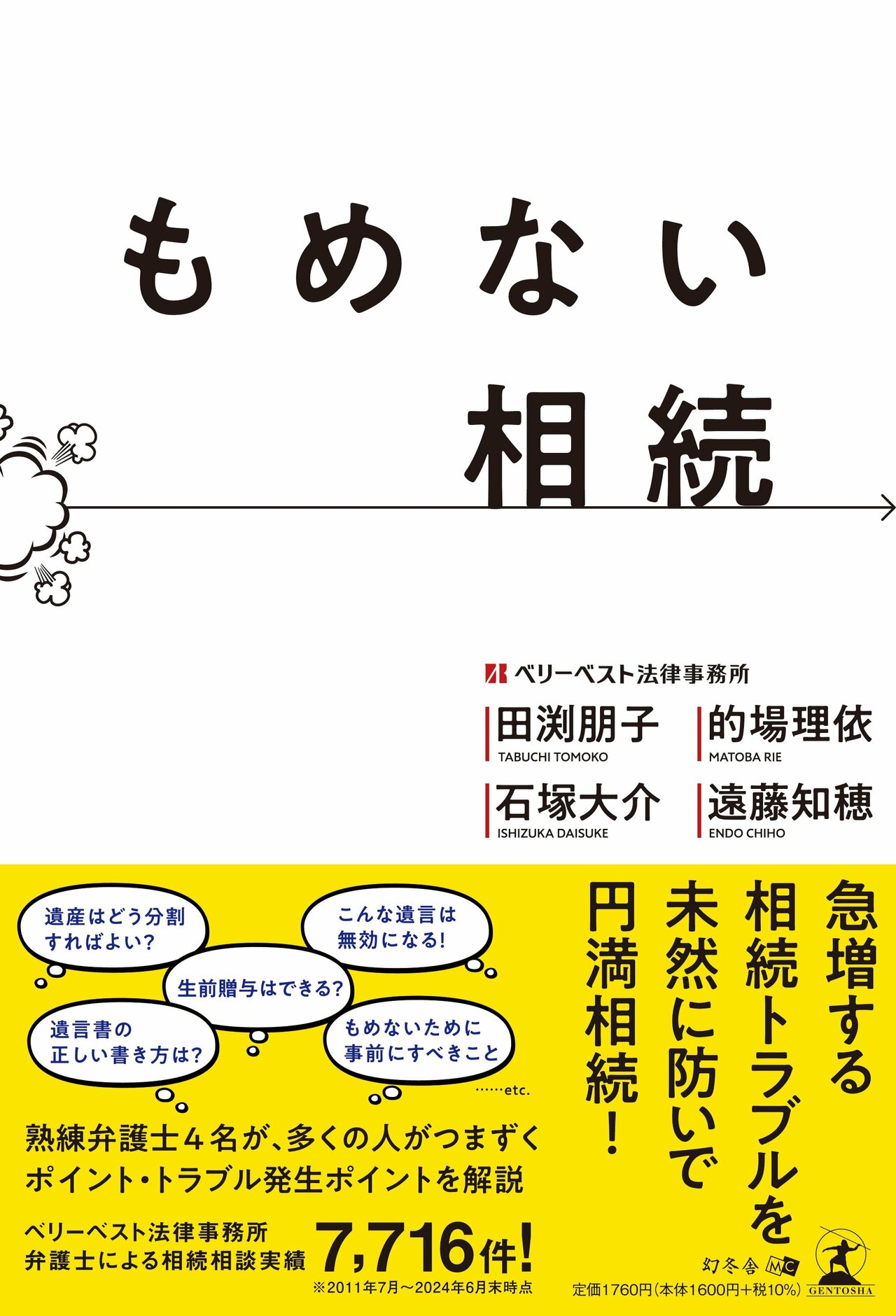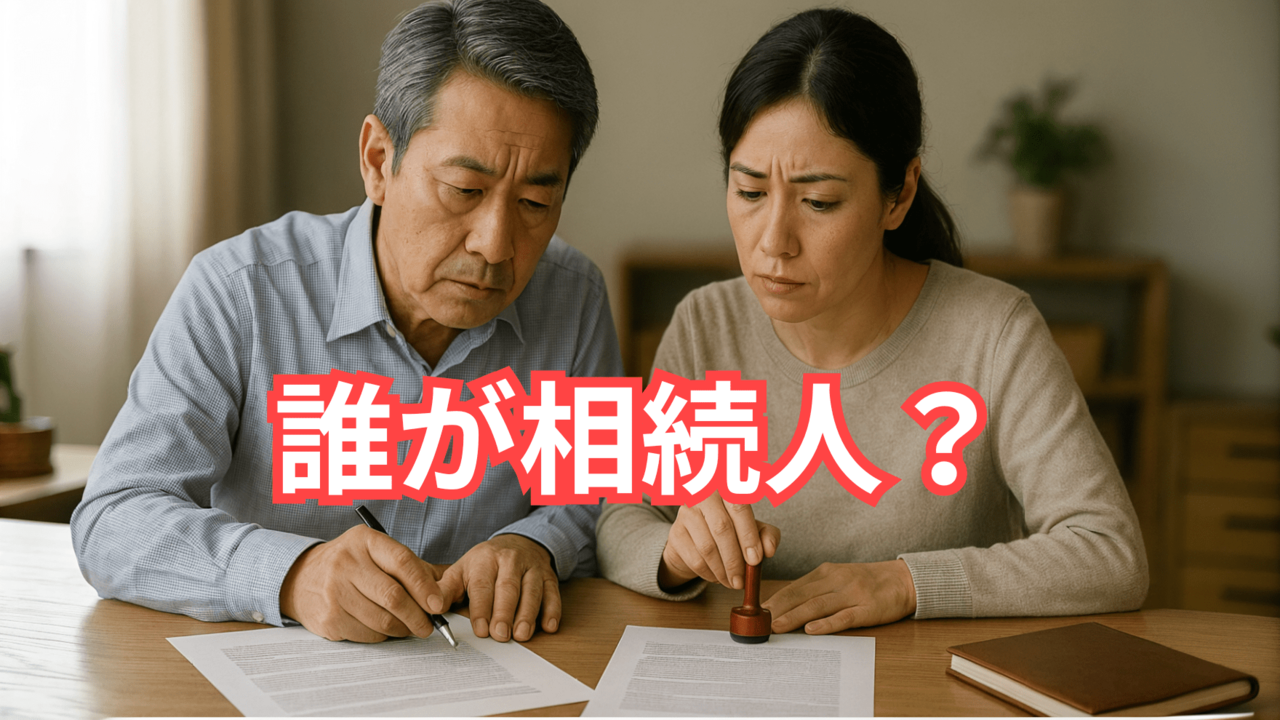第1章 遺産分割(石塚大介弁護士)
(2) 遺産について確認することの流れ
注意いただくこととして、令和3年に法律が改正され、令和6年4月1日から、相続登記の申請をすることが義務になります。相続(遺言も含みます)によって不動産(土地、建物)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をする必要があります。上記のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となりますので、不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。
(3) 遺産分割とは
①遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、被相続人の遺産について、誰が、どのような遺産を、どのくらいの割合で相続するかを話し合う手続です。
被相続人が遺言書を作成せずに死亡した場合には、被相続人の遺産は、法定相続人の法定相続分に応じた共有状態となります。遺産分割をしないままの状態では、遺産である預貯金は被相続人の名義のままであり、その払い戻しをすることができません。
不動産についても被相続人名義のままでは、不動産の自由な処分も困難になります。そのため、遺産の中に預貯金や不動産等がある場合には、名義変更の手続をするためにも遺産分割協議によって遺産分割方法を話し合う必要があります。
②遺産分割をする時期
被相続人が亡くなった後に遺産分割を行います。被相続人の生前に遺産分割協議をしても有効にはなりません。遺産分割は、被相続人の有効な遺言書がないような場合や遺言書があっても遺産分割協議が必要な場合に行うこととなるため、まずは遺言書がないかどうか調査をします。
遺言書の調査をしても見当たらない場合には、遺産分割協議を行います。なお、遺言書がある場合でも、例外として相続人全員で遺言書と異なる分割方法について協議をすれば、そのように分割することも可能です。
③遺産分割協議をする当事者
遺産分割をする当事者は、相続人の全員です。相続人が一人でも参加をしていない場合には、その遺産分割協議は無効となります。
④遺産の分割の仕方
遺産の分割は相続人にて協議して決めるものです。その分け方には法定相続分という目安はありますが、これに従う必要はありません。相続人の全員で納得する場合には、好きなように遺産を分けてしまって問題はありません。
ただ、被相続人のマイナスの債務は自由に分けることはできません。遺産相続によって債務を自由に変更できるとなると債権者に不利益となってしまうからです。被相続人のプラスの資産について協議して分割方法が決まりましたら、それを遺産分割協議書にまとめます。