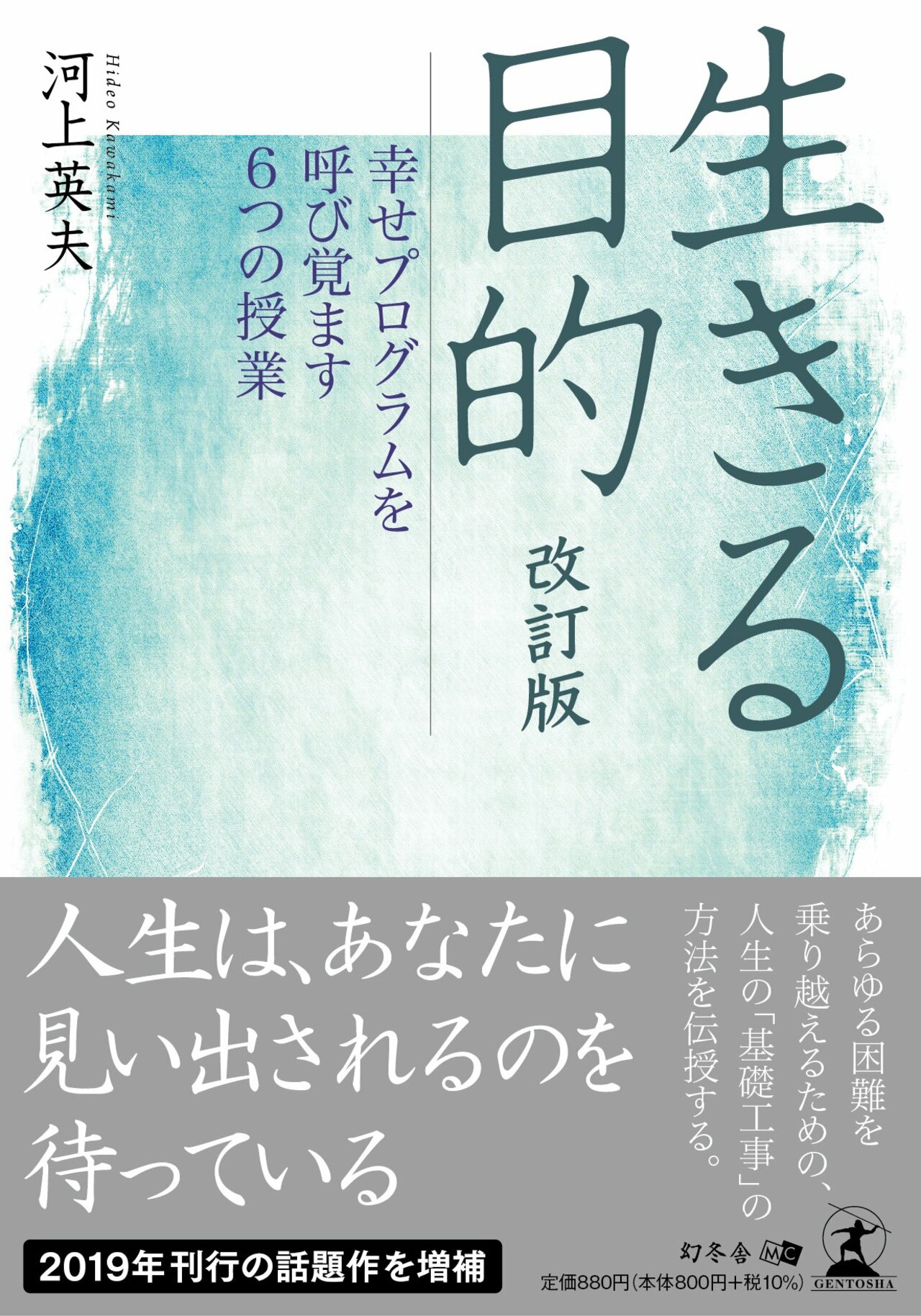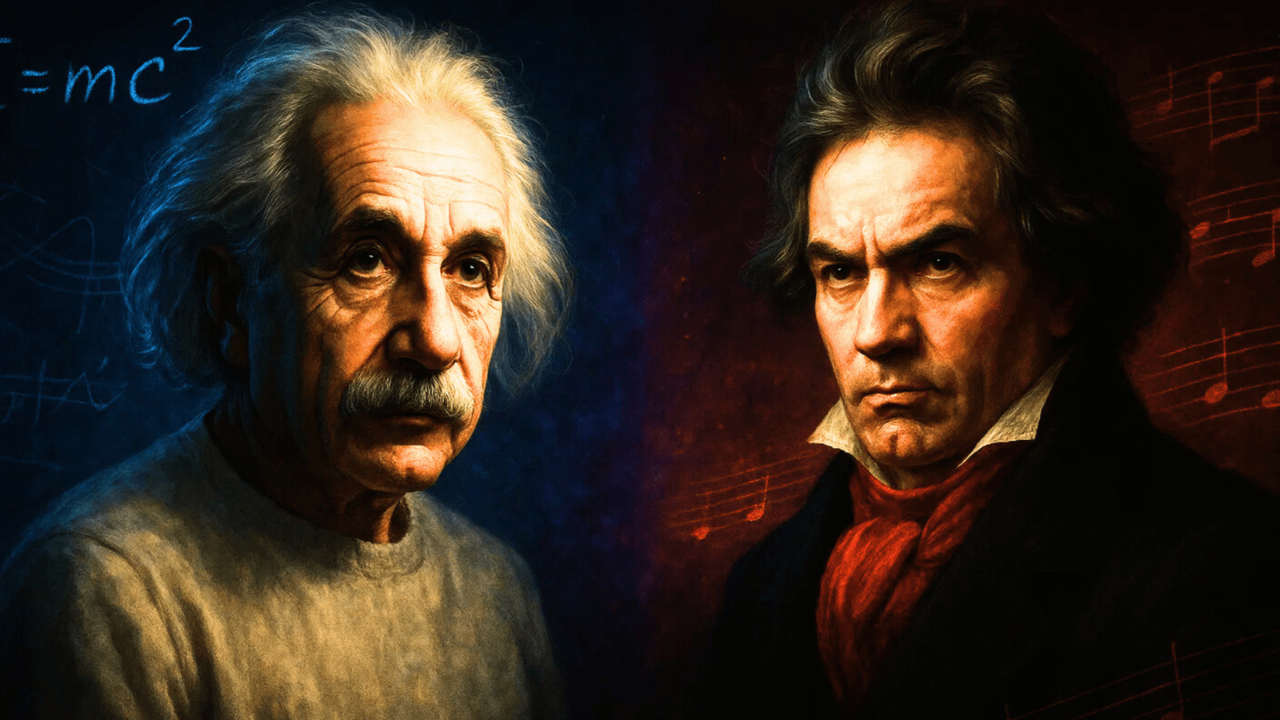四 社員研修での生きがい探し
私は社員七百人ほどの物品販売業を営む企業の社長や会長を三十年続けてきた。そして自社の新入社員教育において、自己実現とはどういうものかを実感してもらうために、私の担当時間にオリジナルな教育をしてきた。
この教育の主眼は新入社員にとってはともすれば一方的な押しつけ教育となる面を軽減し、自分たちで発表する機会も設けることで緊張感と自発性を持たせることにある。新入社員からの評判も、よく理解できたと好評だった。
もちろん、会社の総務や人事、営業や経理といった組織の担当者はそれぞれの部門に応じて専門的教育をしている。
私の教育内容は、これからの社員生活の中でいかに自己実現をしていくか、自分の業務を通じていかに社会貢献をするのか、そしてその結果として、自分の生活の安定を図ることができるようにするとともに、生きがいのある社員生活を送るにはどうすればいいのかという、社会人として基本的なことを体感してもらうものだった。
こうしたことは講師がいくら口を酸っぱくして語ったとしても、社会人としての経験が皆無な新入社員には全く届かない。私は自分たちに考えさせて自分たちで結論を出させるという方法を採用した。
会社が押しつけた結論ではなく、これからの社会人としての生き方はどうあるべきかを、自分たちで考えて出した結論だからこそ、誰しもが納得して実行に移せると考えたからである。
具体的な方法はKJ法というデータをまとめるために有効とされている方法を使っている。KJ法は、文化人類学者の川喜田二郎氏が開発した、データを整理する方法である。
川喜田氏がネパールやヒマラヤの山中で人類の骨を収集していく中で膨大な情報をいかにまとめるか、その方法を模索する中で考案したもので、これによって人類の進化の過程を解明するための基礎情報を整理できたという方法である。
私が社員教育で行っている実際の方法を説明すると、最初にディスカッションのテーマを私が決める。テーマは毎年同じで、「生きがいとは」に決めている。テーマを発表すると毎年決まったように会場から「えー」という声が聞こえてくる。
抽象的で、これまで考えたこともないようなテーマだからこそ最初の反応は戸惑いの声になる。大切なことは、具体的で卑近なテーマでは底の浅いものになってしまうということである。