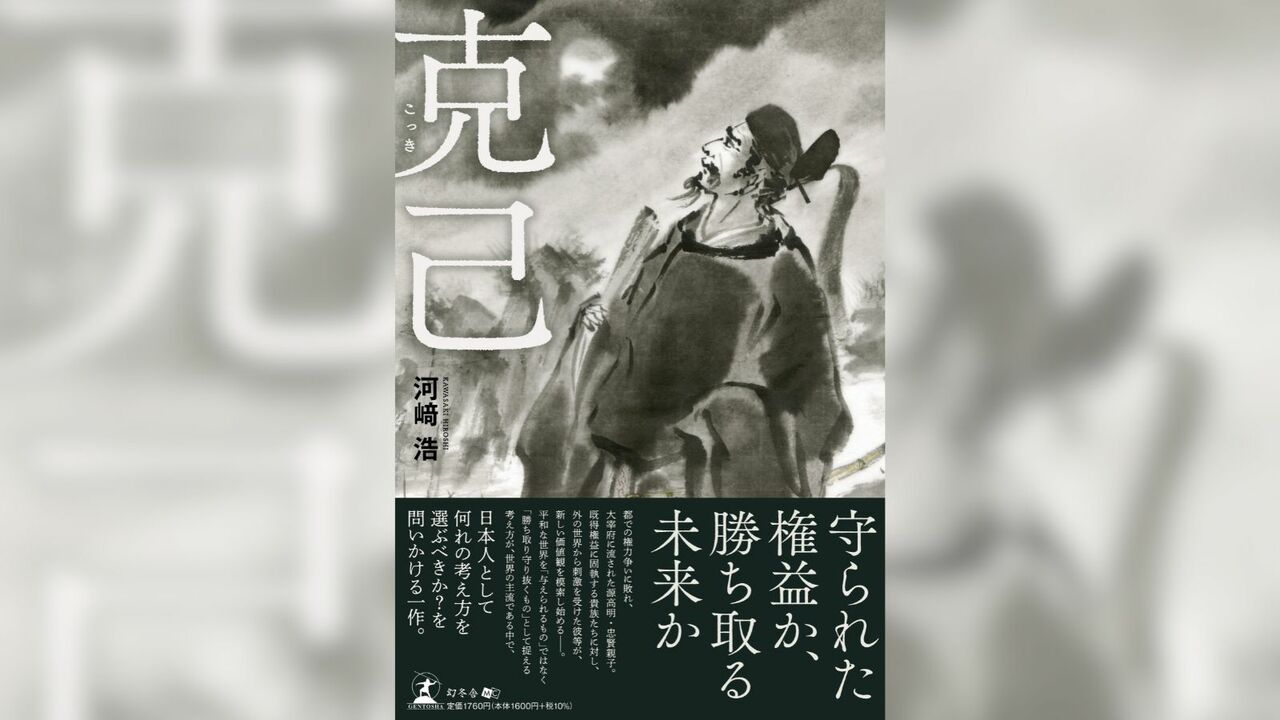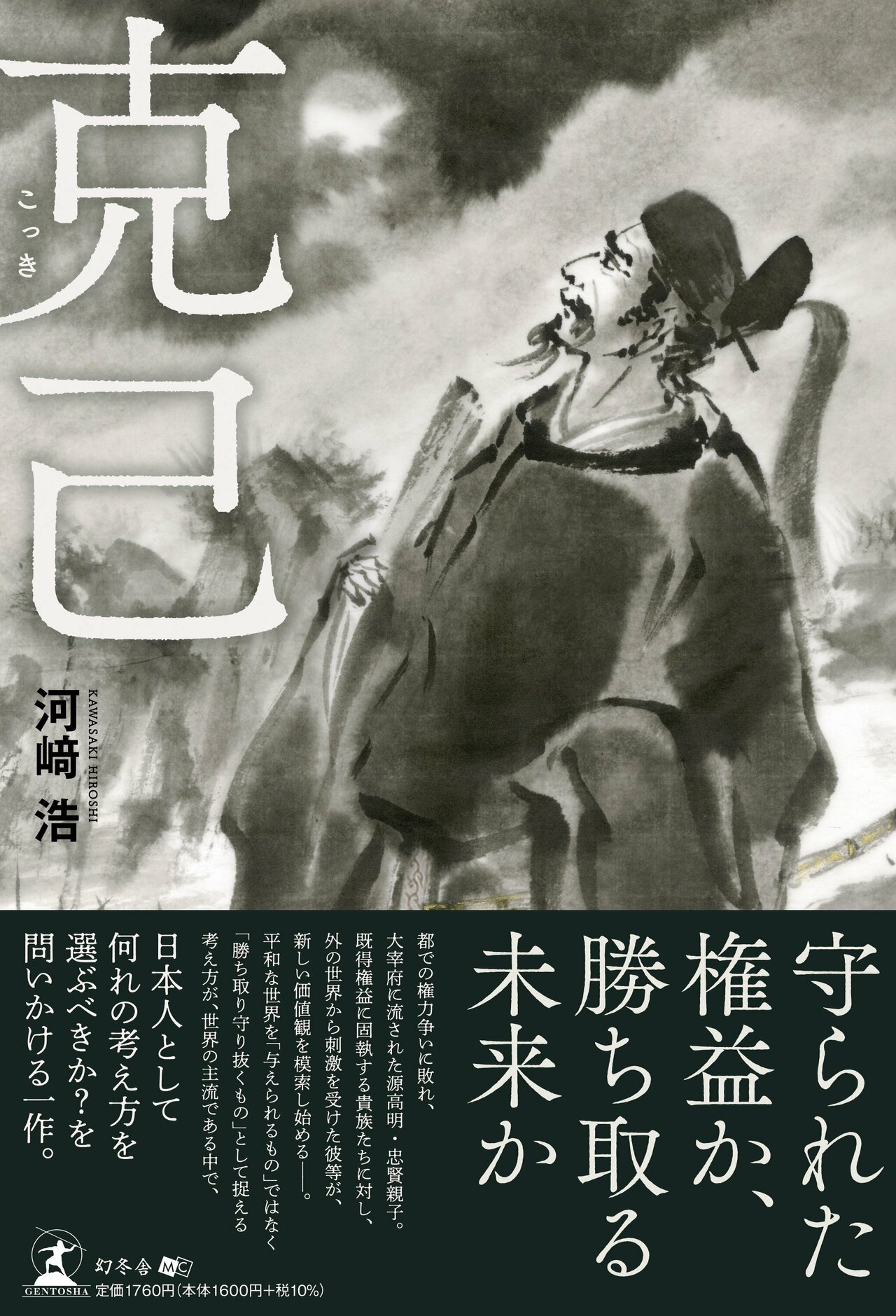【前回の記事を読む】大宰府に迫る海賊の脅威……都が知らなかった“防衛最前線”とは?
半年が経つ
当時は、現代と異なり、男女で役割がハッキリと異なっていた。
それ位、普通の女にとって、家事は、重労働であり、その殆どを課せられていた。
従って夜伽と詩歌音曲のみに明け暮れている〝都育ち〟の雅な女に、気を配らせ、此処で高明の期待する務めを果たす(期待する)事は、現実問題として、無理であった。
高明は、夜這いの夜、食事時、入浴時、誰とはなく、会話を交わす。地元で徴用又は、地元有力者が、遣わした女からの情報には、何ら偏見も自身の経験を基にした見解も持たず、それは生の、活きた地元情報で『在る』と認識して、これを参考にして判断を下し、官位や地位に拘わらず、彼が吟味した人材を適材適所に配置し始めた。
又、警護所と云う、実態として当初は、小屋レベルではあったが、地侍等が、集積できる防衛施設を設け、結果として余剰となった人員にも、それなりの役職を与えた。この警護所の長官は、大宰府で従六位下の監(じょう)クラス。
彼等から見れば〝高位〟の、都育ちの貴族が、当初は司として当たる事で、此処に配置される事を余剰人員の整理と勘繰る、選別された(下種な考えを未だ抱く)人間の不満を抑えた。
彼が着任以降、文官武官、身分・門地・官位を問わず、大宰府で禄を食む人間は。武芸が必須となり、当初は、都育ちの高位の文官も、官位ではなく、能力により、否応無しに機械的、且つ、公平公正に選別されて行った。
彼等の中から、指揮官と実動部隊の振るい分けも、身分・門地・官位の別なく公正公平で実力本位の適材適所な形で配されて行った。高明着任後、半年で、この体制は確立し、軌道に乗って行った。
当時大陸で支配の度を高めて行った〝宋〟から得る工芸品や絹や銭などの物品以外に、周辺の情勢分析は、大宰府の文官にとって、主たる仕事であったが、それ以外に半島の情勢、特に高麗と新羅の関係、其の北方の契丹や女真族の動向を探り、得た文書を読み熟し、分析する事も、この頃から始められていた。
ただ、その情報ソースは、全て受動的、即ち他国から齎(もたら)される情報であり、自らが動き得た能動的な情報ではないのが、現状の悩みであった。
要は、報告内容が、情報を齎(もたら)す場所の主観に偏りがちで、客観性が担保されていない事が、問題点であると、高明は、既に認識していた。