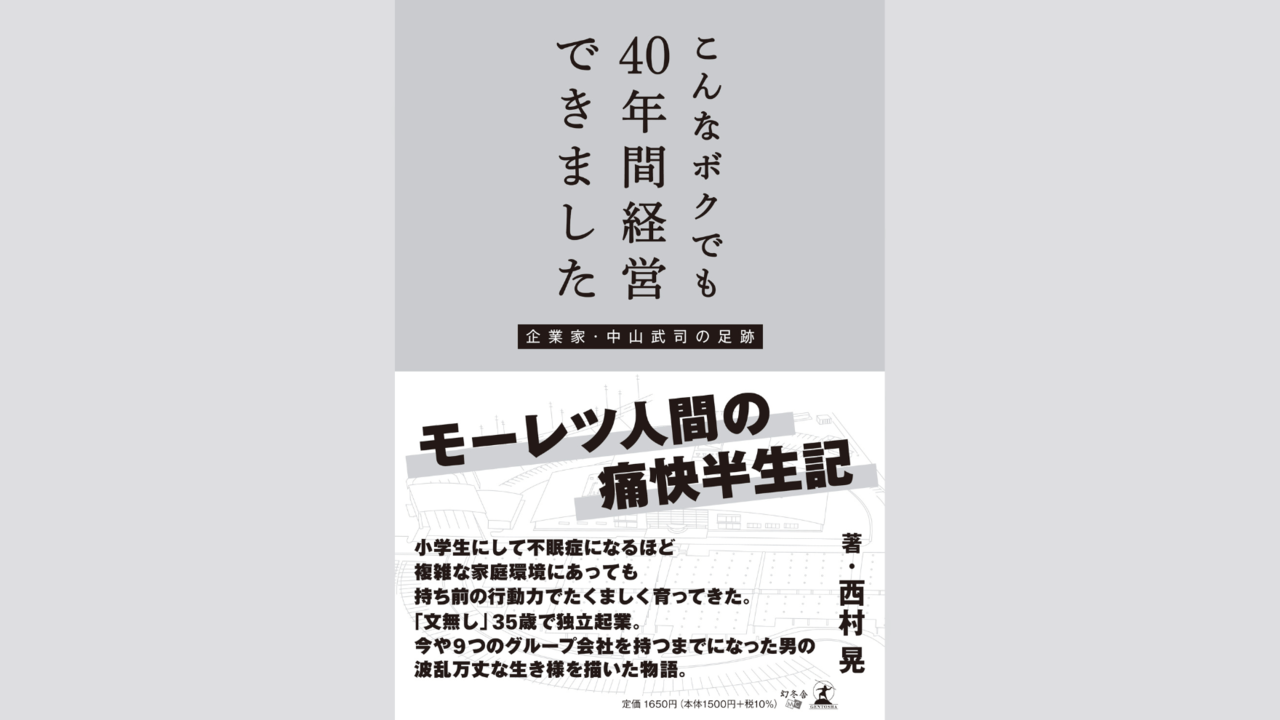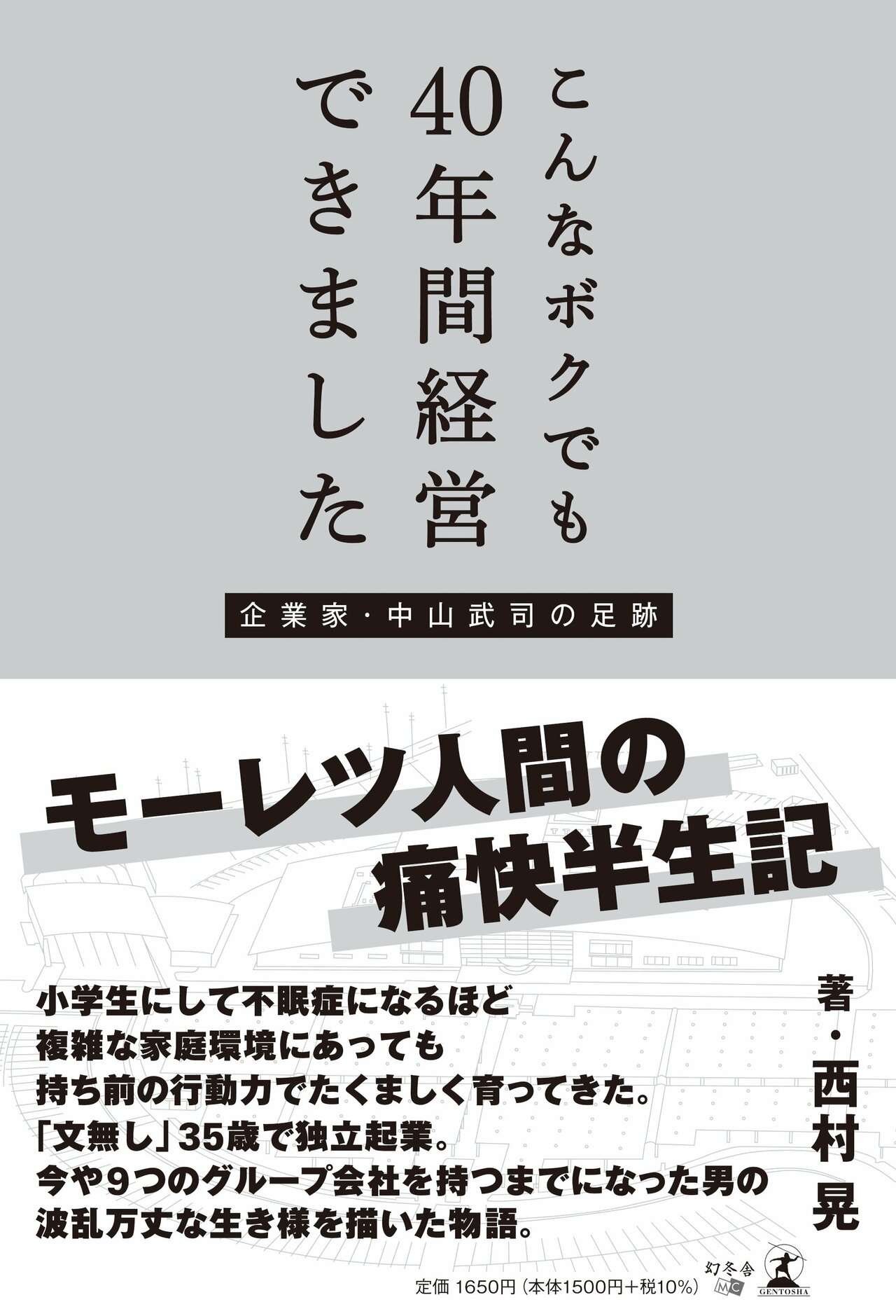【前回の記事を読む】叔父との結婚は、母の強い勧めだった。近親同士の婚姻は、戦後の混乱期には珍しくなく…
第一章 企画と失敗を繰り返した幼少期
両国の幼稚園時代
この幼稚園の最大の行事は学芸会だった。
七十年も前のこの学芸会で忘れられない「事件」があった。
中山武司はそのことを昨日のことのように語る。
「学芸会の劇の主役をやることと、閉会の辞を述べることは親たちから見れば我が子の最高の栄誉でした。その二つの大役をこともあろうに母が手を回して一人占めしてしまったのです」
中山の記憶によると、当時中山家は住宅の建て替え時期にあたり一時的に間借りした家がたまたま幼稚園の先生の実家であったという。その関係から母うめ子は先生と昵懇となり、息子武司の劇の主役抜擢と閉会の辞の役目を頼み込んだ。そしてそこにはいくばくかの謝礼も動いたようだ、と中山は振り返る。
劇の演目は『一寸法師とお姫様』。
舞台衣装店で着物を作り、専門店でかつらをあつらえると、小さな若侍のできあがりとなった。近所の友達は赤鬼と青鬼、主役との差は歴然としていた。いまならこんなことをしたら、ネットで批判され、幼稚園の存続さえ危うくなるかもしれない。そこはなんといっても戦後間もなくのことだった。
しかし結果として、赤鬼・青鬼の家族から、中山親子は総スカンを食らうことになる。
「結局は母の見栄っ張りな性格が引き起こしたことでした。私は嬉しいどころかそのことで友人たちから遠ざけられて寂しくつらい思いをさせられました。恐らく『武ちゃんなんかと遊ぶんじゃない』と友達は親から言われたんだと思います」
と中山は語る。
なぜこの制服で……
子供ながらも武司を悩ます「事件」はさらに続く。
母うめ子は、息子の一流校進学にこだわった。
文京区本郷にある東京教育大付属小学校を目指せ、というのだ。
いわずと知れた国立の名門校である。当時の選抜試験はまず第一関門にくじ引きがあった。何しろ戦後のベビーブーム世代で、小学校といえば一クラス五十人から六十人で一学年に十クラスもあった時代のことだ。案の定武司はくじ引きであえなく本試験前に脱落してしまった。
「まあ例え本試験を受けてもとても受からなかったと思います。ところが母は、それで納得しないんですよ。百貨店に行ってなんと教育大付属の制服を買ってきて、それを着て学校に通えというんです。だから小学校も地元墨田区立の学校ではなく、わざわざ文京区立の湯島小学校に越境入学させたんです。『うちの息子は文京区の東京教育大学付属小学校に通っている』という近所への見栄ですよね」(中山)
武司にとってこの小学校時代の思い出は屈辱的なものだった。