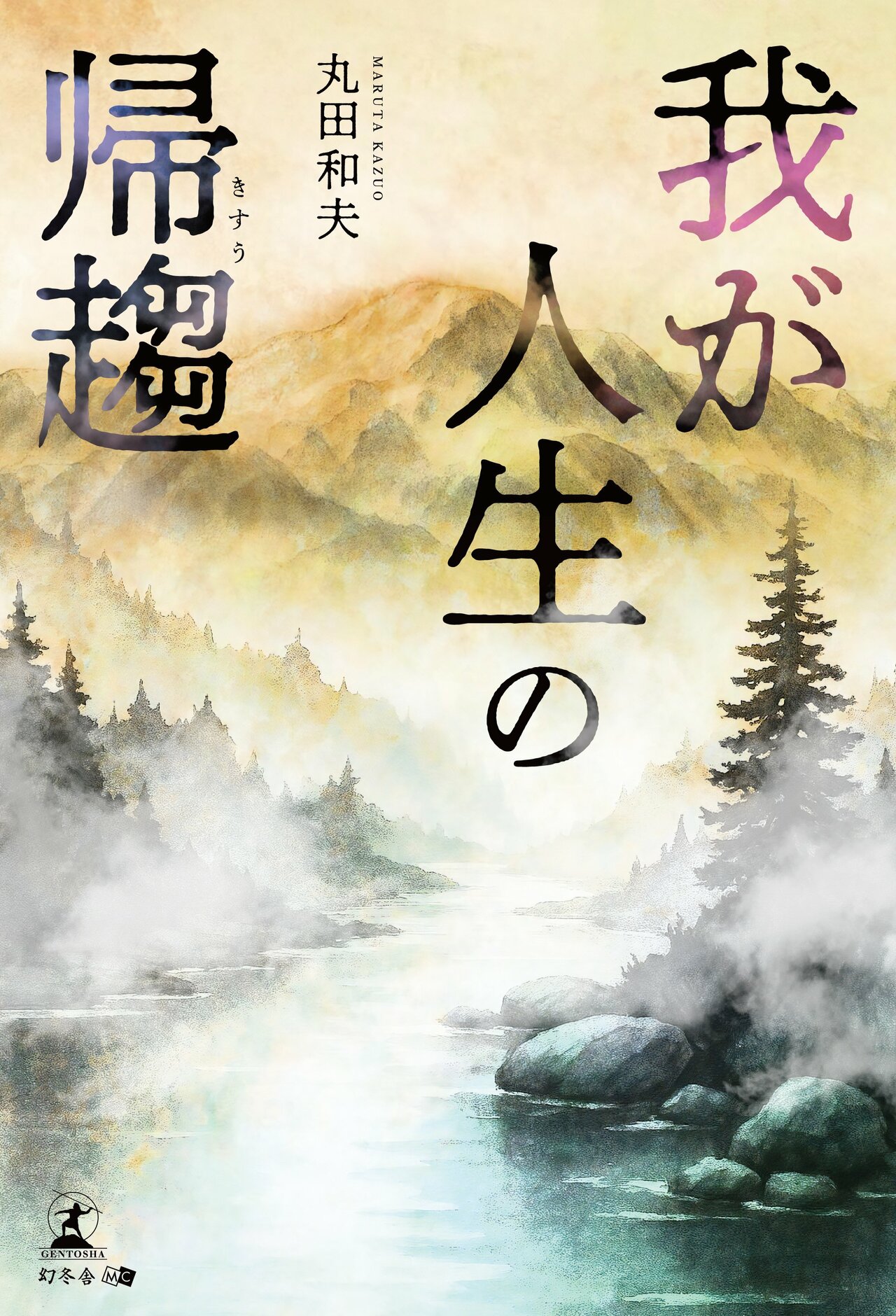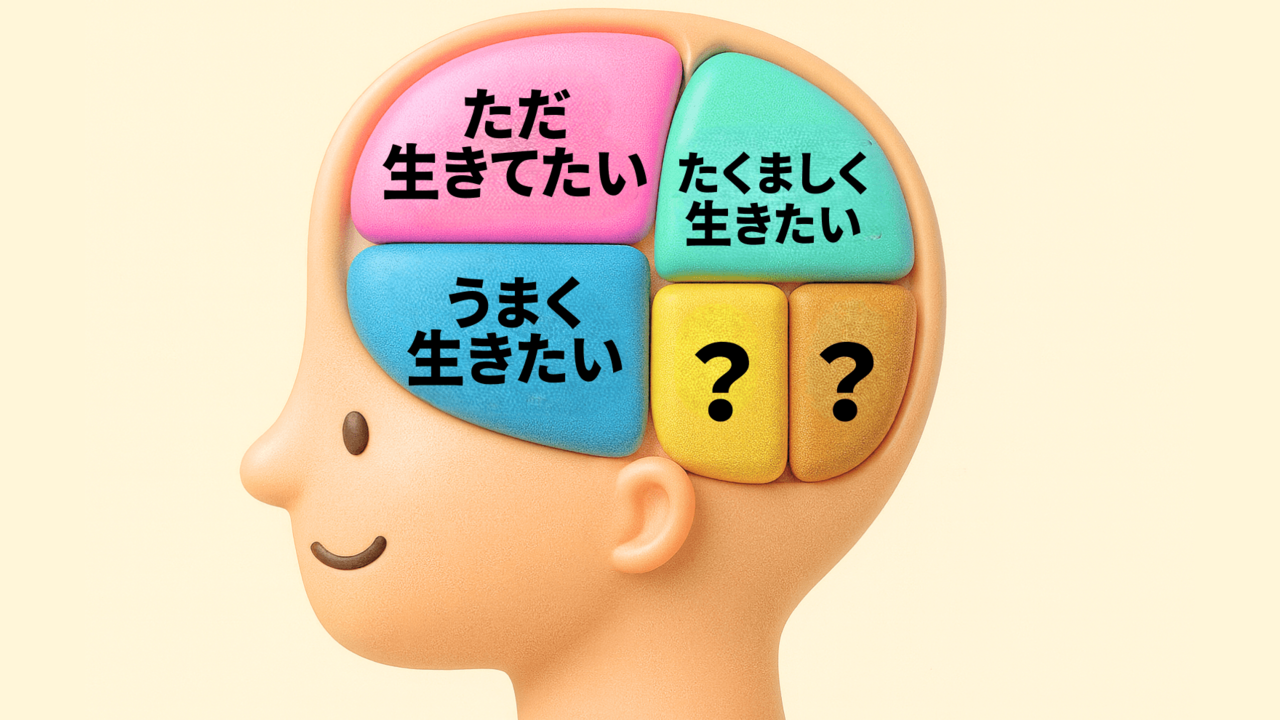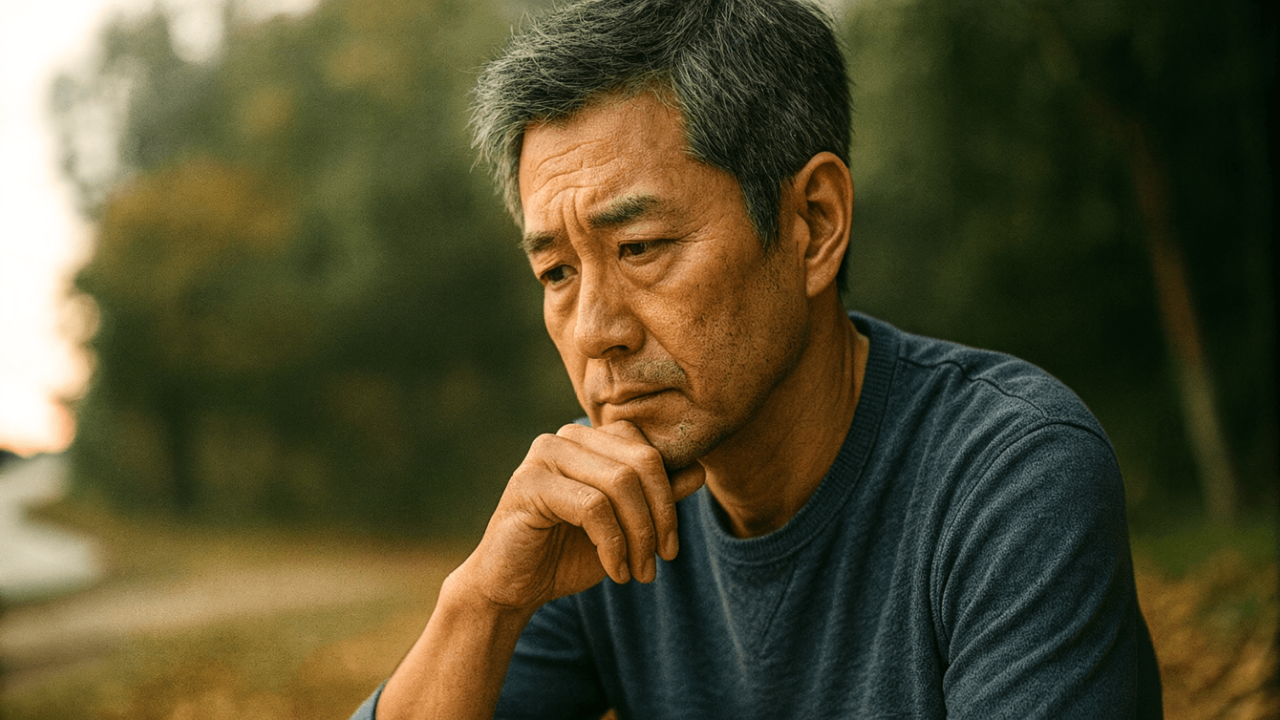「自分のためだけに生きるのではなく、人のためにも生きよ」
医療倫理の下に、臨床や教育の場で医療実践に明け暮れ、自己研鑽する道を歩んできた。
当時はまだリハビリテーション医療の草創期であった(23)。
リハビリテーション専門医も少なく、リハビリテーション医療の主力が理学療法士に託されることが多かった。
他科の回診参加、
担当医とのマネジメントなど、
リハビリテーション専門医の代役を果たさなければならないことが多々あった。
リハビリテーション医療は患者さんの機能的な回復だけではない。
人生にまで関わる仕事なのだ。
人間回復の医道であるとも言える。
特に脳、神経系や筋肉系の慢性進行性疾患や機能障害のある患者さんのリハビリテーションでは、若い時から生と死の問題やQOL(quality of life)に関する哲学的医学課題の解決が求められた(24)。
それだけに、人間的資質、医学的知識や理学療法の技術などの研鑽、そして人間学や自己の探究までも必要とされ、役職的な責任も持たされた。
万日(まんにち)を過ぎたあたりから、自己の内面的成長と社会的現実との行き詰まりを感じるようになり、嗜好が嗜癖に転化する恐れを感じたのである。
人間学に基づいた自己の探求は、まさにそこから始まったと言える。
それを後押ししてくれた次の二つの出来事があった。
一つ目は、『歎異抄』(25)との出遇いだ。
被教育者に学ぶ極みなきひかりといのちを被る道から自己を原(たず)ねる縁をもらった。
(20) 中村 元・他訳註 『浄土三部経』 (上)・(下) 第二六刷改訳 岩波文庫 一九九〇
(21) 聖書協会共同訳 『聖書』 日本聖書協会 二〇一八
(22) ロナルド・ライト〔星川 淳訳〕 『暴走する文明 「進歩の罠」に落ちた人類のゆくえ』日本放送出版協会 二〇〇五
(23) 丸田和夫 「理学療法を論ずるのは易しいが、その要を伝えるのは難しい」 『理学療法ジャーナル』 四二巻八号 医学書院 二〇〇八
(24) 丸田和夫 「癒されぬ病に学ぶ理学療法の原点と本質」 『石川県理学療法学雑誌』 八巻 二〇〇八
(25) 暁烏 敏 『歎異抄講話』 講談社学術文庫 一九八一
【イチオシ記事】「私、初めてです。こんなに気持ちがいいって…」――彼の顔を見るのが恥ずかしい。顔が赤くなっているのが自分でも分かった
【注目記事】「奥さん、この二年あまりで三千万円近くになりますよ。こんなになるまで気がつかなかったんですか?」と警官に呆れられたが…