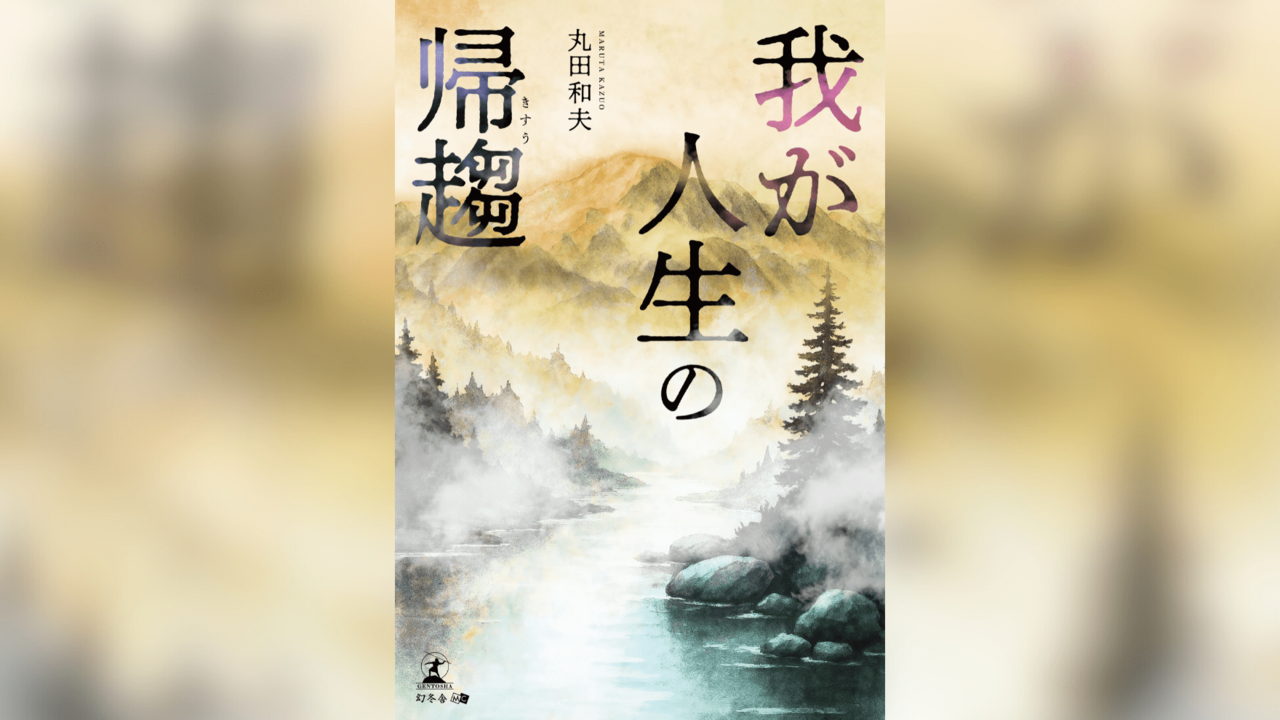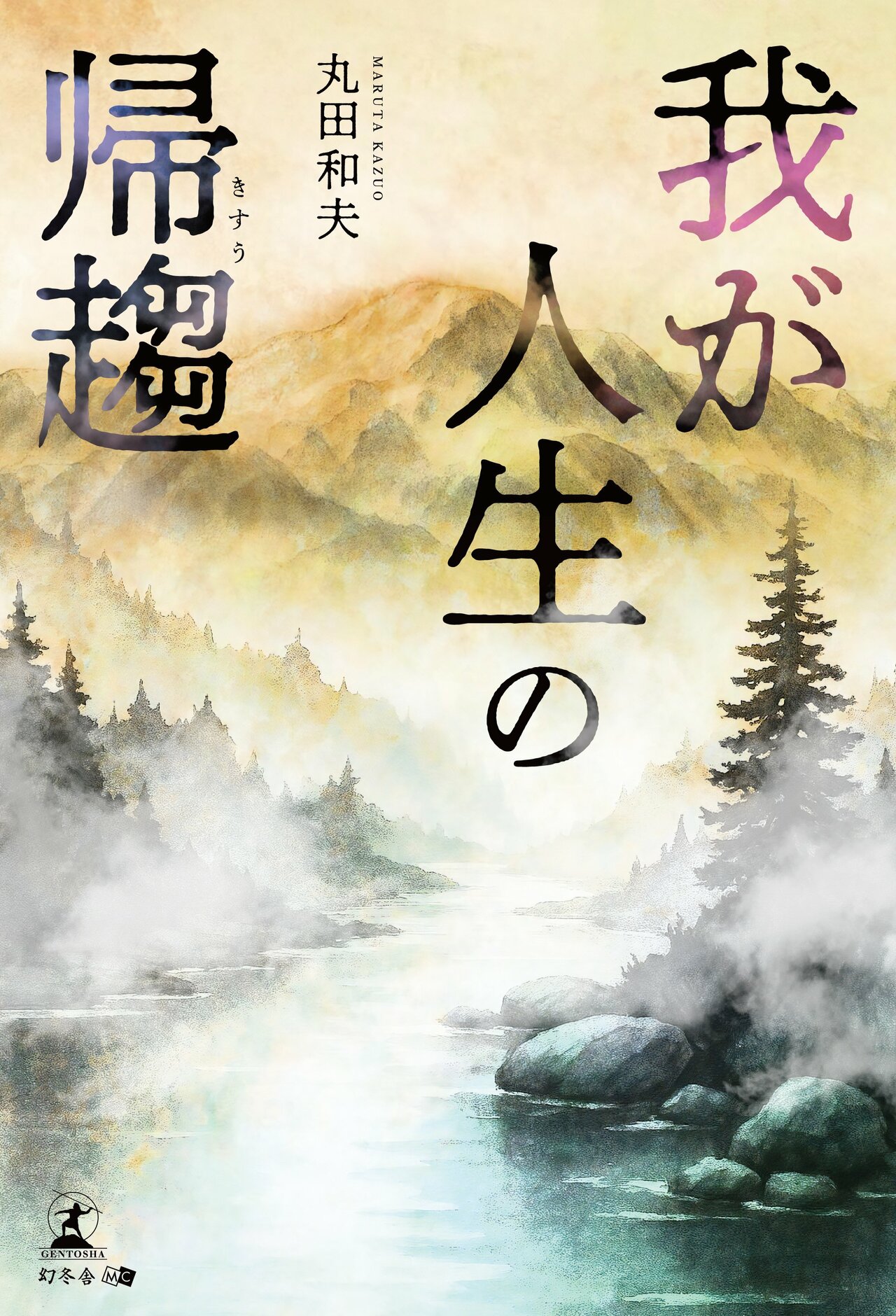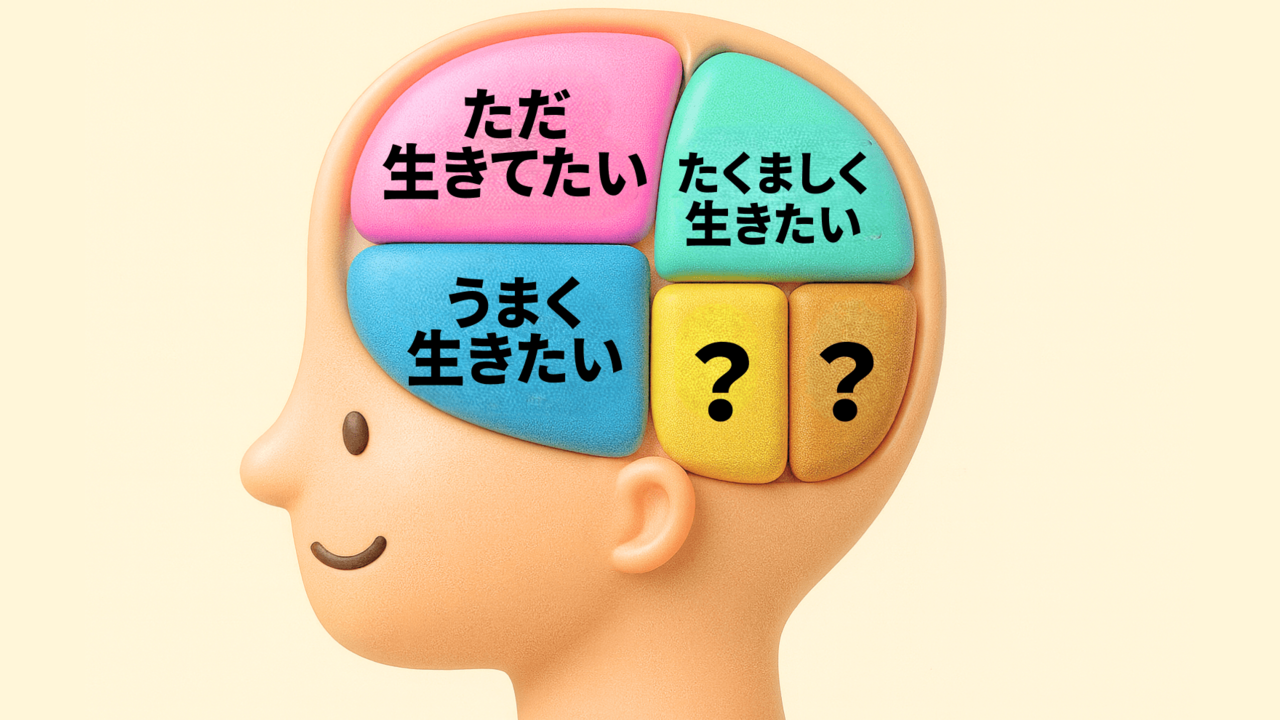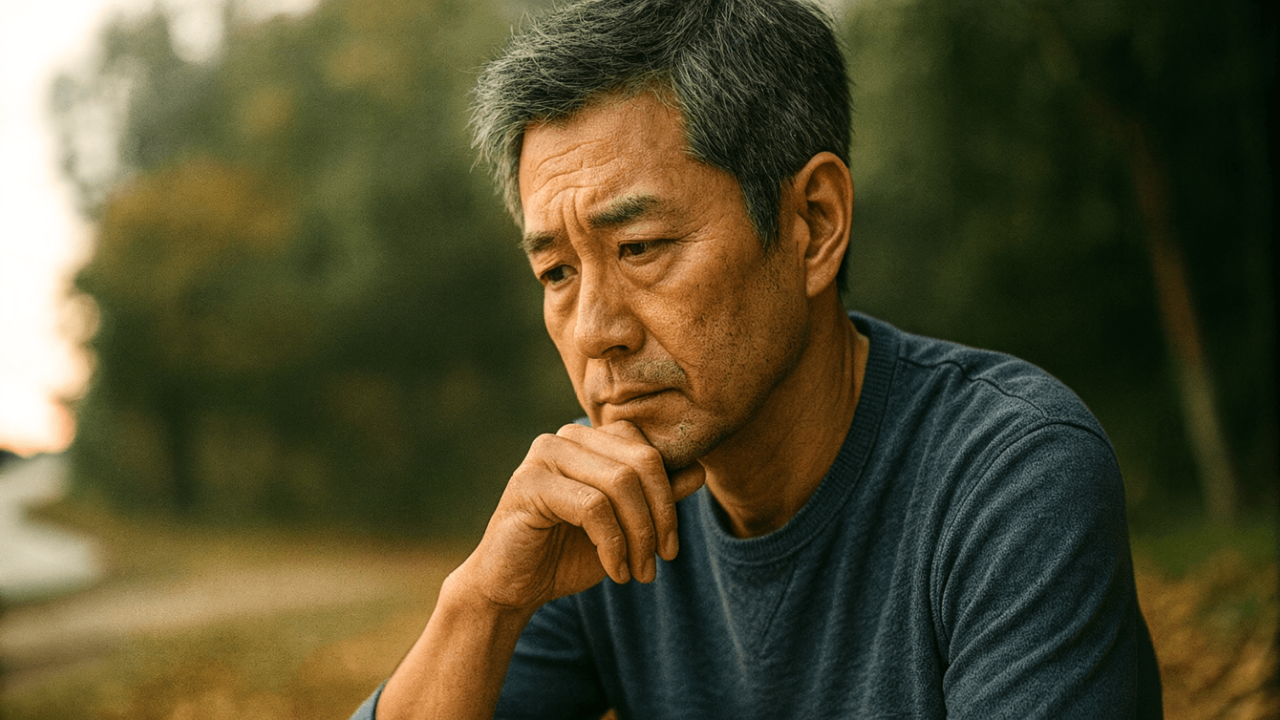【前回の記事を読む】真実に生きるとはどのようなことなのか? 真実に生きるとは、真実をよりどころとして生きること
執筆にあたって
いずれにしても、人智を超えた未知の世界の話ではないか。人間的なものの考え方ではとうてい理解しがたい。だからこそ、実践真宗学の学びを求めたのである。
このようにして、我が人生の前半期(first half)は近代の科学的合理性に基づいた科学的世界観を形成してきた。
後半期(second half)に入って、それが宗教的・仏教的世界観に転じた。
しかし、未だに科学的世界観と宗教的世界観が交錯していている。
そこで、己を深めるに至った出遇いとは、それは一つの観念にとらわれず、多種多様な宗教的思考、それにまつわる哲学や宗教との邂逅(かいこう)だった。
本書の内実は真実に生きる人生の歩みと、こころの遍歴の表白である。
ここで歩みのすべてを書き出すことはできないが、その一端に触れてみたい。
人生とは無常な物語のようなものだ!
誰でもこころがゆらぎ、乱れそうになる時がある。
哲学は専門的に学んだわけではない。むしろ人生観や世界観的な意味において、一生を貫くこころの大黒柱を築き上げる諸縁の一つとなったことは間違いない。
人間のこころの奥底には善のこころと悪のこころがない交ぜとなっている。それはシェイクスピア文学から出遇ったギリシャ・ローマ時代のキケロ、エピクテトス、マルクス・アウレリウスなどの三人の思想(1)から学んだことであった。その中でも特に、清沢満之(2)や夏目漱石(3)も読んだとされるエピクテトスの『人生談義』(4)には現代の若者の苦悩にも応えられる理念を感じた。
さらに、宗教的な世界観との実践的な最初の出遇いには、某宗教団体での挫折体験があった。教祖を崇拝して、言葉巧みな勧誘、多額のお布施や献金を要求するような真実の宗教にはあるまじき行為が平然と行われていたからである。
キリスト教では、学生時代に病院や施設での実習で出遇ったキリスト者の精神の偉大さに触れた(5-8)。また、京都や大阪での路上生活者の人たちへの夜回りに参加しながら聖書にも触れた(9)。「小さくされた者の側に立つ神……」(10)には、思点の転換が促された。そして、最も衝撃的であったのは、東日本大震災後(11)石巻の福祉避難所でのボランティアでハワイからやって来た青年(ボランティアのためにハワイの家を売り払って日本に来た臨床宗教師)との出遇いだった。そして今は、理髪店の店主がキリスト者であったことから、毎月一回、聖書等の学びを継続している(12)。
仏教では、北欧の福祉視察研修で出遇った曹洞宗の僧侶からの宗教多元主義の影響が大きい(13、14)。浄土真宗については、北陸地方が真宗王国と称されるほど浄土真宗篤信の土徳文化の地で、義父が浄土真宗本願寺派の門徒であったこと、そして最も劇的であったのが、わたしの人生において出遇った善き師の一人でもあり、常に「尽くして忘れよ」と言っておられた理学療法士の大先輩が、人工呼吸器を挿管した死の床で語った、言葉にもならない声、「マルタクン、タンニショウヲヨメ」であった。
一道に徹せず、節操がないと言われればそれまでのことだが、これも人生の武者修行のようなものかもしれない。大切なことは真実に生きることであり、もし皆さんが何かに頼りたくなった時は、必要に応じて頁をめくっていただければ幸いである。
あとは、捨てるも読むも読者のご判断にお任せする。