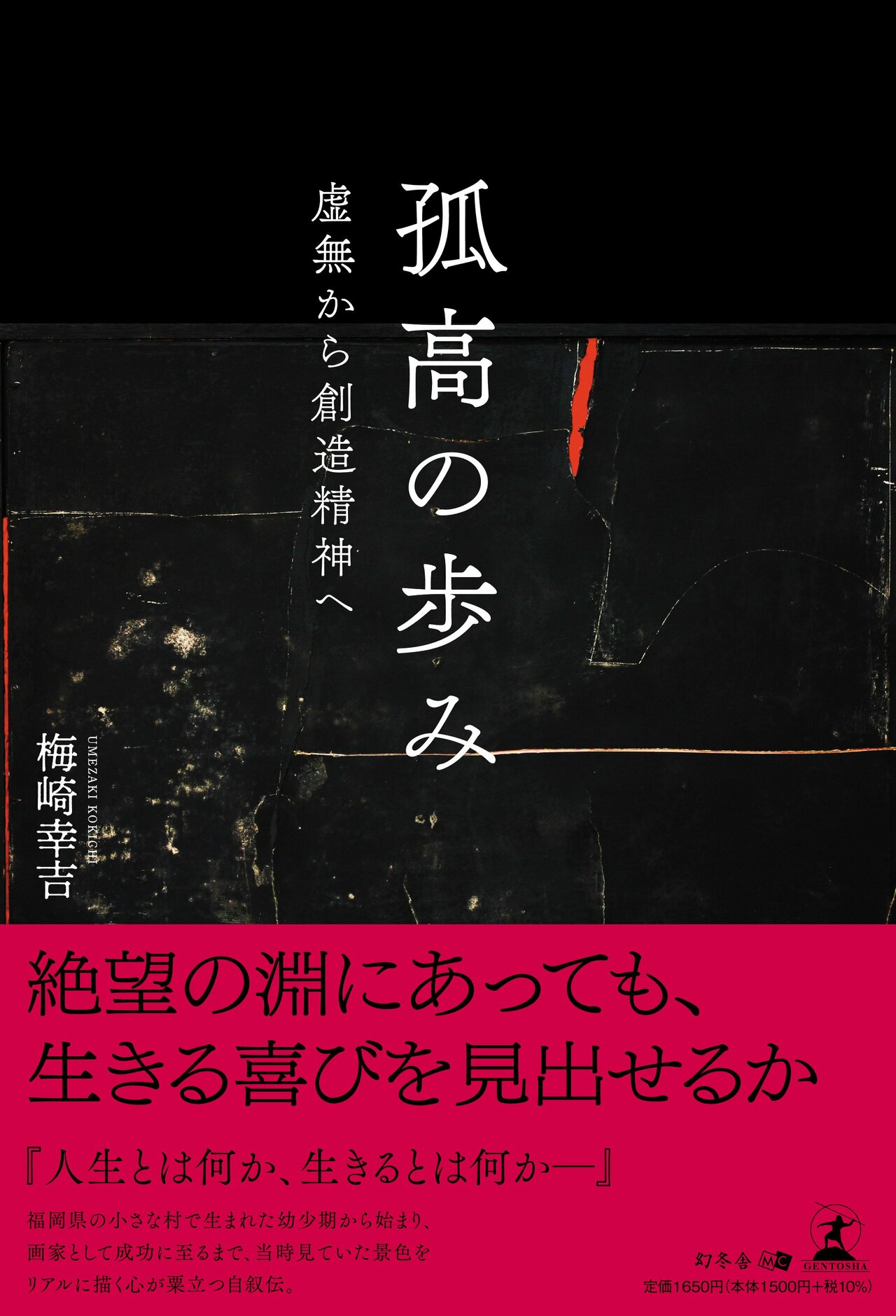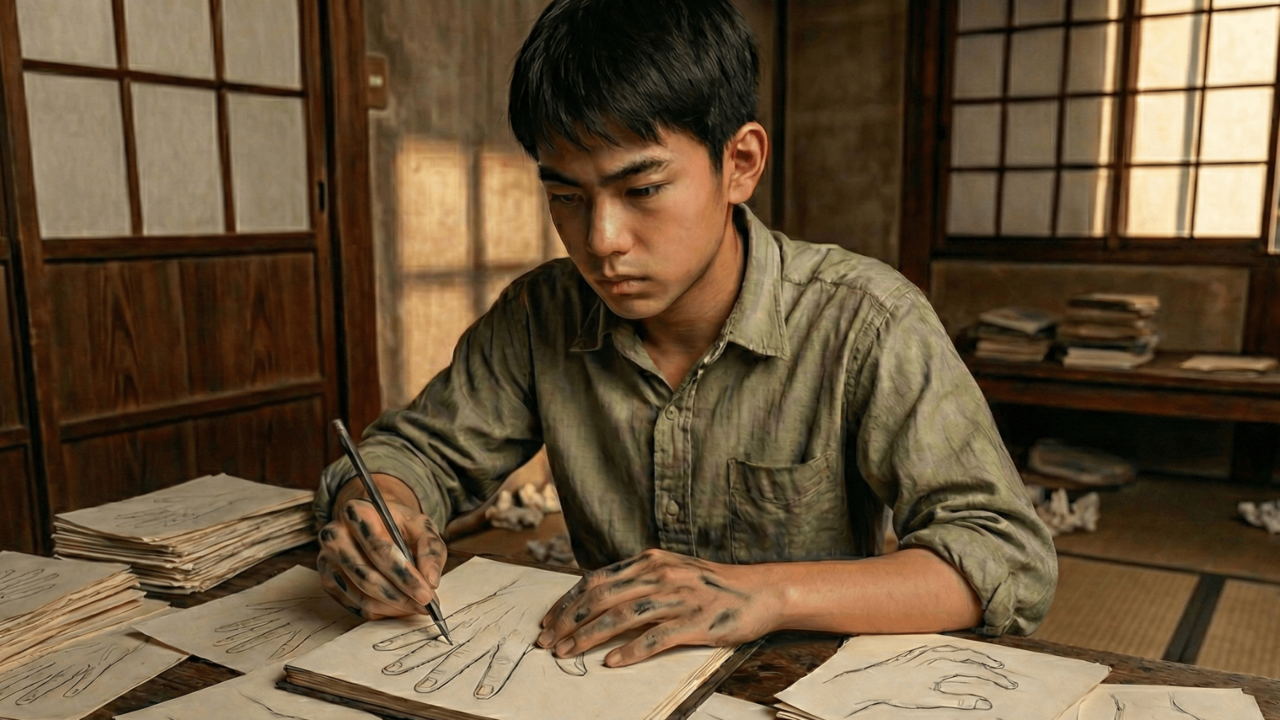私が近視であると分かって眼鏡をかけたのも東京に来てからである。すでに九州時代でも黒板の文字は見えなくて、何が書かれてあるか分からなかった。勉強が嫌いなのと、見えないのとが両方であった。
それと、私が学ぶことに抵抗したのは、モノの原理や法則を、記号や約束事として誰がどのような基準で決めたのか? という疑問が常にあったためでもある。
例えば、記号はもとより、円周率などの計算を何もない状態でどうやって考え付いたのか、なぜ円は三百六十度なのか。
直角が九十度であるのは、単に円に縦横に真っ直ぐに線を引き四で分割したものである。もしこれが四百度だとすれば直角は百度である。合理的に考えれば四百度のほうが簡単ではないか?
それに私の素朴な疑問である足し算、引き算にしても、物を同質の状況環境のものと設定し、全てが同じであるという前提が中々理解できなかった。
本来、合理的なものの考え方をする自分ではあったが、物事の基本の前提となる原理の説明がなされない限り、私の頭は動こうとしなかったのである。掛け算でも私はつまずいた。特に、この問題の根源的な問いは様々な形で後々まで続くのである。
プラスとプラスを掛けるとプラスになる。だが、マイナスにマイナスを掛けるとプラスになる。これは私には何か手品のように思われた。
これは、言葉で言えばこういうことだそうである。肯定を肯定すれば肯定となり、肯定を否定すると否定になり、否定を否定すると肯定となる。
しかし、私の頭はそうは考えなかった。否定を否定すれば、さらなる否定であって、どういうからくりでそれが肯定になるのか、と。
これは鶏が先か、卵が先かという問題と似ている。私の思考はこの問題を引きずったまま中学を卒業することになるが、単に知識として鵜呑みにすることができない問いであった。当然、他の学業にも興味は持てなかった。
私は渋谷区立外苑中学校に入った。家から山手線沿いに歩いて四十分ほどである。帰りはよく明治神宮の中を通った。クラスは六組まであって、一クラスに五十人くらいいた。各小学校から来たそれぞれの番長のような連中が勢力争いのようなことをしていた。
👉『孤高の歩み—虚無から創造精神へ— 』連載記事一覧はこちら
【イチオシ記事】二階へ上がるとすぐに男女の喘ぎ声が聞こえてきた。「このフロアが性交室となっています。」目のやり場に困りながら、男の後について歩くと…
【注目記事】8年前、娘が自死した。私の再婚相手が原因だった。娘の心は壊れていって、最終的にマンションの踊り場から飛び降りた。