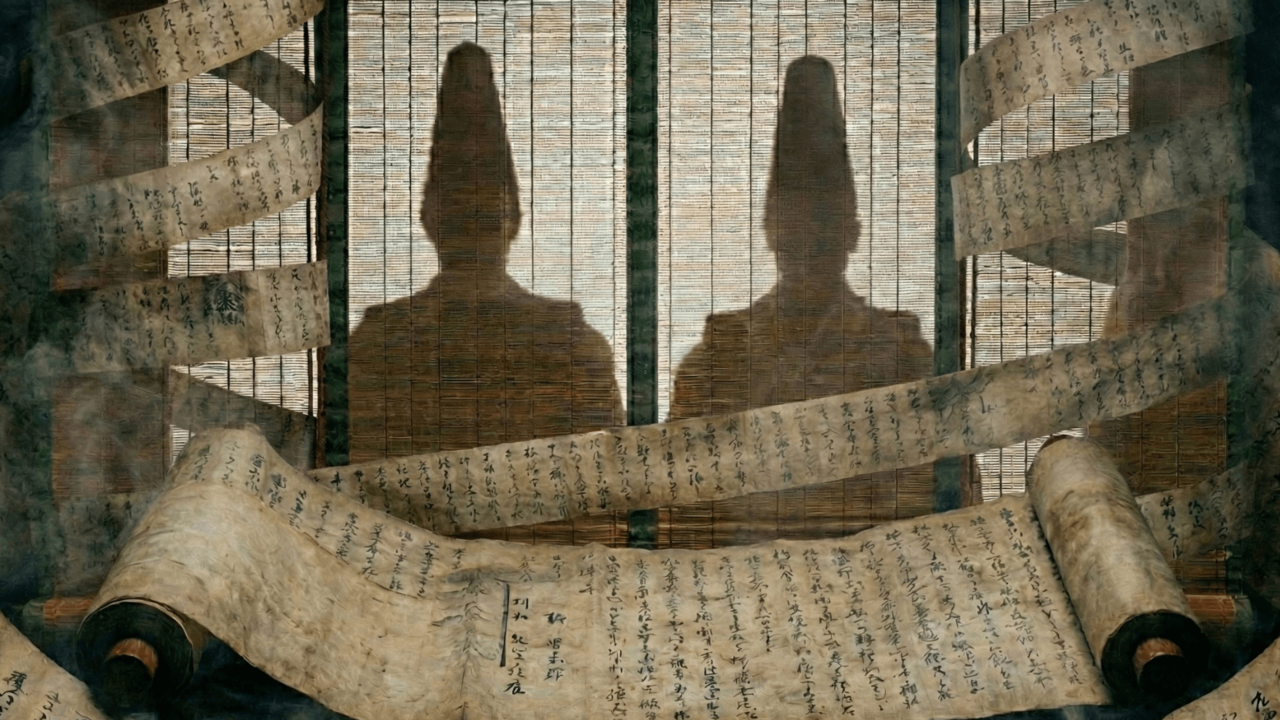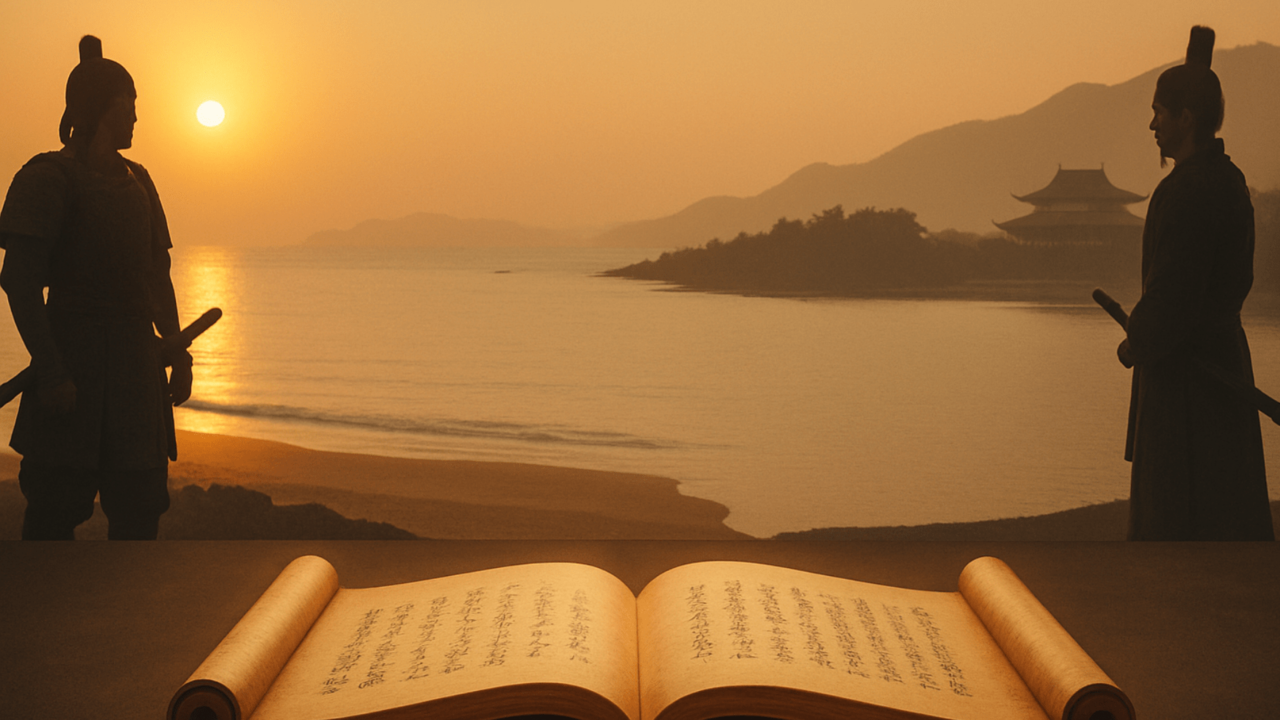さらに気づくことは、「応神天皇」以降皇居を河内や難波に、御陵も河内に造られる例が多く見られる。通称「河内王朝」と言われるものである。
以上の四つの注目点を、皇統を「接ぎ木」した痕跡と考えると、二つの系統に分けることができる(表2)。日向出身で「神武天皇」から一七代続く数値情報が多い系統と、近江出身の「成務天皇」から「武烈天皇」に至る河内に勢力を持つ系統である。これらの二系統が敦賀(福井県)出身の継体王朝に引き継がれる。
上の推論は『日本書紀』のデータを用いて論じたが、『古事記』のデータにも注目するべきものがある。それは「成務天皇」から「允恭天皇」(一九代)までの没年と享年が明記された数値情報の塊が見られる(表1)。七代も続くことは他の箇所にはない。またこの七代が前述した『日本書紀』の「接ぎ木」の痕跡部分と重複している。
『古事記』の数値情報のうち、「仲哀天皇」の享年と「允恭天皇」の没年のみが『日本書紀』のものと一致しているにすぎない。このことは「成務天皇」から「反正天皇」(一八代)までの数値情報が、別人のものと並記されていた可能性を思わせる。
つまり日向出自の「神武天皇」系列と近江出自の「成務天皇」系列のそれぞれに属す二人の人物のデータ合成により、一連の皇統が再構成されたのではないかという問題提起である(表2)。
二系統に属する人物達は、当然没年齢は異なっている。系統を一本に再編するためには、時間軸の調整が必要となるだろう。前述した「応神天皇」の即位が遅れた(二倍年を考慮すると三五才)理由も、この時間軸を操作することによる結果かもしれない。
【イチオシ記事】二階へ上がるとすぐに男女の喘ぎ声が聞こえてきた。「このフロアが性交室となっています。」目のやり場に困りながら、男の後について歩くと…
【注目記事】8年前、娘が自死した。私の再婚相手が原因だった。娘の心は壊れていって、最終的にマンションの踊り場から飛び降りた。