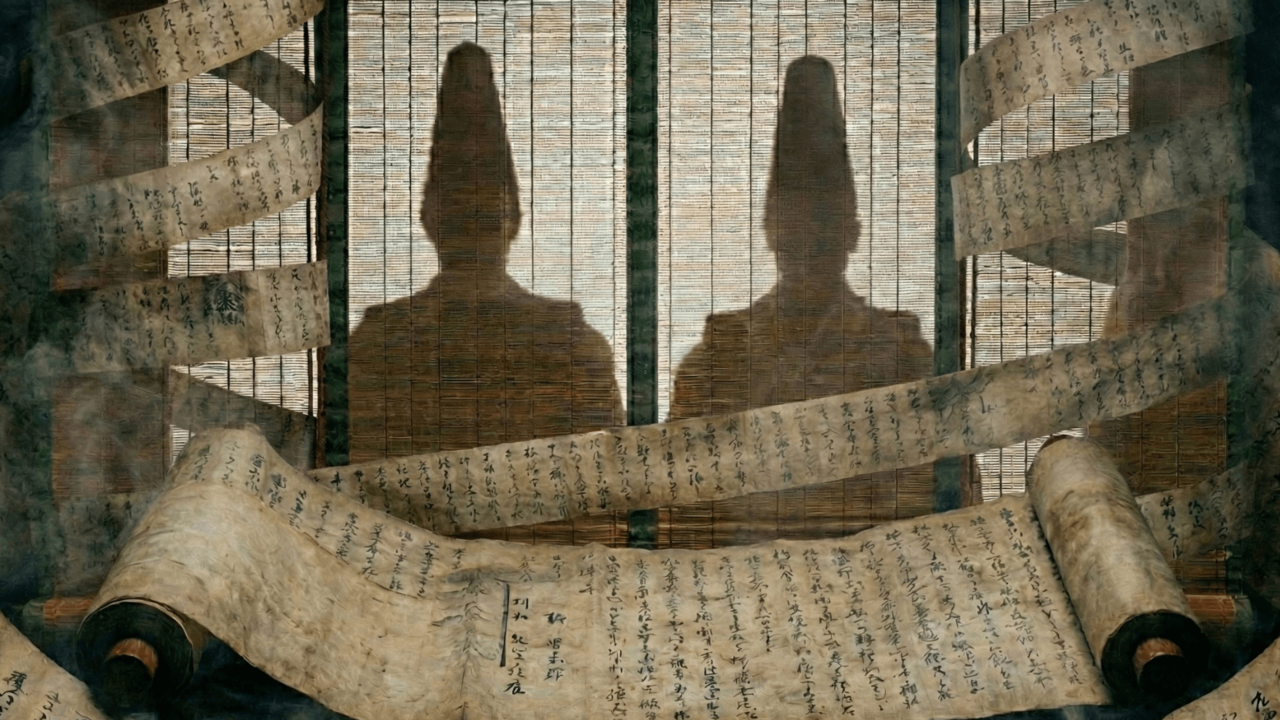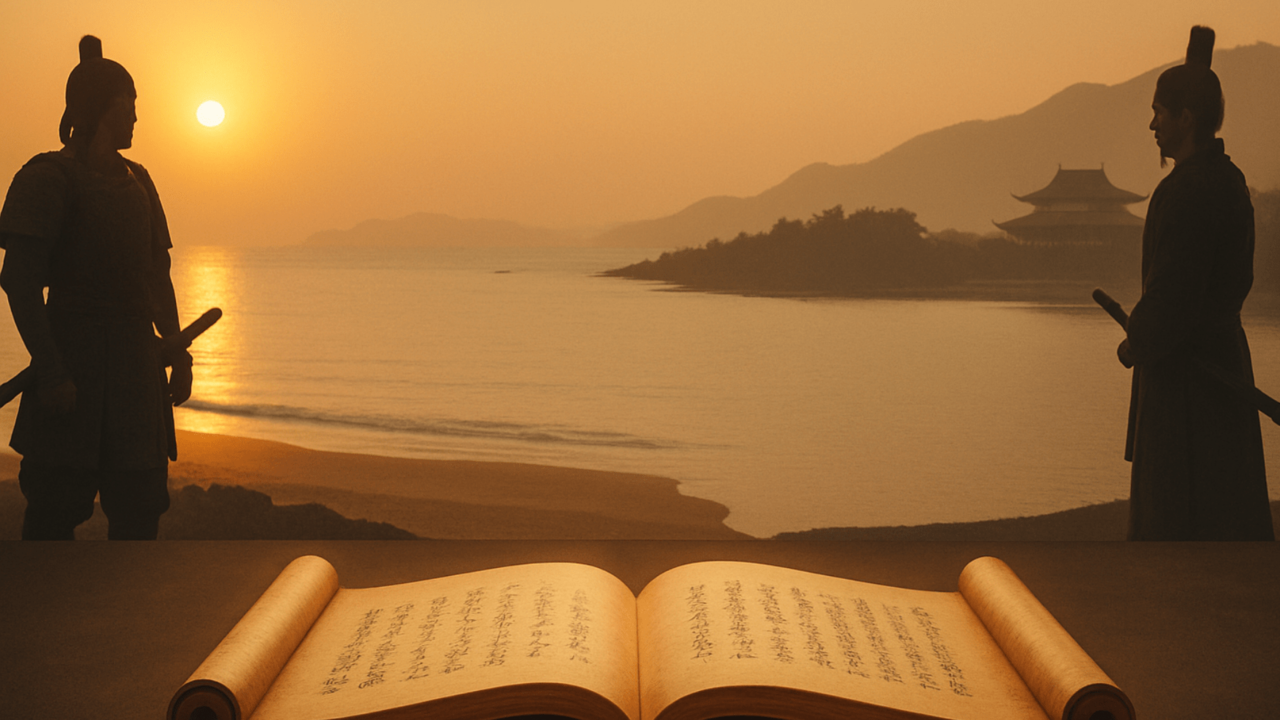①「成務天皇(一三代)記」には「近淡海の志賀の高穴穂宮に座す」とある。建前論で言えば、「宮」とは天皇が住まう処、皇居であり、そこで政を執り行う。ただ実際には天皇が住めばどんな建物でも「宮」と名付けられる。つまり「成務天皇」が近江(滋賀県)で政治を行ったというより、そこに住んでいた、出自が近江であることを示していると考えた方が良い。
②「仲哀天皇」(一四代)は悲劇の人である。角鹿(つぬが)(敦賀、福井)、穴門(山口県)、筑紫(福岡県)を転々と移動し、不可解な死を遂げた。御陵は河内(大阪府)にあり、大和以外の地に造られた初めての例である。
③「神功皇后」は「仲哀天皇」の死後、六九年間(二倍年で考えると三五年)の長きにわたり摂政の地位にあった。『古事記』では「仲哀天皇記」の大部分が「神功皇后」の記述で占められ、『日本書紀』では別項として取り上げられている。
なぜ女性(皇后)摂政の時期が必要だったのか。今までの話題で言及しているが、邪馬台国に女王が君臨していたからだろう。『記紀』編纂時に集められた情報の中には、九州における史実や伝承も多く存在したと考えられる。それらを『記紀』に取り込む為に、六九年の長きにわたる女性(皇后)指導者が必要だったのではないだろうか。
④「応神天皇」(一五代)は「神功皇后」の摂政期間が長かったので、即位年齢は六九才(二倍年で修正すれば三五才)となるが、これは不可解なことと思われる。一般的な考え方からすれば、幼君が成長すれば速やかに政権を還すものだ。「応神天皇」は成人しても「神功皇后」が亡くなる壮年(三五才)まで天皇位に就けなかった。なぜだろう。この理由に関する一解釈は後述する。