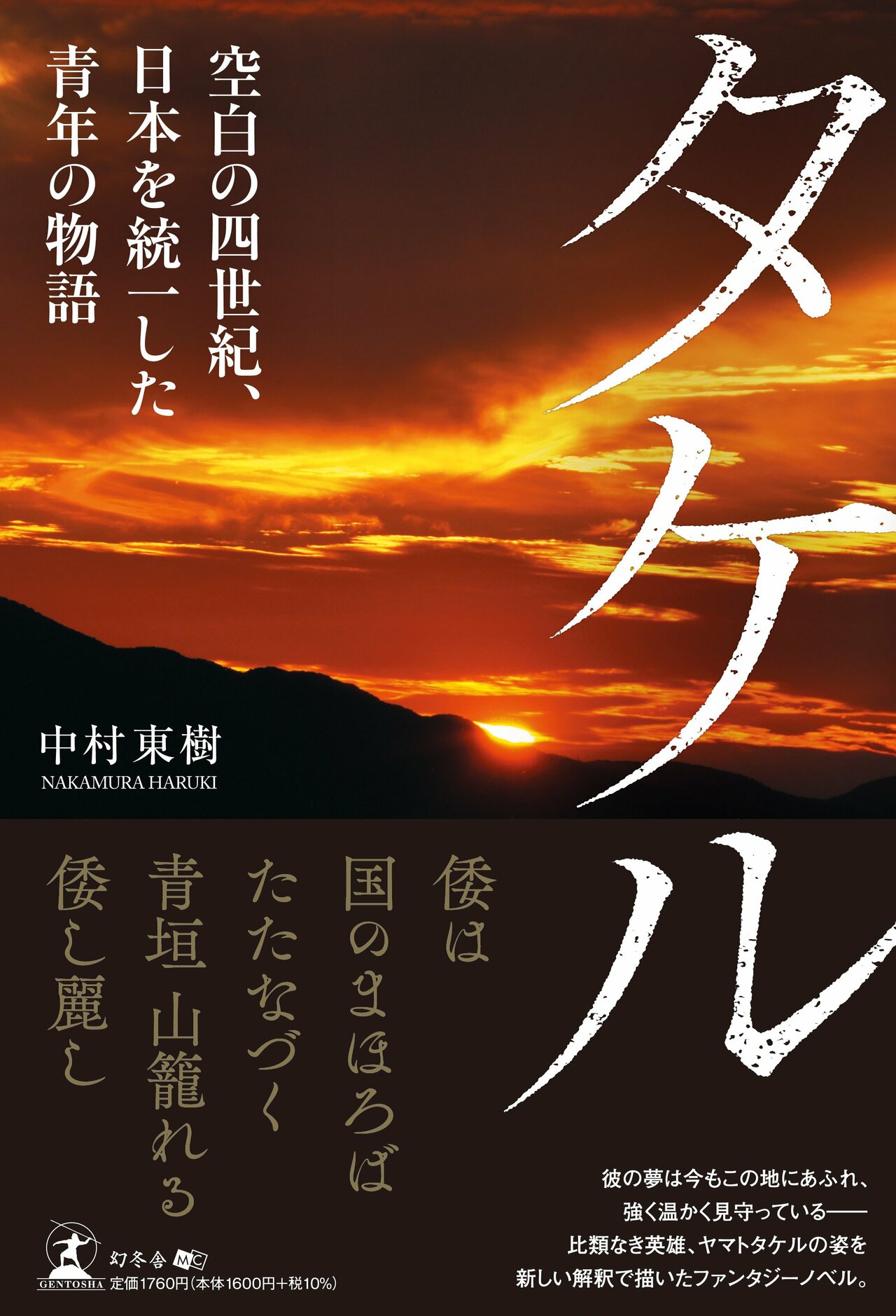「もう大丈夫だとは思うが、住まいまで送っていこう」
そういうと小碓は娘たちを促して山道を下りて行った。小碓の仲間の子供たちが、手際良く小碓が仕留めた猪を木に結びつけ、四人で運んでいた。四人がかりでないと運べないくらい大きな猪で、かなりの量の猪肉が手に入ったことになる。
フタジ以外の娘たちは大変だった。小碓は、大王の後継者の資格を有する皇子であり、武勇に優れているだけでなく、類まれな美男であった。以前から宮廷に出入りする娘たちの一番の憧れの人であった。その皇子と、こんなに近くで一緒に山道を歩いていることが信じられなかった。
この機を逃してなるものかと言わんばかりに、娘たちはいろいろと話しかけるのだったが、小碓も嫌な顔もせずに応じていた。フタジは黙ったままみんなから少し離れてついて行った。娘たちが驚いたのは、フタジと小碓はすでに昔からよく知る仲だったということだ。大王の一族なのだからお互いを知っていても何ら不思議なことではないのだが、これまでフタジが小碓の話をしたことは一度もなかったのである。
フタジたちの住まいに近づいてそろそろ別れの時になったころである。小碓が突然
「フタジ、手を見せてみろ」
そう言ってフタジに近づき、いきなり両手をつかんだ。手を引っ込める時間もなかった。蒼く染まった両手を見ながら
「やはりな。ありがとう」
小碓は手を離し、自分の貫頭衣の胸の辺りをつまみながらお礼を言った。そして自分の居宅に向かってさっさと帰って行った。
周りの皆はあっけにとられていた。もうすでに陽が落ちて、木陰が長くフタジの顔を覆っていたため、その顔が真っ赤に紅潮していたことに誰も気付かなかった。