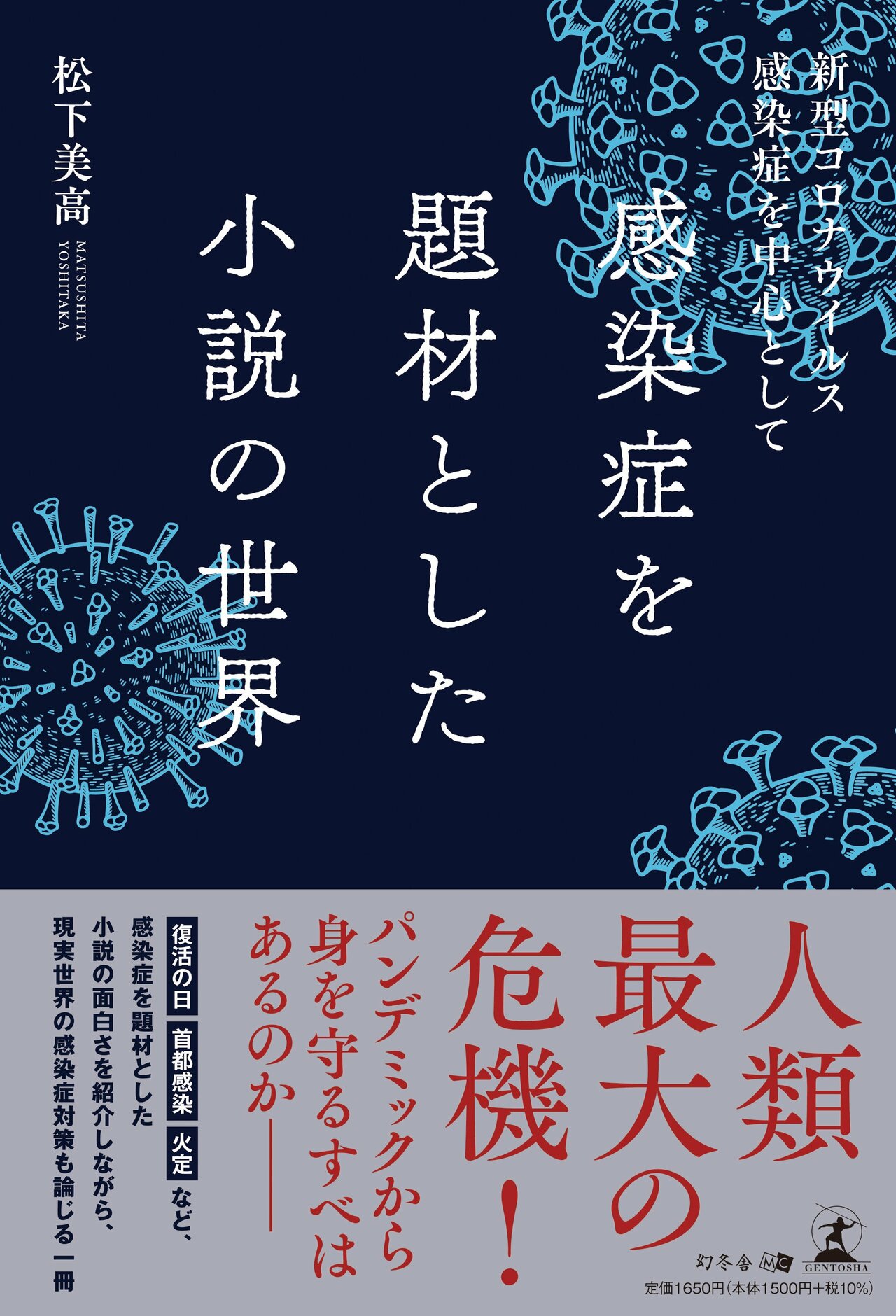『火定』/澤田瞳子/PHP文芸文庫(2020年発行)
(2017年 PHP研究所から単行本として発行、2020年文庫化される)
【作品概要】
奈良時代に起こった天然痘の大災禍状況を鮮明に描いた作品である。京内の病人の収容・治療を行う施薬院で働く下級官僚の蜂田名代(なしろ)が地獄のような状況に直面し、人間としてどう生きるべきか苦悩する。天平2年の奈良を舞台にした歴史小説であるが、この時代の人々の行動パターンが、現代のコロナ禍で生きる私たちのそれと類似していることが分かる。
㊟タイトル「火定」について
何百という天然痘患者が全身を水疱に覆い尽くされて高熱で死んでいく中で 主人公・名代が思いを語るくだりが、本書284頁にある。「世の僧侶たちは御仏の世に近かんとして燃え盛る炎に身を投じるという……自分たちもこの世の業火によって生きながら火定入滅(かじょうにゅうめつ)を遂げようとしているのではないか」。この火定がタイトルになっている。
【あらすじ】
奈良時代の735年から737年にかけて奈良の都に天然痘が大流行し、人口8万人の3割近くが死亡するという歴史的な大事件を題材とした小説である。
下級役人の蜂田名代は、庶民の医療を行う施薬院の運営にたずさわっていた。施薬院の先の見えない仕事で上司にこき使われ嫌気がさしていた。
ある日、この施薬院に一人の病人がはこばれてきた。その顔一面にえんどう豆ほどの疱疹ができ膿を含んで腫れあがっていた。裳瘡(もかさ)(天然痘)の前兆であった。
施薬院を支える唯一の医者であり、疱瘡の治療法が記されている新羅の書物を発見した綱手医師、施薬院の庶務を一手に担う有能な相談役の広道、施薬院の財務一切を預かる慧相尼(けいそうに)、人出不足の施薬院の応援に派遣されてきた医生あがりの助っ人・真公(まきみ)、20人ほどの孤児の世話をする僧侶の隆英、元侍医であり冤罪で刑を受けるが恩赦で釈放された諸男(もろお)、天然痘の蔓延する中で「常世常虫(とこよのとこむし)」という神をでっちあげ疫病退散にききめあらたかな禁厭札(まじないふだ)を売り出し人心を惑わす詐欺師の宇須などの人々が登場し、恐ろしい疫病裳瘡をめぐって壮絶な人間模様が展開されていく。
【感想】
天然痘は1980年WHOの根絶宣言によりその恐怖は完全に過去のものとなった。本書を読み終えて、天然痘の猛威に人間がいかに翻弄されてきたかその歴史がよく理解できた。
感染症によるパンデミックの極限状態にさらされた時人間は、闇の世界を惨酷なまで白日の下にさらけ出す。と同時に、人間として根源的な生き方が顕在化してくる。施薬院を抜け出したいと考えていた名代が、惨酷な現実を体験する中で成長をしていく姿に感動を覚えた。本書の最後の頁(430頁)に記されている言葉がその成長の証を見事に伝えている。
試し読み連載は今回で最終回です。ご愛読ありがとうございました。
【イチオシ記事】「大声を張り上げたって誰も来ない」両手を捕まれ、無理やり触らせられ…。ことが終わると、涙を流しながら夢中で手を洗い続けた