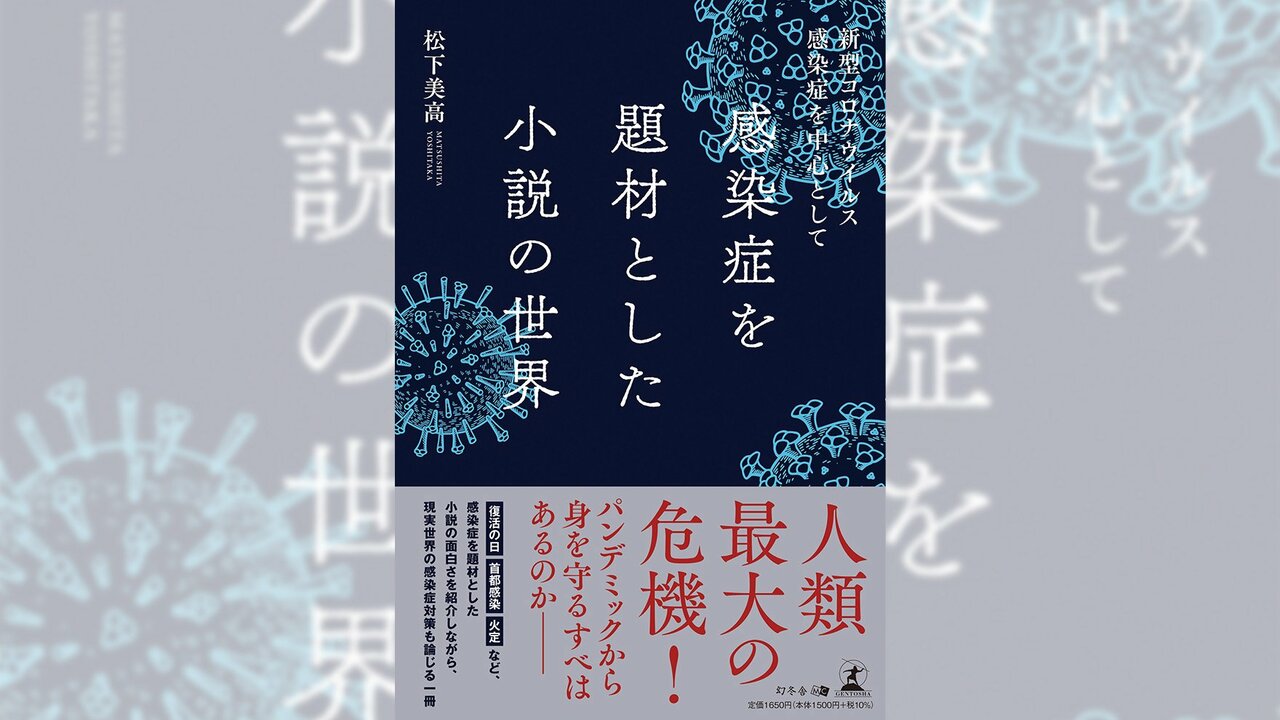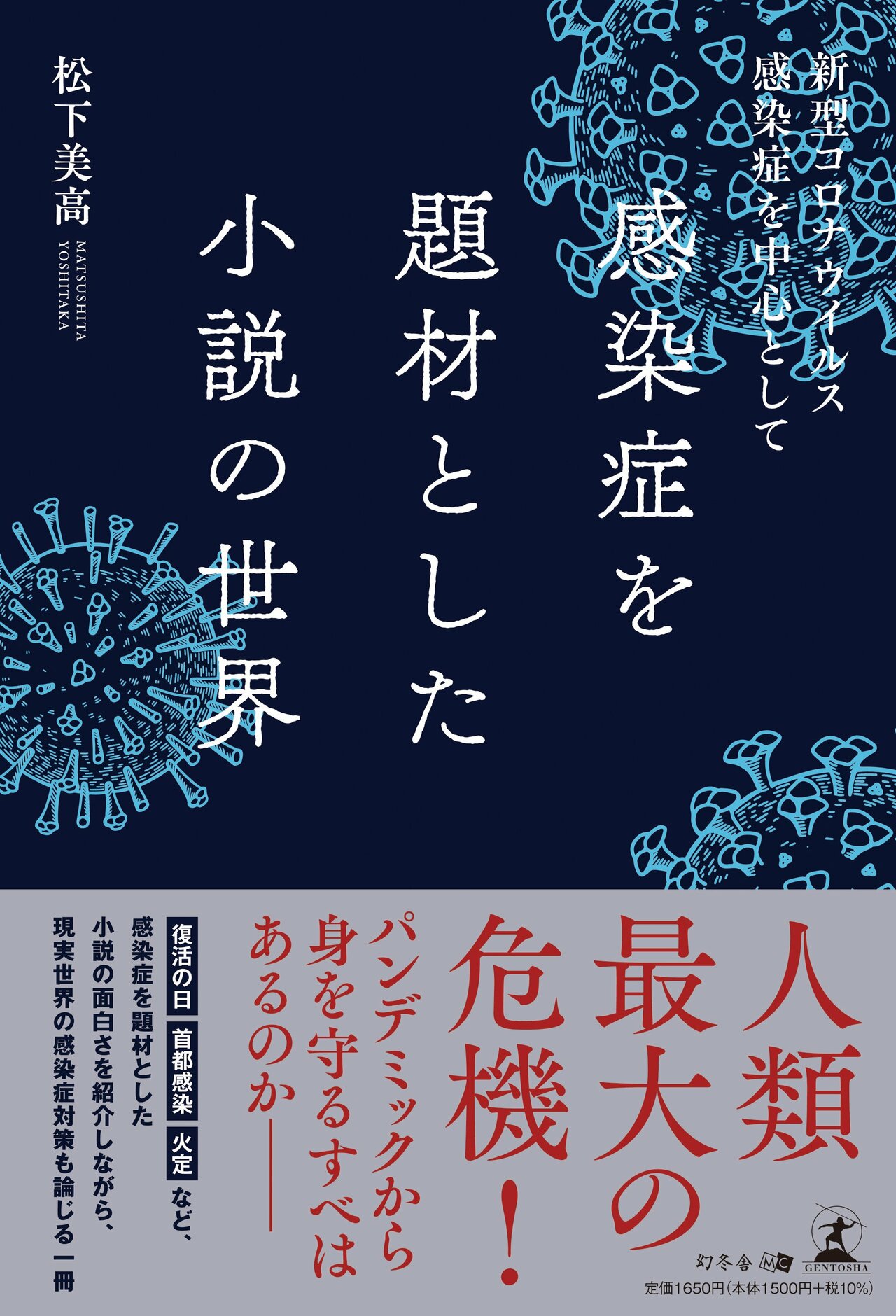【前回の記事を読む】死亡者約7000人。はじまりは高知県の山村に住んでいた3世帯5人の住民と飼っていた犬、猫、家禽のすべてが死んでいたことだった
Ⅲ 「感染小説」、その概要とあらすじ、私的感想
『臆病な都市』/砂川文次/講談社(2020年7月発行)
【作品概要】
首都庁の職員Kは、いくつかの都市でケリという鳥が媒体となる感染症のうわさが広がっているとの報告を受ける。対策の一環として感染の有無を証明するワッペン運動を推進する案が決定された。
【あらすじ】
主人公のKは、首都庁の市町村課に所属する職員である。たまたま首都圏のいくつかの自治体である種の鳥の不審死が次々と起こっているとの報告を受ける。未確認の感染症の疑いがもたれているがその正体は明らかにならず、感染症が存在しているという噂だけが独り歩きしていた。感染症の重篤化を恐れる報道がなされるなど騒動は加熱していった。
新型感染症対策検討委員会で、感染症の対策として健康診断のような何らかの検査を実施し検査を受けた人たちはワッペンをつける案が決定した。鳥による人体への感染などありえないと信じているKは、内心ワッペンの効果など期待していなかった。しかし、Kは行政組織の不条理な倫理に悩みながらもこの対策を推し進めていった。
【感想】
作者は、「この組織において規定される優秀な職員とは、ある理論、学説に通暁しているとか、仮説を立てて特定の問題に対して科学的な手法で解決の糸口を探る能力に優れているということではなく、自身の所属する組織と、相対する複数の組織とのパワーバランスを的確に把握し、波風を立てず、また前例から外れることなく、それでいて自己の組織が持つ機能を拡張させることのできる職員のことだ」と主人公に語らせている。
主人公Kはこの倫理にはじめから終わりまで忠実に従っている。実のないワッペン着用の感染症対策が次第に人権を奪う規範になっていく危険に陥ることになるのだが、現在のコロナ禍の世界にも同じような危険性を抱えている。恐ろしいことだ。