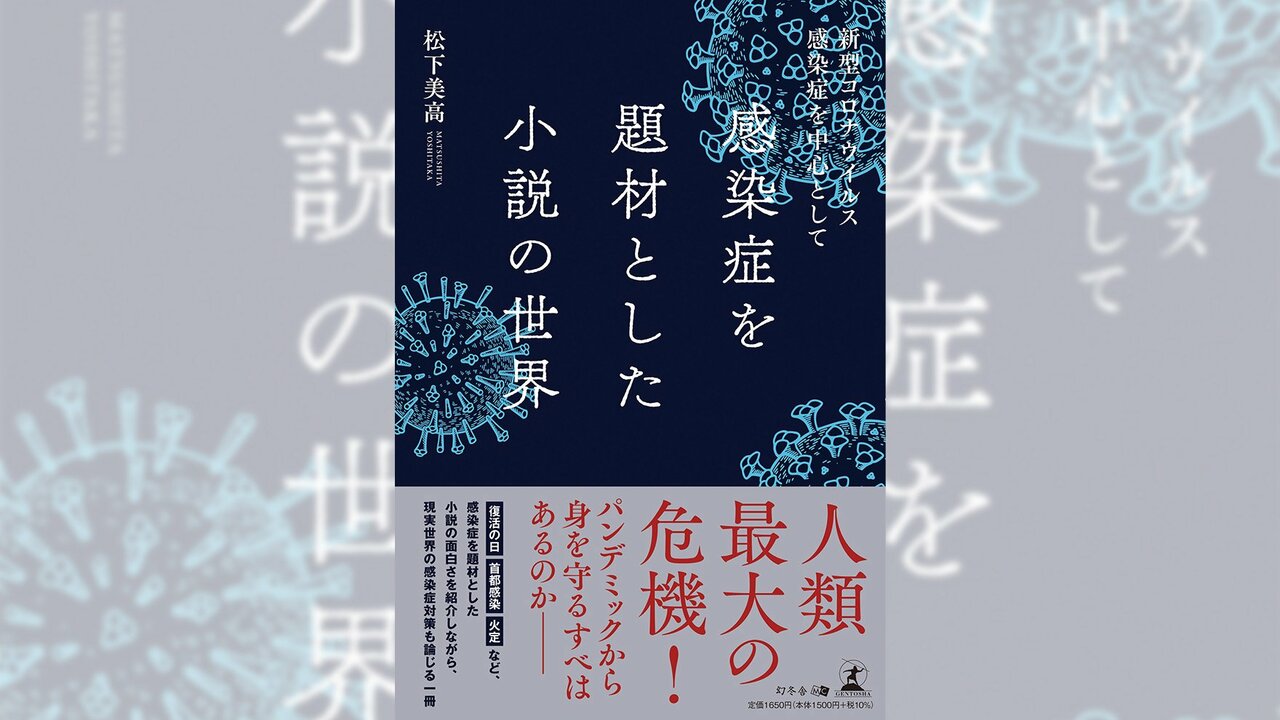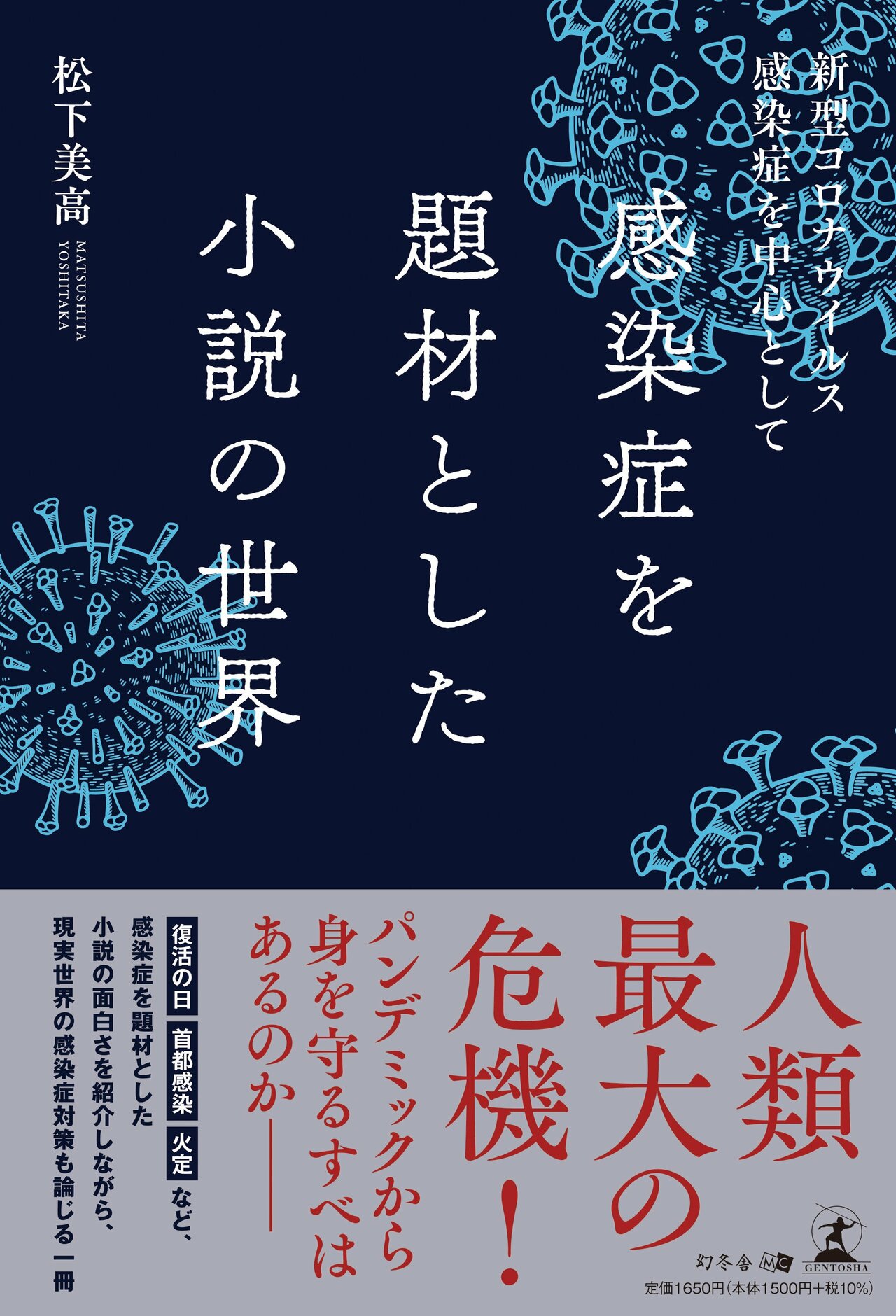【前回の記事を読む】【『サリエルの命題』あらすじ・感想】ワクチン接種の優先順位――現在のコロナ禍の中で人類が直面しているワクチン問題と重なる
Ⅲ 「感染小説」、その概要とあらすじ、私的感想
『夏の災厄』/篠田 節子/角川文庫(2015年2月発行)
(1998年6月に文春文庫より刊行された作品を加筆修正した)
【作品概要】
埼玉県のある小都市で、日本脳炎に似た未知のウイルスによる感染症が発生した。行政機関、開業医、保健センターの職員、保健婦のそれぞれの役割をどうするか、住民の感染者に対するいわれのない差別と偏見にどのように対処すべきかなどの問題が次々に起きた。このような問題に住民はどのように取り組み解決していったのか。その過程を多角的に描いた作品である。
【あらすじ】
埼玉県昭川市(架空)で、痙攣、頭痛、吐き気などの症例が現れる日本脳炎に似た疫病が多発した。保健センター職員の小西、夜間救急診療所の堂島看護師、旭診療所の鵜川医師たちが感染防止や原因究明に乗り出す。
特に、窪山、若菜台地区に患者が集中する事態に市民の間に不安が広がり住民間の対立、ワクチンの接種、感染を媒介すると疑われる蚊の駆除など様々な問題が次々と起こる。
小西職員は、ゴミ捨て場に繁殖するオカモノアライガイが新型日本脳炎ウイルスの発生源ではないかと疑っていた。小西は同窓の生物学者・三浦にオカモノアライガイがウイルスの宿主になる可能性があることを聞きこれが発生源であることを確信した。
鵜川医師はインドネシアのスパンティ社が開発したワクチンが新型脳炎に効果があることを知り、厚生省に使用の承認を求めて奔走する。
【感想】
小西職員、堂島看護師、鵜川医師たちの主な登場人物の活躍が、600頁にも及ぶ小説の中で生き生きと描かれている。物語もよどみなくスムーズに展開していく。人間とウイルスとの戦いには終わりがないといわれるが、本書では新しいウイルスに遭遇した時人間はいかに無力であるかをまざまざと見せつけられる。
しかし、強力な天敵にしぶとく立ち向かっていく人間の前向きな姿にも感動を覚える。日本医療小説大賞を受賞作品に値する興味深い小説である。
『破船』/吉村 昭/新潮文庫(1985年3月発行)
(1978年筑摩書房から単行本として発行され、1985年新潮社から文庫化された)
【作品概要】
主人公伊作の住んでいる貧しい村では、座礁した船の積み荷を奪い生活に充てるという風習があった。ある年、赤い着物を着た死体を積んだ船が村に漂着したことから、伊作たち島民にとってとんでもない悲劇が降りかかる。
【あらすじ】
主人公・伊作の住んでいる貧しい村では海の荒れた夜、夜通し塩焼きが行われる。その明かりに引き寄せられて岩礁に乗り上げ難破した船から積み荷を奪うという風習があった。村人たちに幸福をもたらす恵みの船であった。しかし、死をもたらす災厄の船でもあった。
ある年、赤い着物を着た死体を積んだ船が村に漂着した。恐ろしい疫病を患い船で放逐された人たちであった。この赤い着物から感染がはじまり村は厄災に見舞われる。
【感想】
記録文学の巨匠・吉村 昭が、江戸時代の寒村の人々の生き様をリアルに描いた名作である。現在の終息の見えないコロナ禍の中でウイルスによる感染症に人間としてどう生きるべきかを考えさせられる小説である。