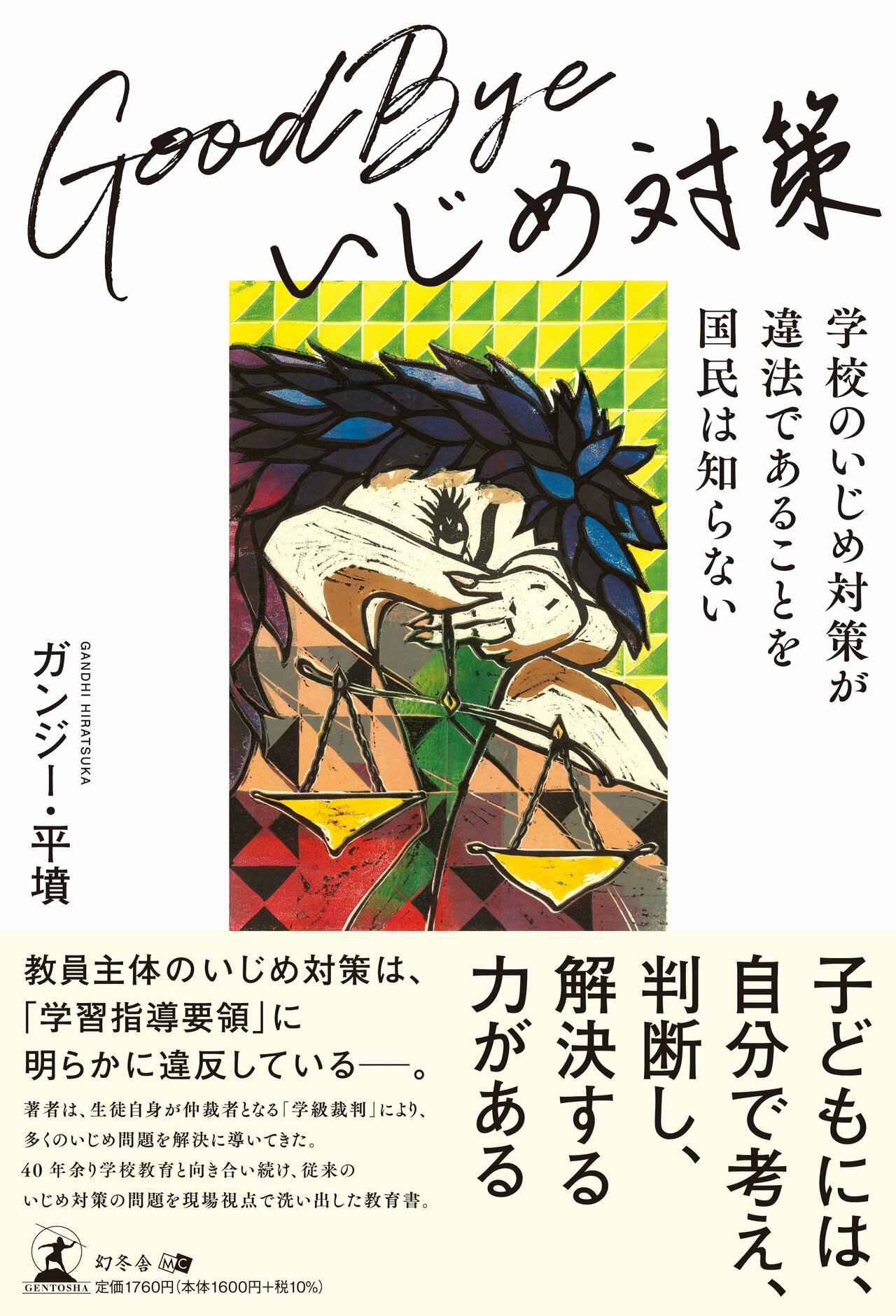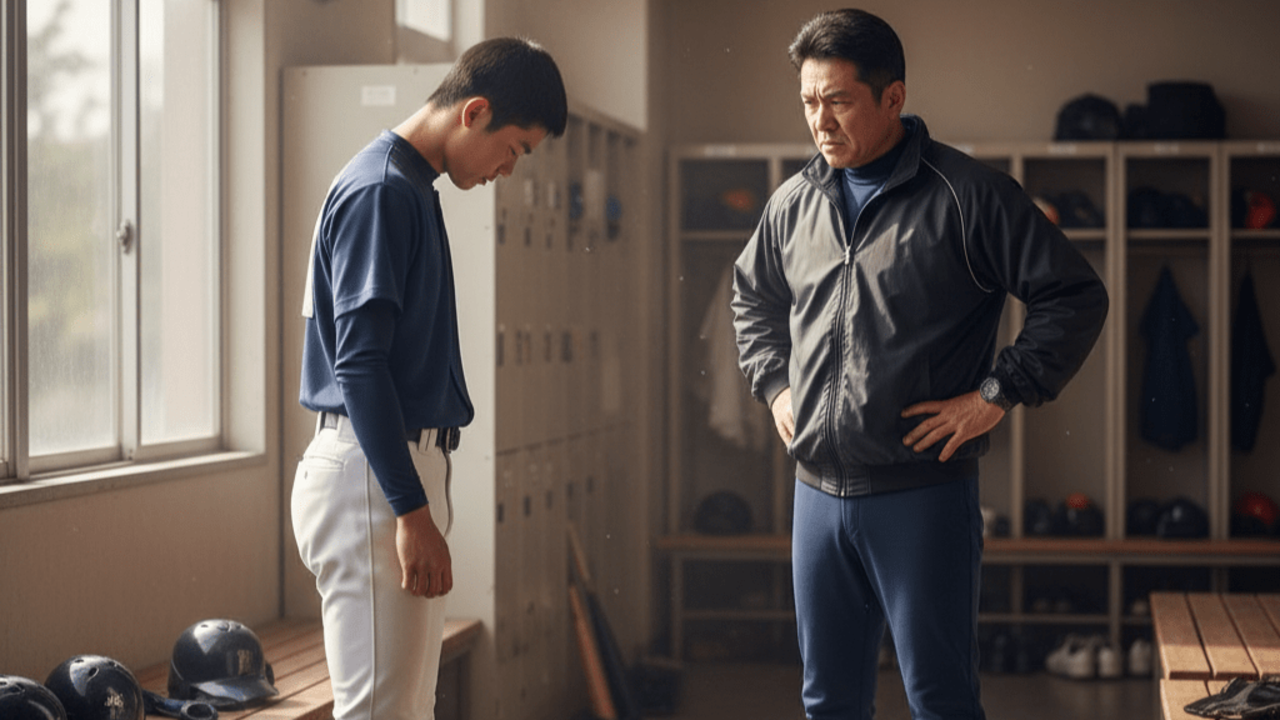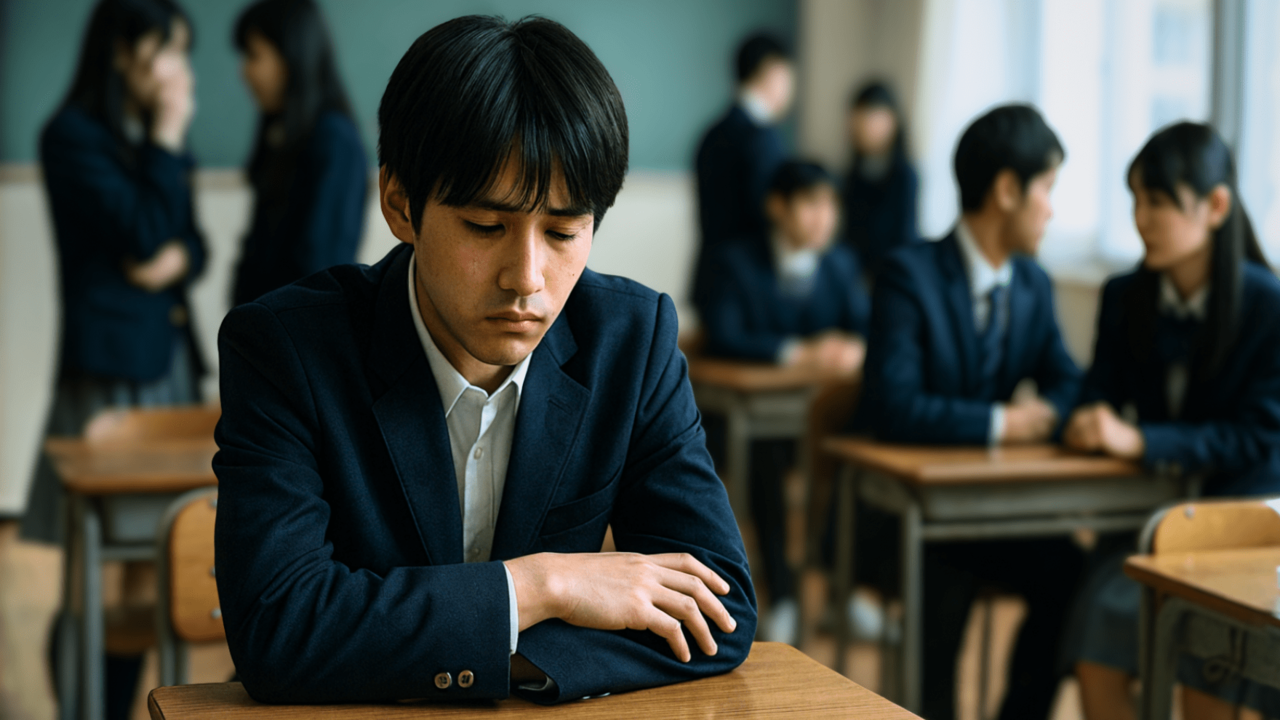解消とは、今までの状態や関係、約束などが消えてなくなること、問題をリセットして白紙に戻すことです。
いじめ解消の条件について文科省は、「いじめが止まっている状態が3カ月以上継続していること」「被害者が心身の苦痛を感じていないこと」と説明しています。
これは2016年の青森市の中学2年生の女子生徒が自殺した事件で、学校は生徒指導によっていじめが「解消」したと判断しましたが、その後も生徒に対するいじめは続き自死にいたったことによります。
文科省は毎年の「いじめ解消率(その年度内に、いじめがどれだけ解消したかを示す割合)」を公表しています。
2016年度が90・5%、2017年度は85・8%、2018年度は84・3%と毎年80~90%と高い水準を維持しています。
文科省は、「いじめ認知件数の多寡にかかわらず、いじめ解消率が高いことが重要」とか「解消率が高いなら、数が多いのはむしろ積極的に取り組んでいる証拠」 と説明しています。
そのため学校や教育委員会は、「いじめ解消率」のアップを至上命題としています。
しかし、「解決」から「解消」と文字を入れ替えただけで、目の前のいじめは3カ月過ぎようが何も解決していません。
実際、小学校でいじめを受けた子どもが、何年か後に仕返しをしたという事例は枚挙にいとまがありません。
学校では、毎年9割余解消したいじめが、翌年にはふたたびいじめの認知件数の過去最多を繰り返しているのです。