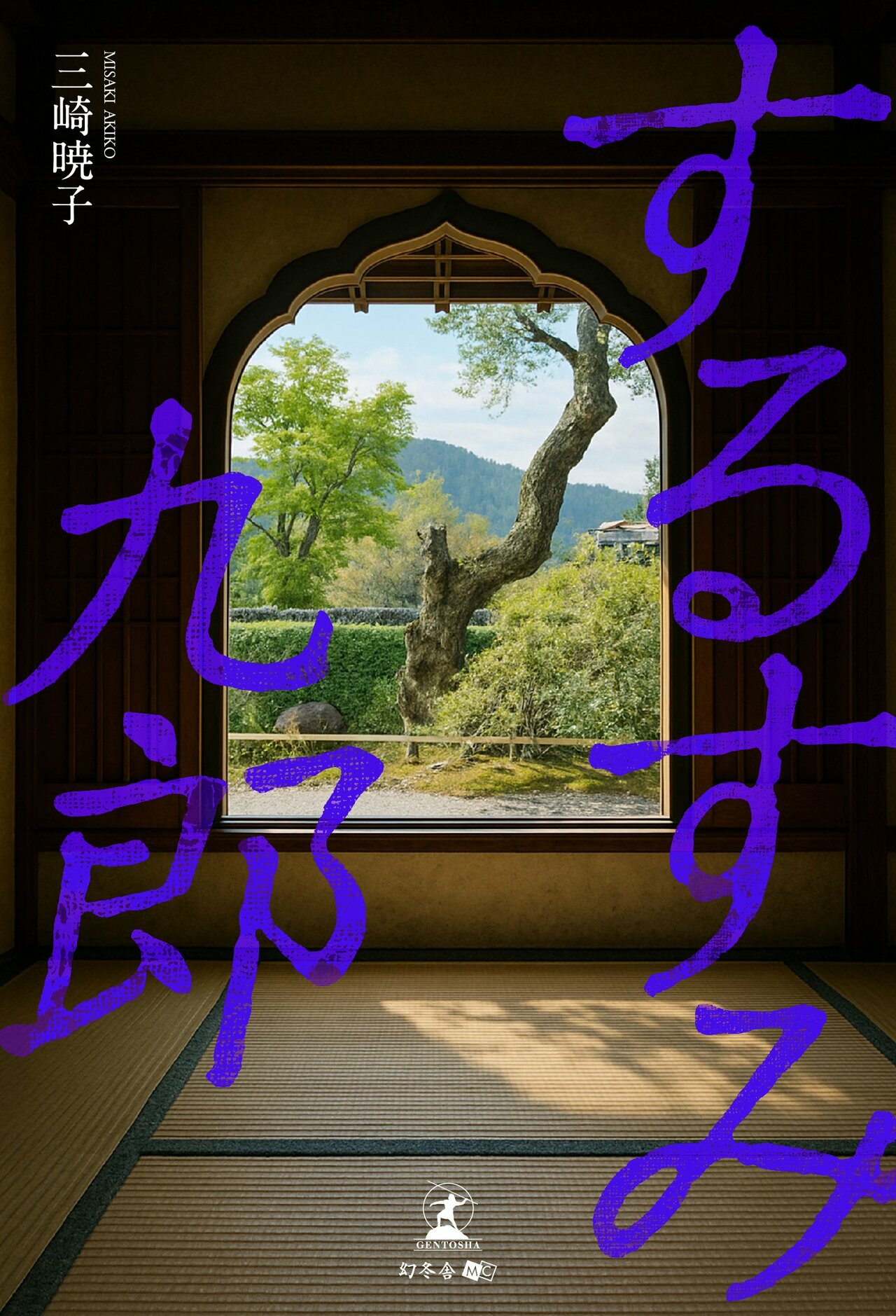「これ、この紙は鼻をかんだ後の畳紙(たとうがみ)の如くになっておって、一文字も読めんぞ。墨の跡も滲んで消えておるわい」
その時、九郎の黒く汚れた顔にも分かるほどの赤みが、ぱっと差した。そのまま固まったような姿は、何かにじっと耐えているように見えた。鳥の巣のような頭の上に、山桜の花片がひとひら載っている。そのどこか可愛げのある憫然(びんぜん)たる姿は、十分に秀衡の興を誘った。
秀衡はその、羞恥と後悔と挫折に捕らわれた姿を面白そうに眺め、ややあってこう云った。
「ともかくも難儀な旅であった様だの。腹も減ったるべし、行水でもしてから厨へ上がって飯を食え。話はその後だ」
ほっとしたような顔で足を引き摺りながら、従僕に導かれて去ってゆく若者は、途中でふと足を止めて、もう一度振り返って秀衡の顔を思わず確かめるように見た。作法は忘れているが、その邪心の無いふるまいの、いのちの素直さと、捨て犬が拾い主を見極めるが如きその痛切な目のいろを秀衡は見届けた。
その後ろ姿を見送りながら、呟いた。
(とうとう来たのか、一人で。大したものよ)
秀衡は源氏の落とし胤(だね)が京を出奔して平泉に向かった事は、京からの書状によって知っていた。
今来た若者が真にそれかどうかは、追々話を聞けば分かると思った。だが恐らくは間違いなかろう、そして心の内では、源氏の御曹司の着到を既に寿いでいた。天下は久しく平家の世だが、その一方、侵すべからざる北の王者である奥州藤原氏にとって、源氏の隠し駒を手にしておくのは何かの役に立つかもしれないと思っていた。
それとは別にしても、今の若者の純情を見て、己の胸のうちでことことと湧く清水(しみず)が生まれたような気がして、ふと笑った。
その日から、奇縁により巡り会ったこの天と地ほど境涯の違う両人は、期せずして生涯に亘って互いの胸襟(きょうきん)に住まいをした。