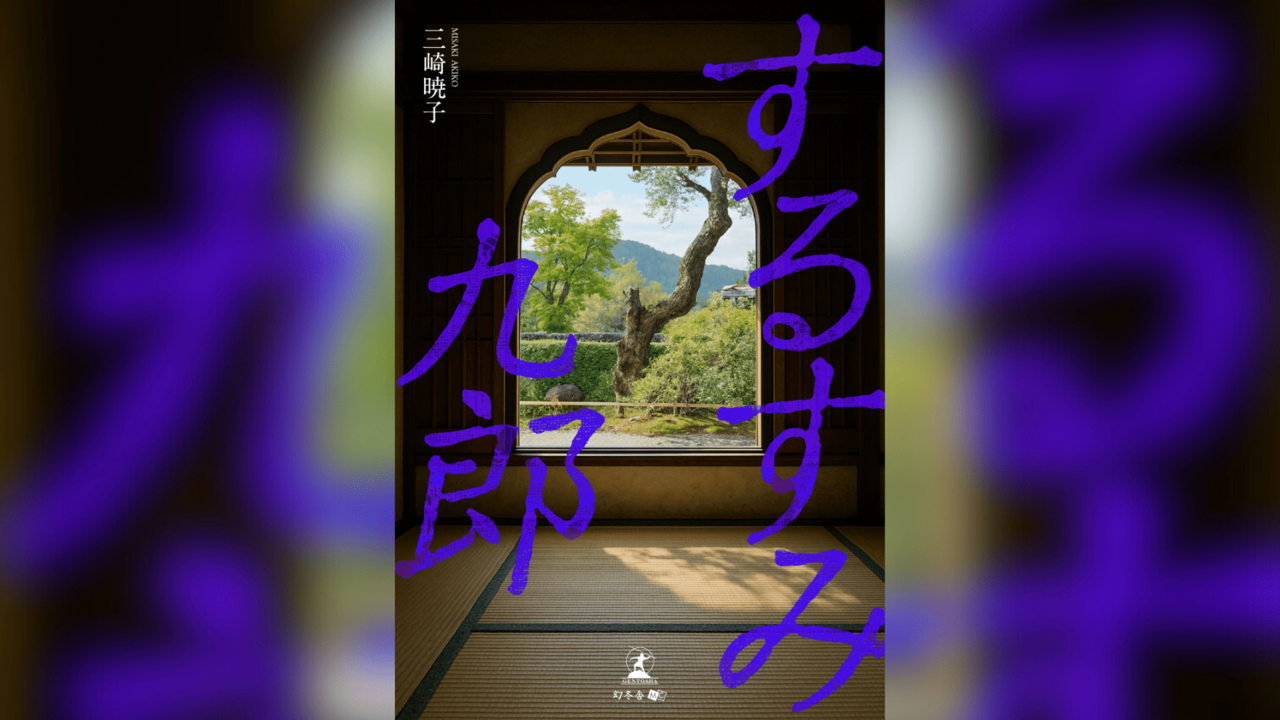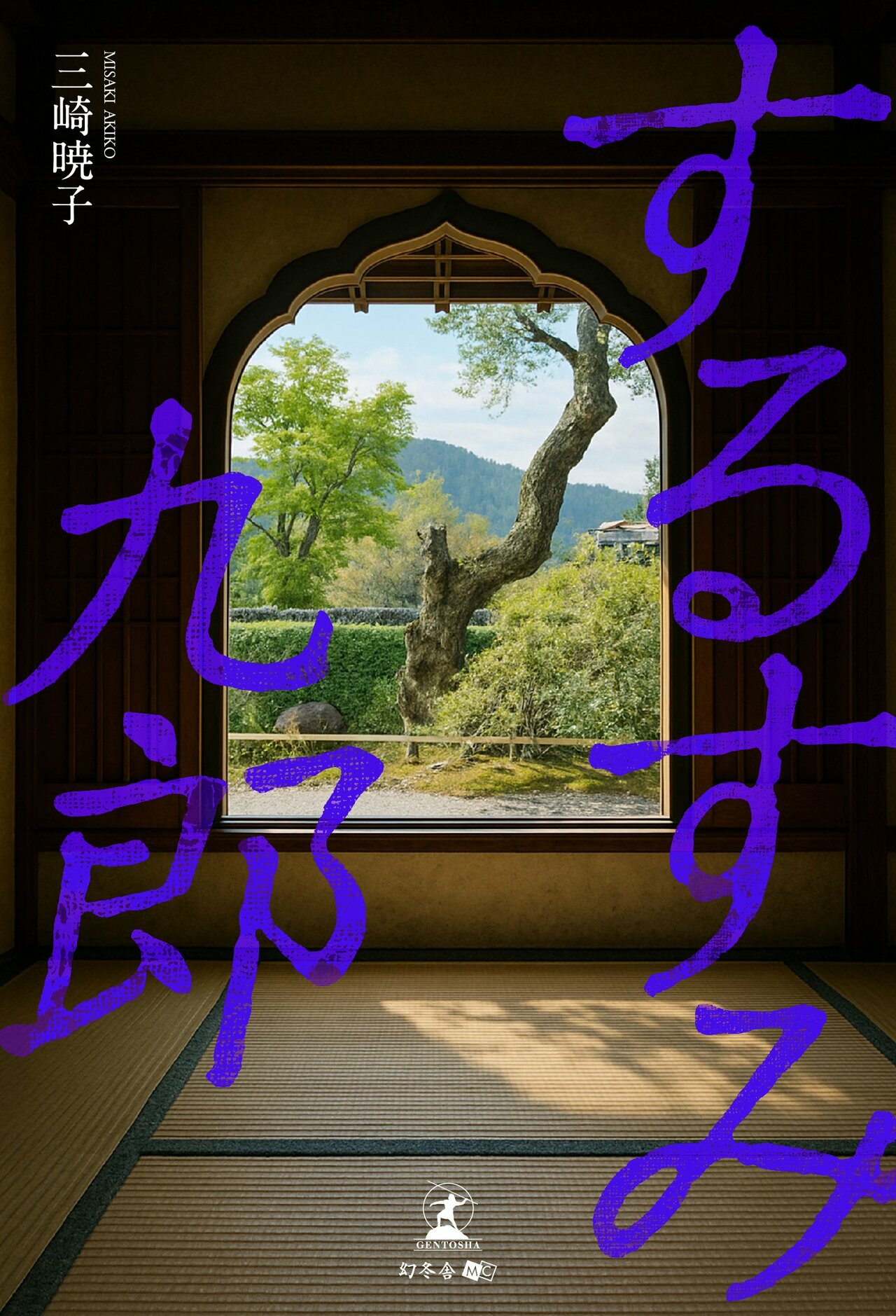【前回の記事を読む】1189年、奥州・平泉。最期の日々を過ごす源義経は、静かに“あの日々”を思い出していた――
第一章
承安五年(一一七五年)
旧暦三月二十二日 十七歳
奥州/平泉 伽羅(きゃら)ノ御所
当時、蝦夷地(えぞち)注1を除く北日本の全てを統べる太守(たいしゅ)、且つ又鎮守府将軍である奥州藤原家当主に謁見して、恐れ畏まるばかりにあらず、さても嬉しそうに笑う者は、嘗て見た事が無かった。
見ると、汚れくたびれてはいるが、元は平絹らしい袴を身に着け、しかし上は直垂(ひたたれ)ではなく小袖のみ、足元は裸足である。髪はそそけ立ち、顔は垢なのか日焼けなのか煤(すす)け立ち、しかしどこで拾ったか盗ったか古びた烏帽子(えぼし)を被り、太刀を佩(は)いている。
なるほど正体が分からぬ、と思いながらも、しかし秀衡は、その若者の正直そうな会心の笑顔に、心ならずも誘い込まれていた。
「そちはどこから参った、して名乗りは」
「京の都より参り申した、名は源九郎義経。先に亡くなりし源左馬頭義朝(みなもとのさまのかみよしとも)の九男にござります」
秀衡は胡坐の膝に片肘を支えて顎をさすった。
「いつ都を出たか」
「去年の春にて」
「さらば、一年掛かったという訳か。その間、どこで何をしておった」
「一口には申し上げ難うございます」
「如何にもな。さらば、その義経公が何故当地の基成公の親戚だと申すか」
九郎義経は、つと目を上げて云った。
「基成公のお父君は、我が継父の御従兄弟(いとこ)君、憚りながら某は、基成公の又従兄弟(またいとこ)にござります。又畏れながら、御屋形様の御前様には我が又従兄弟姪(またいとこめい)にまします。ここに、我が継父より御屋形様への書状を持ち来りてござります」
そう云って九郎は、小袖の襟元を摑み、襟の糸目を黄色に染まった歯で噛み切ると、暫くごそごそと探っていたが、襟の中から一筋の細布をするすると抜き出し、布を広げて、中から紙切れを一枚取り出した。
傍の所従にそれを持ってこさせた秀衡は、そのくしゃくしゃになった紙を広げて少し見た。そして顔を上げて、若者の顔とそれを見比べながら暫し黙っていたが、やがて穏やかに云った。