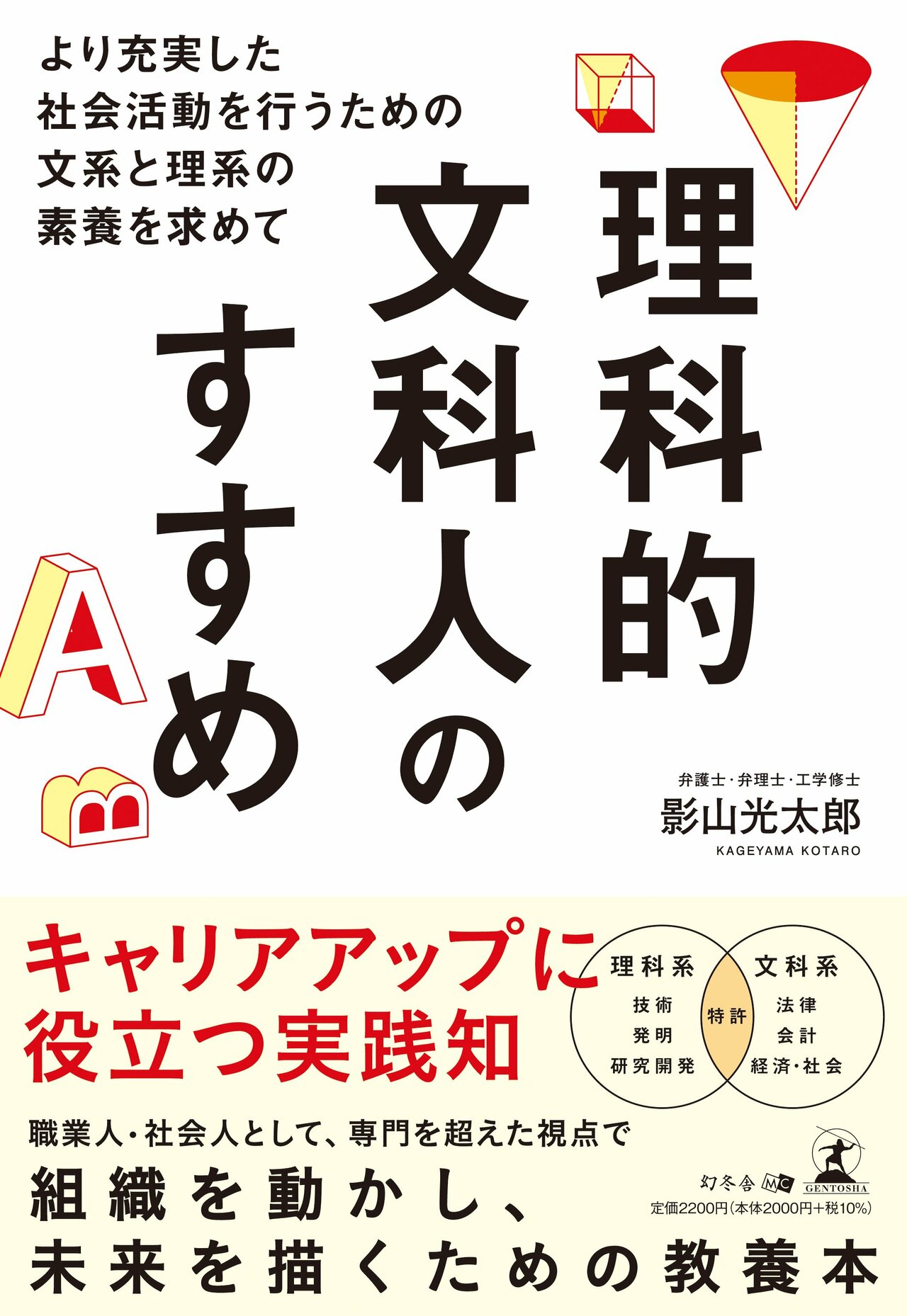3 会社を考える原点・旭硝子株式会社(現AGC)
(1)旭硝子株式会社に入社し製造現場(工場)を強く希望
東京大学修士課程(2年)修了後(1968(昭和43)年)、旭硝子株式会社(現AGC)に入社した。博士課程(3年)に進むと、人生が研究者として固まってしまうので、もっと広い可能性を考えた。
本当は、海外に留学をしたかったが、当時はそんなに簡単ではなかった(1ドル=360円で、かつ為替の交換等も自由ではなかった)。
旭硝子は自分の専攻分野がその会社で最主流になるような会社ということで選んだ。旭硝子はガラス、化学品等の製造販売を中心とした三菱系の総合化学メーカーであるが、板ガラスメーカーとしては、現在、世界最大である。
板ガラスは、窓ガラス、自動車ガラス等の身近に普通にあるガラスである。そして研究者であることを辞めて実業界に出る以上、研究所ではなく製造現場(工場)での勤務を強く希望した。
これが容れられ、鶴見工場(現、京浜工場)硝子製造第1部並板課に配属された。鶴見工場は、当時、多くの板ガラス製造装置を有し、板ガラス製造工場としては世界最大であった。
ここでの2年間のうち、最初の1年は板ガラス製造装置の建設に従事し、後の1年は三交代勤務でガラス製造の現場監督を行った。
板ガラスは、ソーダ灰と珪砂とカレット(ガラスの破砕くず)と他の少量成分を1600℃以上で槽窯(タンク)内で加熱溶解させてロールで引き上げ製板して(当時、私が従事していた装置)、製造するものである。
この製造装置は巨大で、幅20m、長さ60 m、高さが建物6階分程度あった。
ガラスの製造においては、「筋」(溶解の不均質によって生ずる、ガラス面を透視したときのゆがみ)「砂利」「泡」等の欠点の発生を抑えて歩留まり(製品の収率)を上げねばならない。
その製造には、溶解・製板の過程を通じて種々のノウハウがあった。
例えば、溶解槽での原料の反応の発泡状況を着色ガラスを通して見て溶解状況を観察するわけであるが、この良否の判断が経験を積まないと難しく「窯には神様がいる」などといわれたものである。
三交代勤務とは、朝出、中出、夜勤というように一日を三等分して勤務するわけである。
これは前記のようにガラス製造は高温で行うので、いったん加熱・溶解したら5年程度はそのまま製造を継続するためである。
【イチオシ記事】折角着た服はゆっくり脱がされ、力無く床に落ち互いの瞳に溺れた――私たちは溶ける様にベッドに沈んだ
【注目記事】「ええやん、妊娠せえへんから」…初めての経験は、生理中に終わった。――彼は茶道部室に私を連れ込み、中から鍵を閉め…