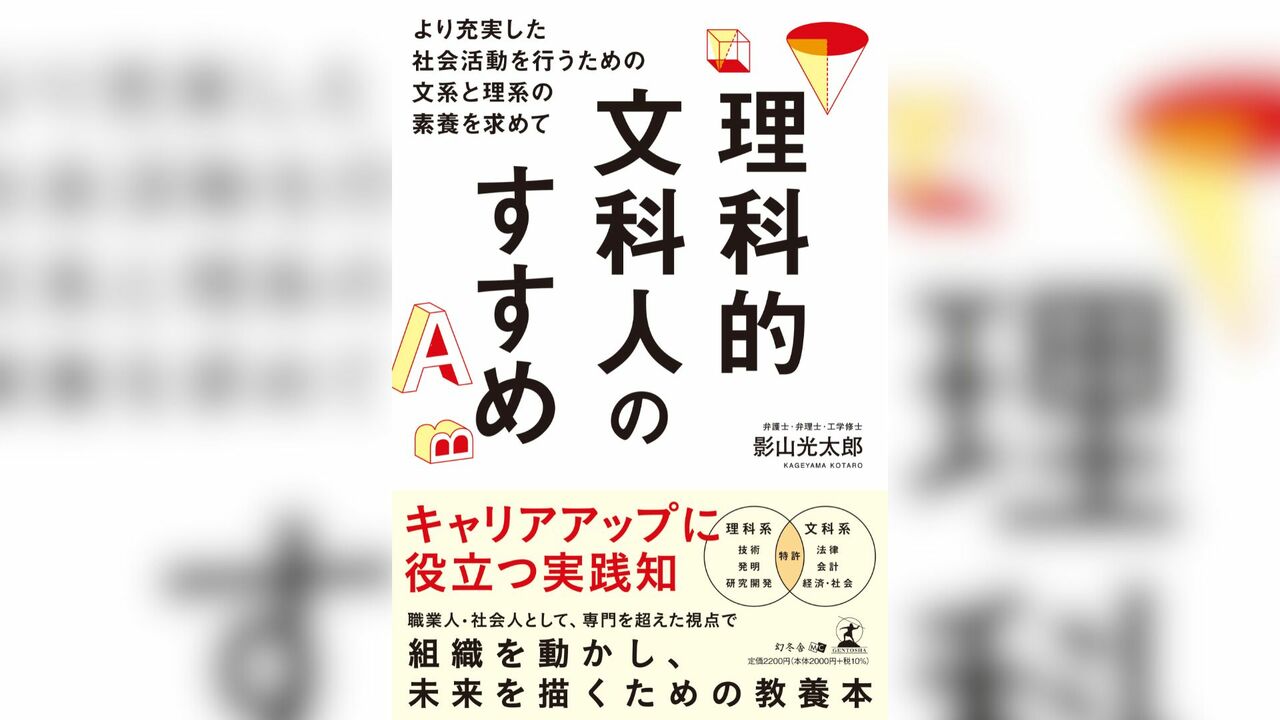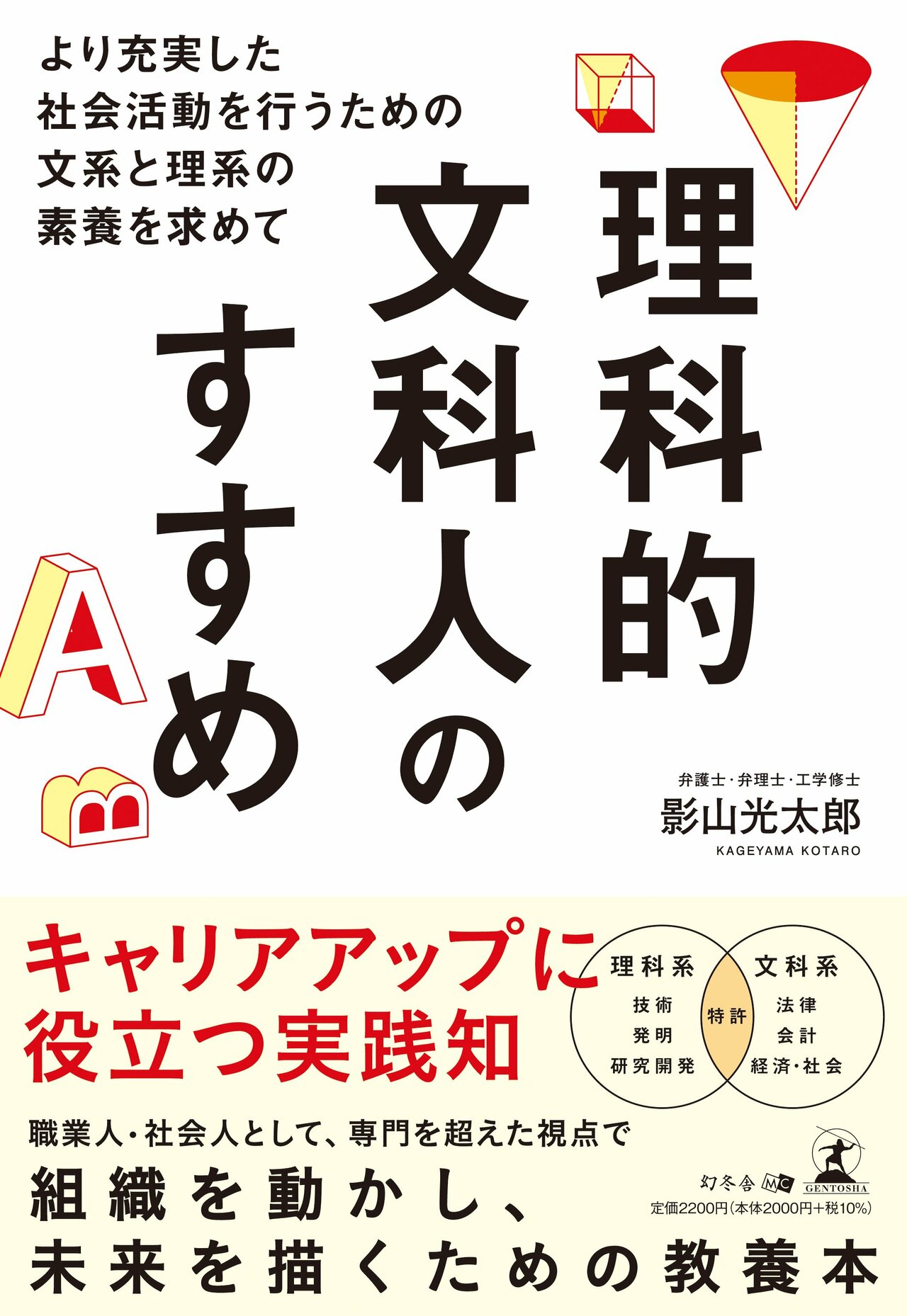【前回の記事を読む】「国がつぶれるとは思わなかった」――海軍の技術将校だった父。戦後、公職追放され家族は貧しい生活を送っていた
第1章 筆者の経歴
2 大学で理科系の道を目指す
(2) 世界一流の研究に触れた大阪大学理学部関研究室での実験・研修
ちなみに、その後、Asは半導体材料の産業上重要な原料として用いられるようになった。
As2S3のガラスを研究対象とすることは、東京大学の指導教授から勧められたが、このようなガラスは、当時、赤外線の透過性が良くて注目され、Asが半導性物質であることから、その研究も興味深いと思われたのであろう。
なお、この研究は直接何かに役立つということはない基礎的な物質の構造の研究である。
私が前記のような成果を上げることができたのは、関研究室が世界で最も優れた低温からの熱測定装置を有していたからである。
熱測定及びこれに基づく物質の分子論的構造の研究において関集三教授のグループは、世界的実績を上げていた。
筆者は東京大学の修士課程の学生であったが、この装置を使わせていただきたいと思って関教授に手紙を書いた。
そうしたら関先生から、筆者が測定したいと考えている物質についてかつて測定されているかどうかを調べてみなさいと指示された。そこで図書室で数日掛けて(当時は、このように時間がかかった)、ChemicalAbstract(世界の文献の要約)を調べたところ、ソビエトのV.V.タラソフという人が測定していることが分かった。
そこで、そのことを知らせると、その測定結果を拡大図示してみなさいと指示された。そこで指示に従って図示したところ、その測定値のバラツキと比較して関先生のところの装置で測定したならばより精度の高い測定値が得られることが分かった。
その結果、測定が認められることになった。つまり、未だ測定したことのない物質か、従来の測定値より精度の髙いものでなければ意味がないということである。筆者は、この一連のやりとりで世界一流の研究とはこういうものかということを教えられた。