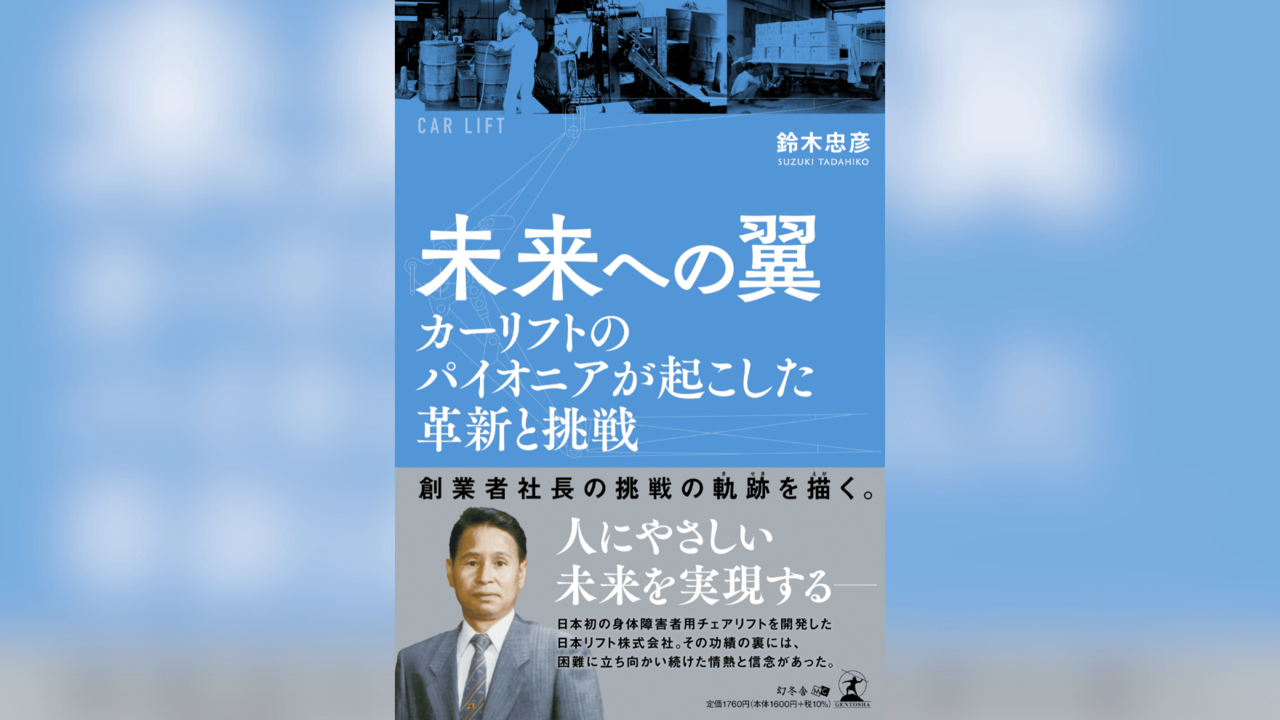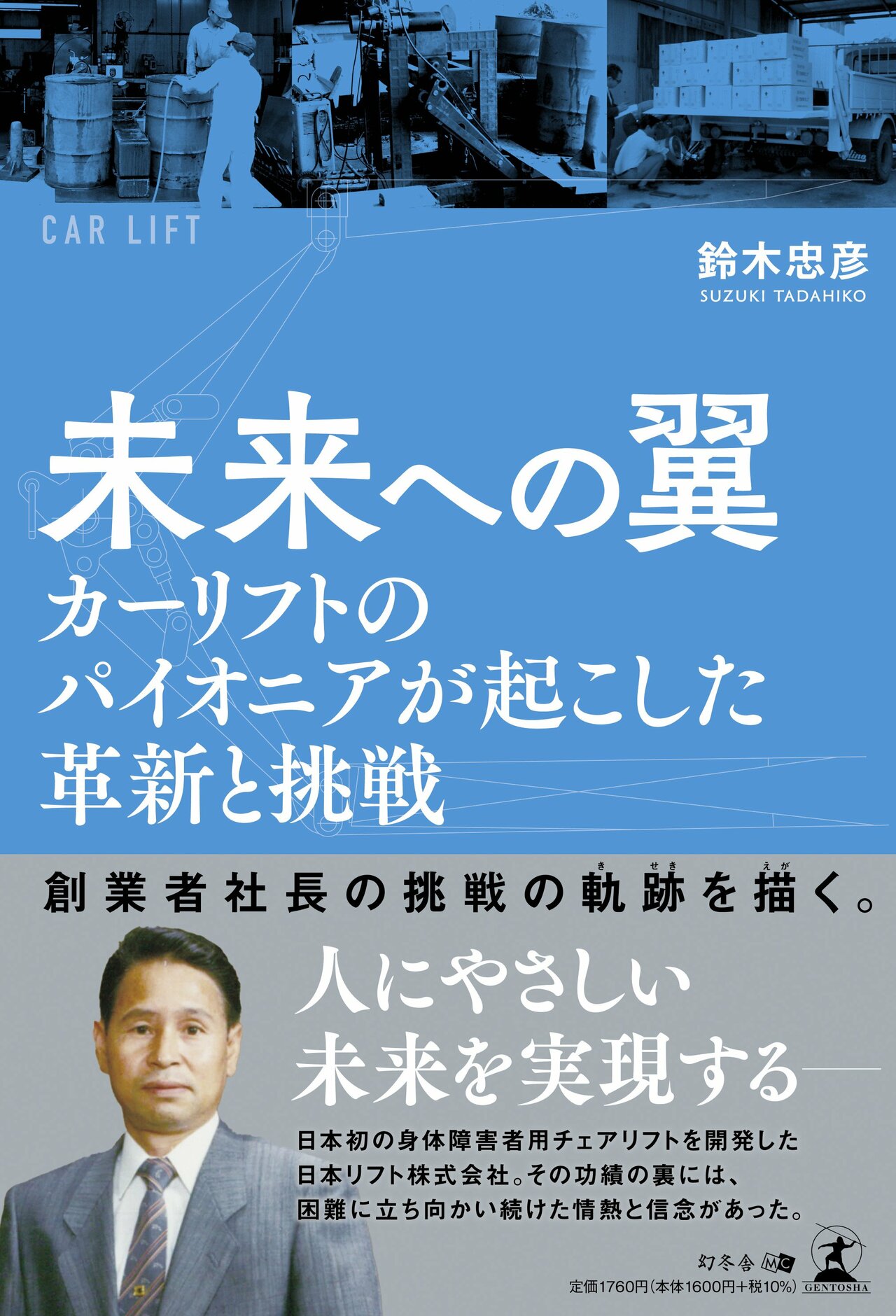【前回の記事を読む】三歳の夏の夜、遠くの町が真っ赤に燃えているのが見えた。それが太平洋戦争末期一九四五(昭和二十)年七月の甲府空襲だった
第一章 機械と向き合う人生の始まり
車との出会い
戦後父は郵便局を辞め、農業と山仕事をするようになっていた。私は小学生の頃から手伝いをさせられた。
しかし家の手伝いをしていたのは私だけではない。当時は小学生でも農業の手伝いをするのはごく普通のことだった。だから学校に農休みという休みがあった。田植えや稲刈りの時期には、休校になる仕組みだ。その間は子供も農作業の手伝いをしなければならない。
その頃住んでいた家は、玄関を入ると大きな土間があり右側には牛小屋があった。牛に餌をやり世話をするのも、小学校の頃から私の仕事だった。
当時は牛とか馬に鍬を引かせて、農地を耕した。馬や牛は労働力として貴重な存在だった。出来なかったところは人の力で耕した。
春になると水田に水を入れて平らにならし、細い縄を張る。そして十人位並んで田植えをした。当時は「結(ゆい)」という制度があり、人手が足りない時はみんなで助け合って作業を進めた。
水田の中に雑草が生えると、稲の成長に悪影響が出てしまう。今は除草剤や草取り機を使うのだろうが、当時は草を見つけると四つん這いになり手で草を取り除いたものだ。
またその頃、開拓団が山の木を切り倒して土地を耕し農地を広げていた。馬や牛で農地を耕していた私達とは違い、開拓団は大型のトラクターを使っていた。父はトラクターの運転手に頼んで、私をトラクターの脇に乗せてくれた。