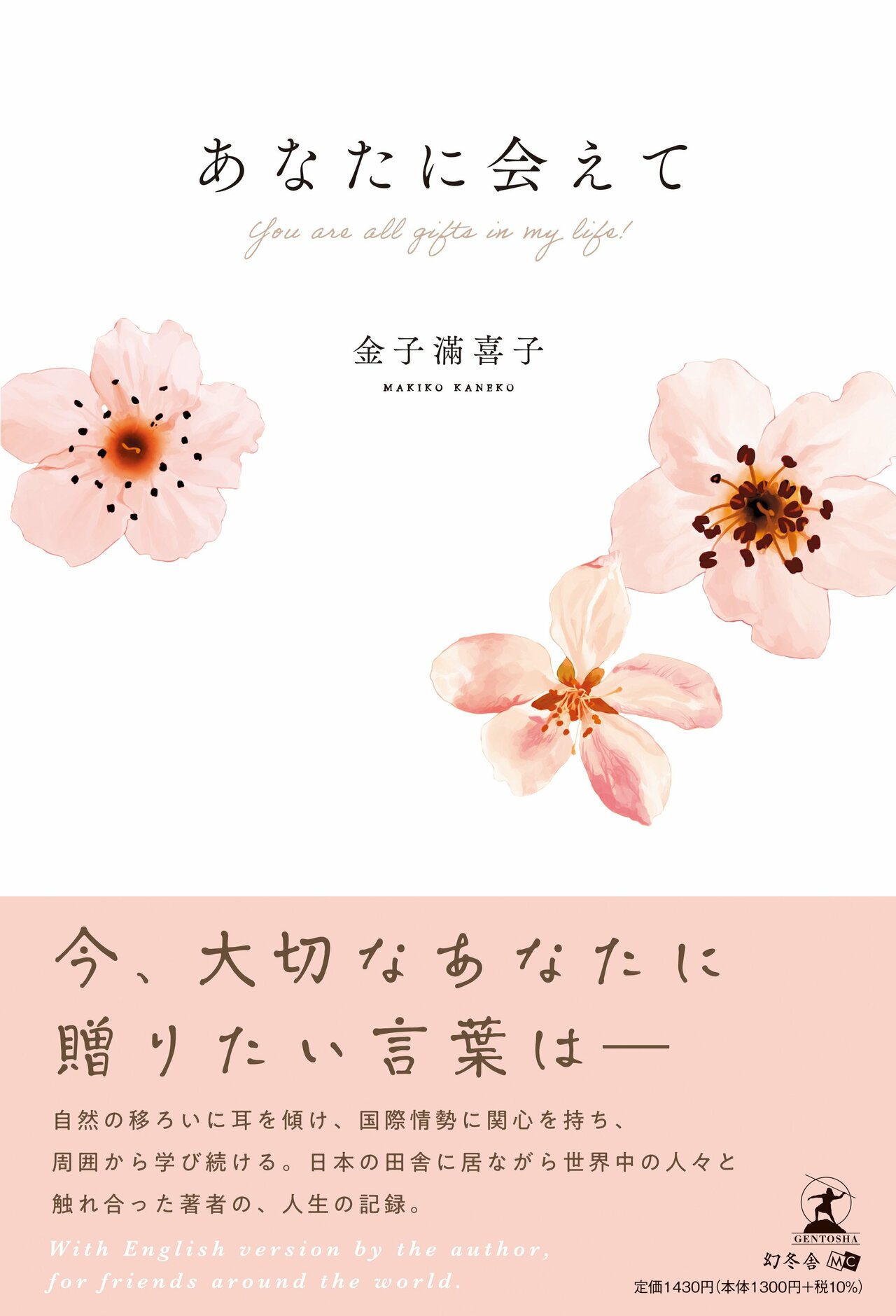旅が教えてくれたもの(青春編 京都・北陸・中国大陸)
本の世界と旅
「旅と本は似ている」と誰かが言っていました。確かに、未知のものに出会うワクワク感や感動は、旅でも読書でも味わえるでしょう。
けれども、実際に我が身に起こることは旅の中でしか味わえません。たとえそれがどんなにささやかな会話やありふれた食事であっても、それは長い間心に残る我が身が体験する現実です。
広島の県北の小さな町で生まれ育った私は、アンシリーズやジェーン・エアなどを愛読し、本の中の世界を心に温めて思春期までを過ごしました。
人口 2 万人という山に囲まれた町で当時は活気もあったのですが、高校生になった頃から、どうにも我が町を狭く、息苦しく感じたものです。
本は唯一、ぞくぞくする外の世界に通じる扉でした。当時は観光のために旅をするような時代ではありませんでしたから。
京都──1976年~1980年
そんな私が旅の醍醐味を知ったのは、立命館大学に入ってからでした。大学のキャンパスは京都御所の近くにあり、下宿は『方丈記』を書いた鴨長明で有名な下鴨神社のそばにありました。
3 回生からは文学部が衣笠に移転したので、花園に下宿し、妙心寺の境内を自転車で駆け抜けて大学に通いました。
その途中には仁和寺があり、大学の正面には龍安寺、隣には金閣寺がありました。初めて金閣寺を訪れた時、金箔ではなかったものの、周りの自然と調和したその威容に感動しました。
金箔の金閣もそうでない金閣もどちらも好きです。京都にいれば、授業の合間でも一歩足を延ばせばそこは歴史的な古刹です。
現在の世界遺産に囲まれて暮らしていた当時の私を振り返り、何と恵まれていたのだろうとため息が出ます。
ただ、当時は今ほど観光ブームではなく、もっと静かで生活の中にお寺があるといった感じでした。
【イチオシ記事】店を畳むという噂に足を運ぶと、「抱いて」と柔らかい体が絡んできて…
【注目記事】忌引きの理由は自殺だとは言えなかった…行方不明から1週間、父の体を発見した漁船は、父の故郷に近い地域の船だった。