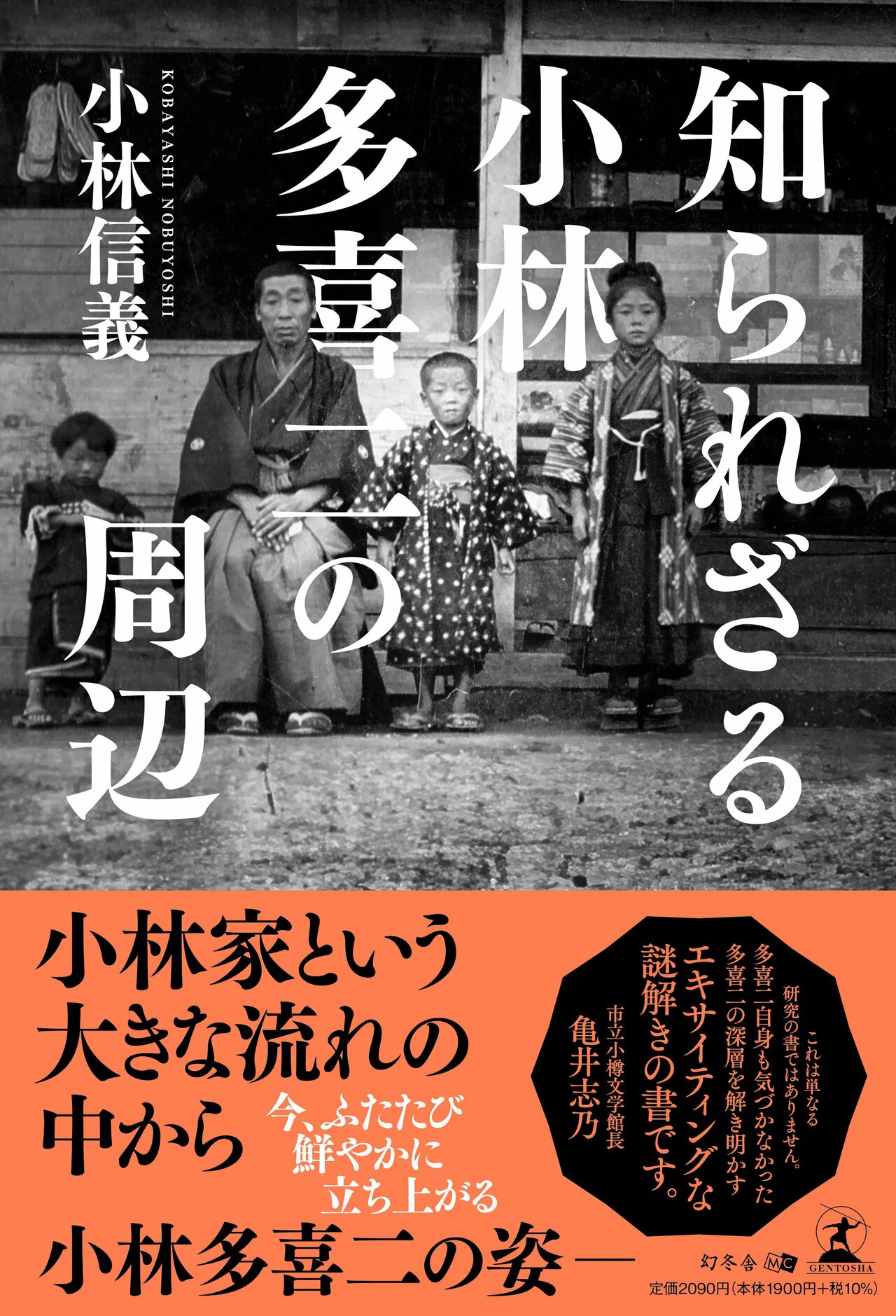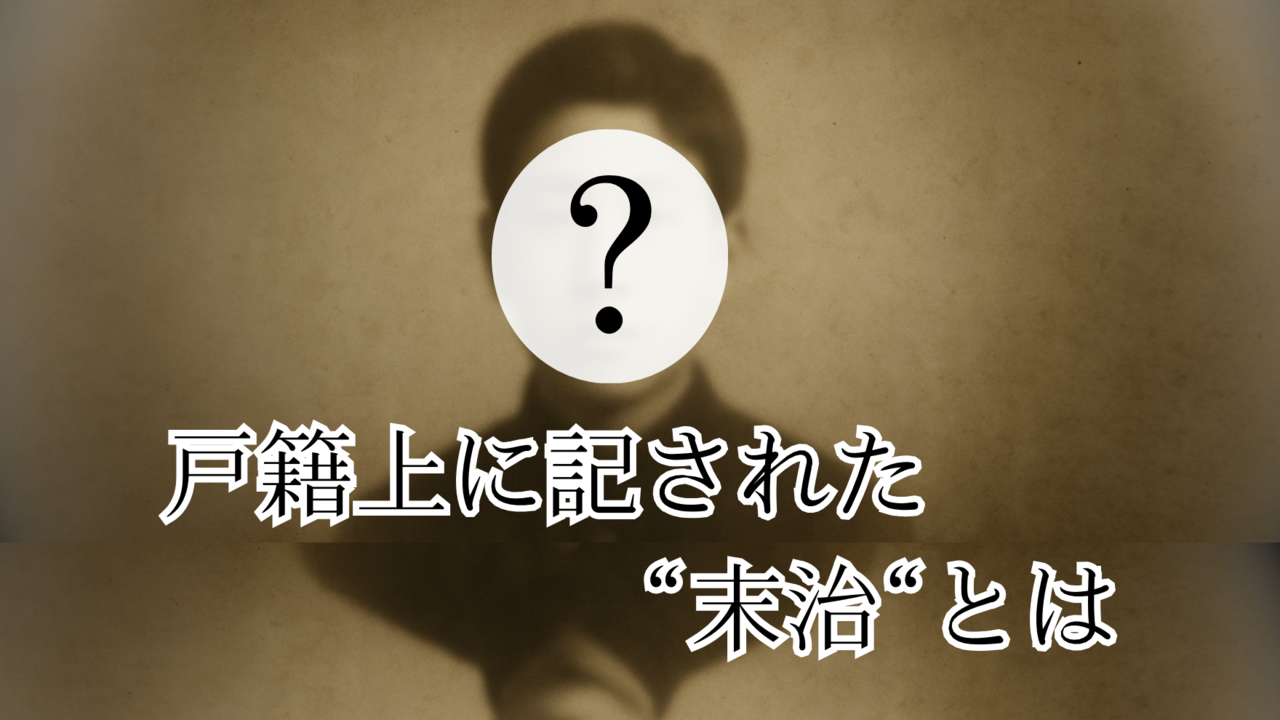多喜二の父末松の兄である慶義は、小樽のパン製造で財をなしました。秋田の土地を手放さざるを得なかったことで小林家を衰退させた意識があったと思いますが、末松一家を小樽に誘ったのは家長としての義務感からでしょう。
末松・セキ夫婦は住み慣れた故郷を離れられずにいました。しかしながら長男の多喜郎には、さらなる教育を与えるべく明治40年(1907)の春から小樽の学校に通わせることになりました。
その経緯については第4章も参照してください。多喜郎はその前年、明治39年(1906年)3月に4年制の尋常小学校を卒業していたはずです。
そして経済的困窮のため、その後の進学ができなかったと私は推測します。その頃の小学校は4年制や6年制の端境期でした。新制度によると小学校5年生および6年生に相当する2年制の高等小学校がありました。
1年間のブランクがあったと私は考えますが、多喜郎が小樽に来て通い始めた学校は「高等小学校」に相当するのではないでしょうか。ところが多喜郎は小樽の慶義宅で生活を始めて間もなく、満12歳になる直前の明治40年(1907)10月5日に死亡してしまいました。
前記のように多喜郎が4年制の尋常小学校を卒業した明治39年(1906)3月頃の末松・セキ夫婦の経済状態はかなり逼迫(ひっぱく)していたと思われます。
そのため秋田で高等小学校に進めることができなかったのでしょう。末治はその年、明治39年(1906)3月3日に3男として生まれました。
当時の経済状態で生まれてくる児を育てることができなければ、他家に出した可能性が高いと思います。当時の家制度における家長の権限は絶大でした。
養子に出すには家長の承認をもらう必要がありました。この時の慶義は小樽におり簡単に連絡がとれなかったかもしれません。
やむなく戸籍は小林家のまま……というのが私の推測のひとつ目です。その頃は生まれた子供をはじめから他家の戸籍に入れてしまう強引なことも行われていたようです。
しかしながらこれでは違法です。これとは逆の場合もあり得ます。末治という他家の児を、末松・セキの子として籍に入れたという可能性もないわけではありません。
しかしながら末治を育てた形跡はありません。またそうしなければならない理由もありません。
【イチオシ記事】その夜、彼女の中に入ったあとに僕は名前を呼んだ。小さな声で「嬉しい」と少し涙ぐんでいるようにも見えた...
【注目記事】右足を切断するしか、命をつなぐ方法はない。「代われるものなら母さんの足をあげたい」息子は、右足の切断を自ら決意した。