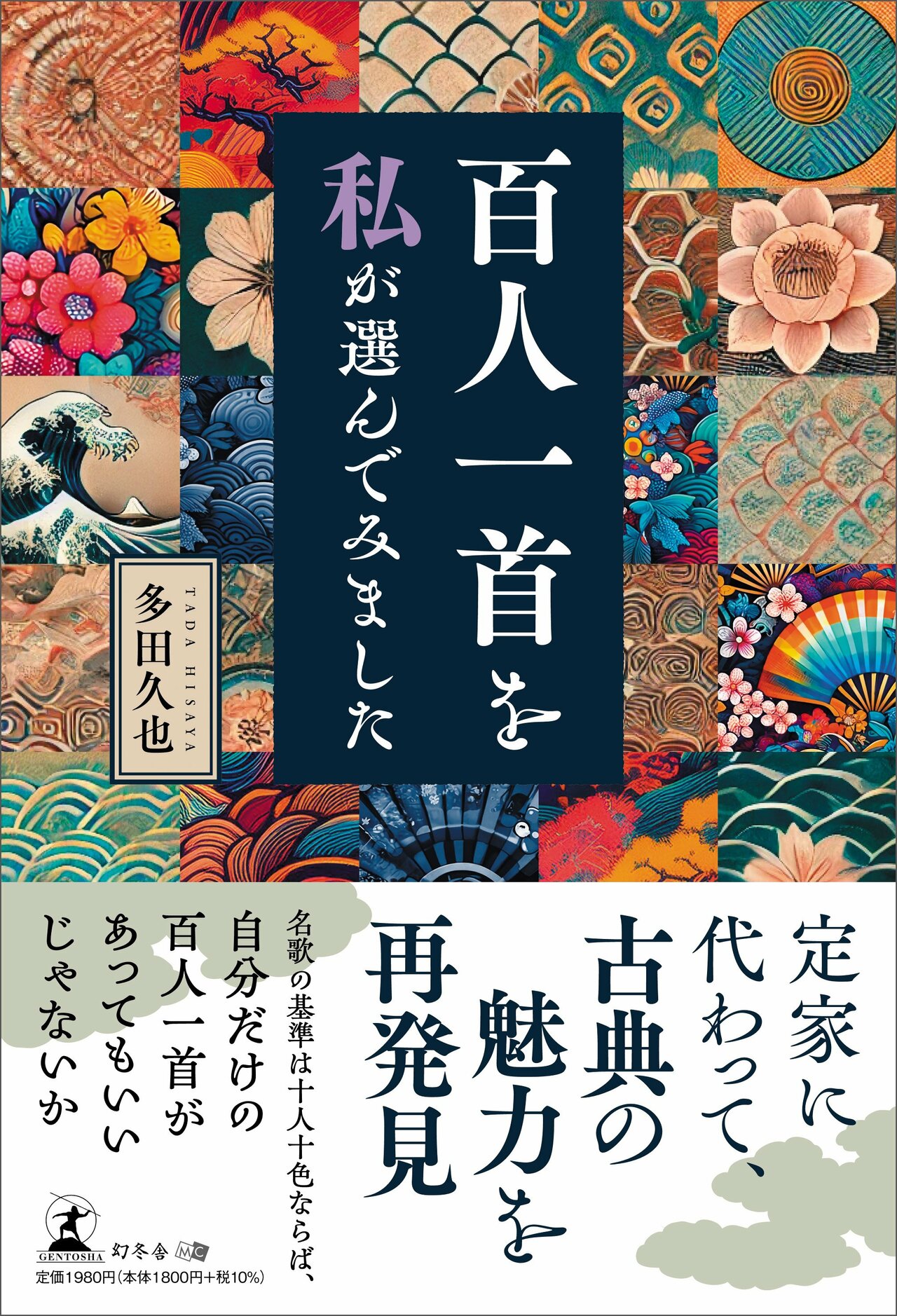9 大伴家持(七一八~七八五)
我がやどのいささ群竹 (むらたけ)吹く風の音のかそけきこの夕(ゆうへ)かも
(わが家の庭の清らかな竹の群立ち、その竹を吹く風の、葉ずれの音がかすかに聞こえてくる、この夕べの物寂しさよ)
「いささ群竹」の「いささ」は清浄な笹という解釈もされているが、私は詞通り「竹の群立ち」と採りたい。「かそけき」は光、色、音などが知覚できるかできない程度の儚さで、家持がはじめて開拓した詞である。
夕暮れのほのかな光の中、ひとりたたずむ孤独な家持。わが家のわずかばかりの群竹を春風がそよそよと通り過ぎてゆき、その葉ずれの音がかすかに聞こえてくる。ああ、この夕暮れのやるせない寂しさよ、とひとり呟くのだ。ひとり静かにこの歌を読んでいると、かさかさという音がわずかに響いてくるような気がする。
もし、『万葉集』の中から一つだけ好きな歌を選びなさいといわれたら、私は迷わずこの一首を選ぶ。田辺聖子はこの歌を「こまやかな心のふるえの独白を耳元で聴く思いがする。万葉のメランコリイはこの一首に凝って珠となった」と賛嘆している。
数年前の春、「哲学の道」をのんびりと歩いて銀閣寺に行ったことがある。もう閉館時間が迫る夕方であった。帰りの出口の方に歩いて、銀閣寺のちょうど裏側にさしかかったときだった。どこからともなく竹の葉がさらさらとそよぐ音が聞こえてきた。そのとき家持のこの歌が心の中に浮かび上がり、しばらくそこに立ち尽くしていたことが思い出される。
選抜首と同じ時期に詠われたのが次の二首、
春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影に鶯鳴くも
(春の野に霞がたなびいて、何となしにもの悲しい、この夕暮れのほのかな光の中で、鶯が鳴いている)
うらうらに照れる春日にひばり上り心悲しもひとりし思へば
(うららかに照っている春の日の光の中に、ひばりの声が空高く舞い上がって……、この心は悲しみに深く沈むばかりだ。ひとり物思いに耽っていると)
これら三首に共通するものは、家持独自の繊細な感性が捉える「春愁」である。特にこれだという悲しい原因があるわけではない。しかし、群竹の風音も、夕霞の鶯も、昼下がりのひばりの声も、心の奥底の感じやすい部分に触れてきて、春の哀しみに心を震わせるのだ。この微妙な感覚は現代の私たちにも共有できるものではないだろうか。
家持が到達した憂愁の境地は、極めて近代的といって良い。このとき、家持は三十六歳であった。
【イチオシ記事】妻の親友の執拗な誘いを断れず、ずるずる肉体関係に。「浮気相手と後腐れなく別れたい」と、電話をかけた先は…
【注目記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。ただ、妹の夫であるというだけで、あの人が手放しで褒めた人というだけで…