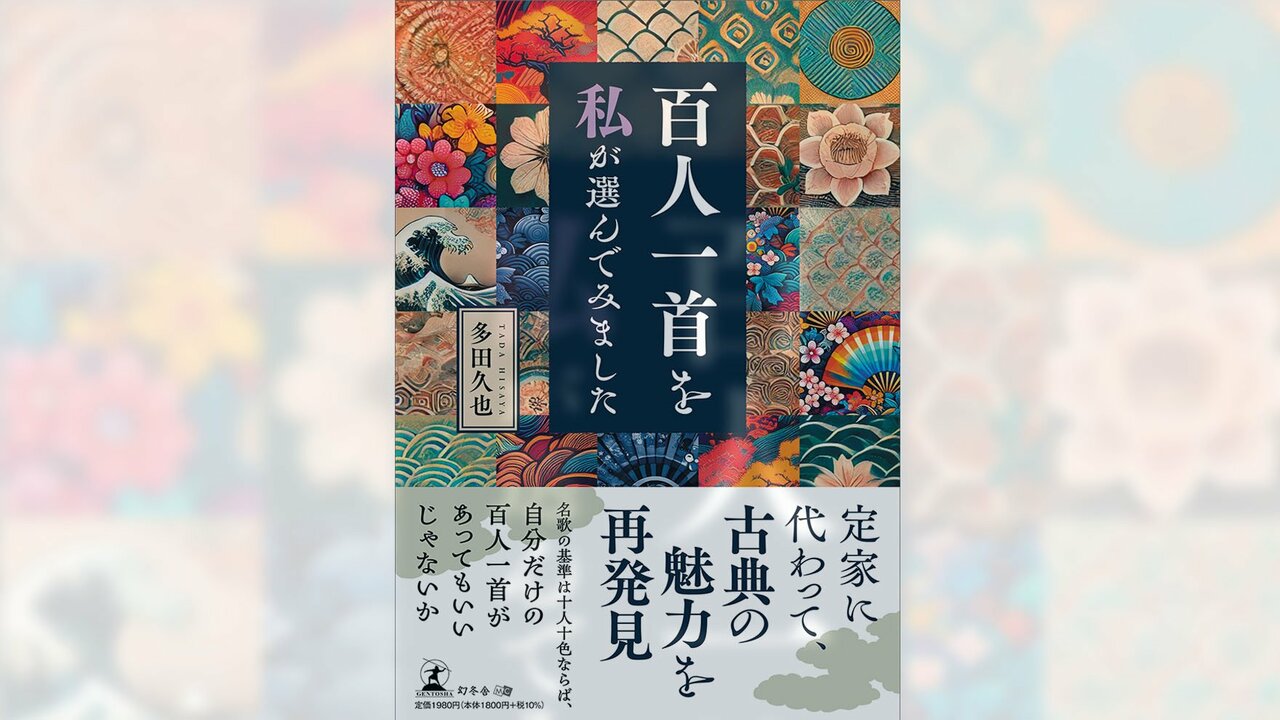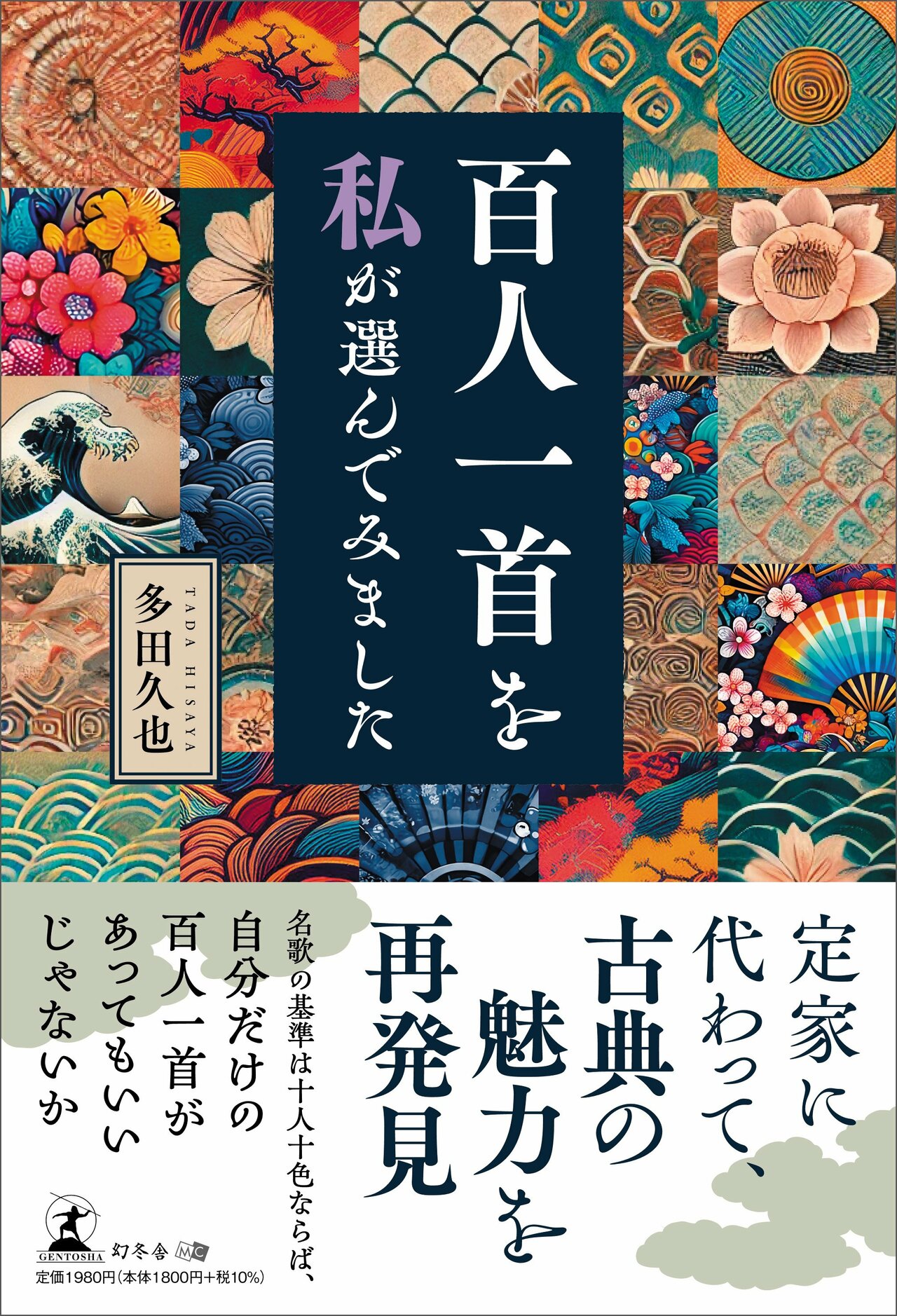【前回記事を読む】美しい自然の事象を清らかに歌い上げる山部赤人。一方、大伴旅人の梅の歌は幻想的ですらある
8 山上憶良(生没年不詳)
若ければ道行き知らじ賄(まひ)はせむ黄泉(したへ)の使(つかひ)負ひて通らせ
(まだ年端もゆかないので、どう行ってよいかわかりますまい。贈り物は何でも致しましょう。黄泉(よみ)の使いよ、どうか背負って行ってやって下さい)
『万葉集』九〇六番の歌であるが、この一つ前に「男子名は古日に恋ふる歌」という慟哭の挽歌がある。それは次のような内容だ。
「願いに願ってやっと授かった白玉のようなかわいい男の子、名は古日(ふるひ)。
一人前に成長するのを見届けようと楽しみに育てる。ところが古日は急に病気になり、どうしてよいのかわからず天の神に祈り、地の神を拝み、居ても立ってもいられない。そして、持ち直すことなく息絶えてしまう。
父親は思わず跳びあがり、地団駄踏んで泣き叫び、伏しつ仰ぎつ、胸を叩いて嘆きくどいた。ああ、これが世の中を生きていくということなのか」
このような悲痛に満ちた長歌が詠まれ、次に詠まれた反歌が今回の歌である。長歌も反歌も涙なしでは読むことができない。
憶良は漢学に造詣が深い教養人で、五年間遣唐使として儒教や仏教の最新の学問を研鑽してきた。聖武天皇の東宮時代に侍講を務めた。その後筑前守に任命され、大宰帥であった大伴旅人と親しく交わり、筑紫歌壇を形成した。
社会的な優しさや弱者を鋭く観察した歌を多数詠んでおり、当時としては異色の社会派歌人として知られた。『万葉集』に八十首以上掲載され、勅撰入集は五首ある。
憶良といえば、子どもへの愛を歌った歌人として有名である。
銀(しろかね)も金(くがね)も玉も何せむにまされる宝子にしかめやも
(銀も黄金も玉もいったい何になろう。これら優れた宝も子に及ぼうか。及びはしないのだ)
瓜食(は)めば子ども思ほゆ栗食めばまして偲はゆ何処より来りしものぞまなかひにもとなかかりて安眠(やす)し寝(な)さぬ
(瓜を食べると子どもが思われる。栗を食べるとそれにもまして偲ばれる。こんなにかわいい子どもというものは、いったいどういう宿縁でどこからわが子として生まれてきたものなのであろうか。そのそいつがやたらに眼前にちらついて安眠させてくれない)
憶良が病に沈んだとき、涙を拭いながら悲しんで詠んだ辞世が次の歌だ。
士(をのこ)やも空しくあるべき万代に語り継ぐべき名はたてずして
(男子たるものは、為すこともなしに世を過ごしてよいものか。万代までも語り継ぐに足るだけの名というものを立てもしないで)
大東亜戦争中は精神鼓舞の材料として使われていたが、後世にまで名を残そうという心意気を示したこの歌は、現代にも通ずるものがある。