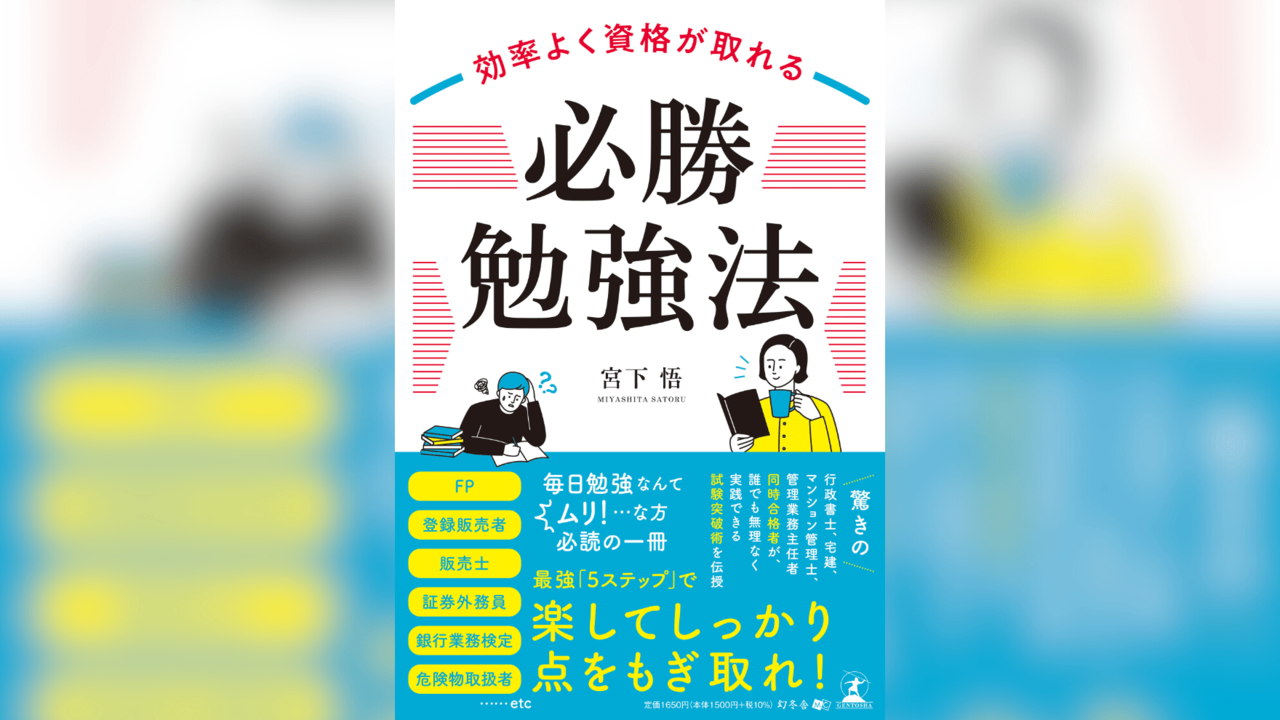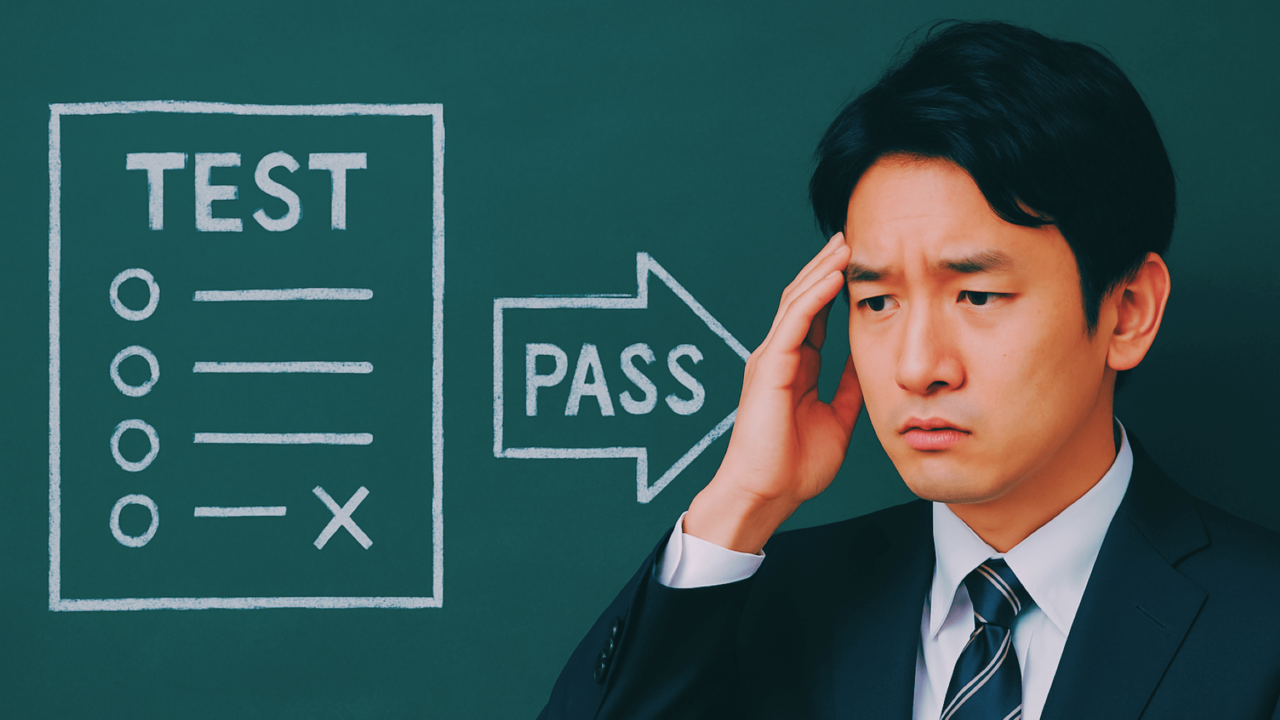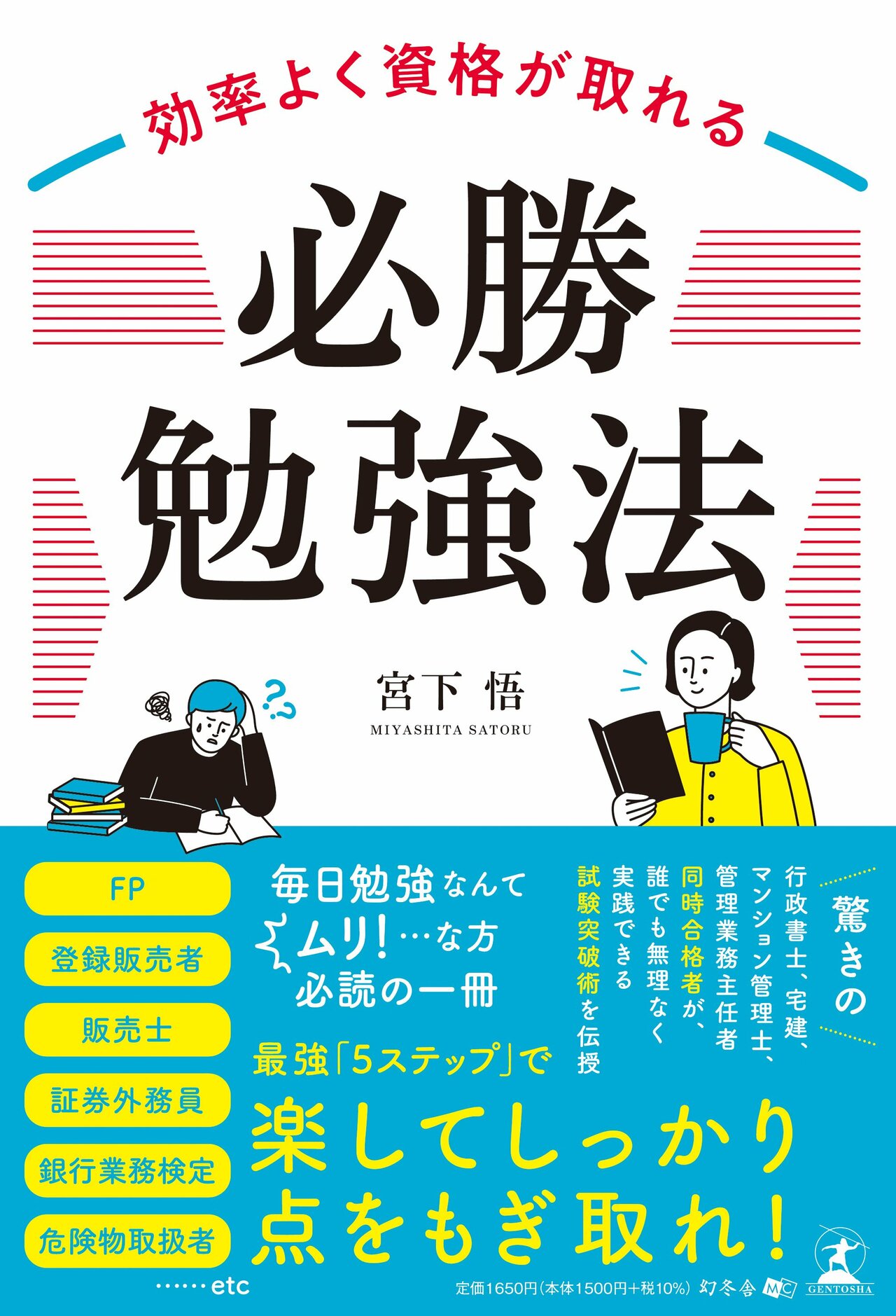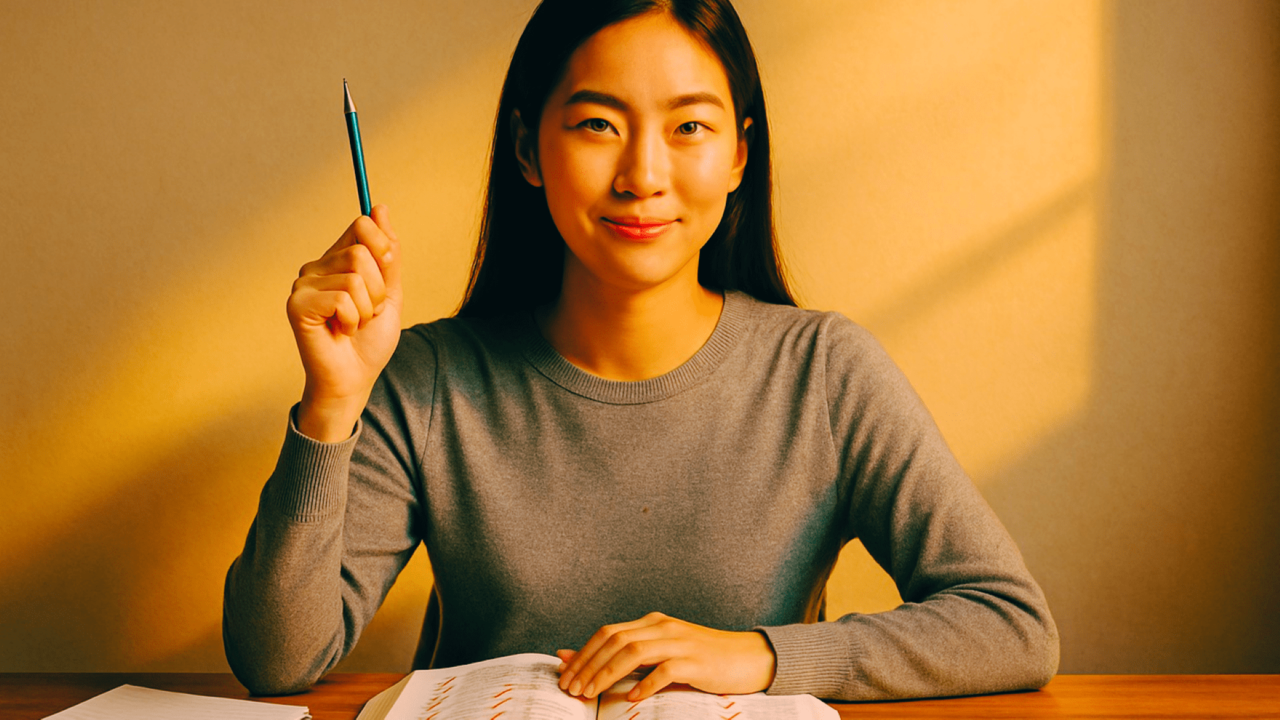【前回の記事を読む】【資格試験】勉強してもすぐ忘れる…合格者がやっていた復習の“方法”と“タイミング”とは?
第1章 「資格試験」に合格するための勉強法とは?
2 合格に必要な「合格力」とは
勉強の定義をしたところで、資格試験において具体的に何を目標とするのかについても考える。
「『合格すること』に決まっているでしょ?」という声が聞こえてきそうであるが、残念ながら、そのような認識ではまだ漠然としている。「『合格すること』とは何か?」というところまで突き詰めて考える必要がある。
資格試験については、四肢ないし五肢択一のマークシート形式のものが多い。本書では基本的に、択一式問題を前提に考えていく。ただし、例えばFPの実技試験や「計算問題」についても、復習を中心とした勉強方法自体に大きな相違はないと考えてよい。
ここで、合格レベルに必要となる具体的な目標は何か。「合格レベルの実力」を、敢えて「合格力」と呼ぶこととする。
その「合格力」とは、
「過去問の選択肢一つひとつを、根拠を持って解答できるだけの実力」
である。
「そんなことできるのか?」という声もあろうし、実際に当日の試験問題の全てを、根拠を持って判断した上で満点を取るのは非現実的である(この点は後述する)。ただ、資格試験において、「誰でも得点できる問題は、必ず落とさずに正解する」ことが、試験合格のために必要である。
試験問題には難易度があり、難しい問題(問題の出し方がこれまでと異なる等)については、正答率も低くなる。資格試験では、この「難易度」を上げ下げすることにより、合格者を一定程度になるよう調整している。やはり、試験の主催者側としては、資格を認定する以上、「一定の品質を保つ」ことが、いわゆる「資格に対する信用」につながるからである。
逆にいえば、他の受験者の正解率が高い問題を間違えてしまう程の実力しか身についていない状況では、合格は覚束ない。その「実力」というのが、先に定義した「過去問の選択肢一つひとつを、根拠を持って解答できるだけの実力」、つまり「合格力」ということになる。
また、試験問題は単純な正誤問題のみでなく、「正しいもの(あるいは、誤っているもの)はいくつあるか」といった問題形式で出題されることがある。このような問題こそ、「受験者が正確な知識を持っているか」が問われており、その人の「合格力」が試される。ここで、根拠を持って正誤判断ができないことには、正解を導き出すことはできない。