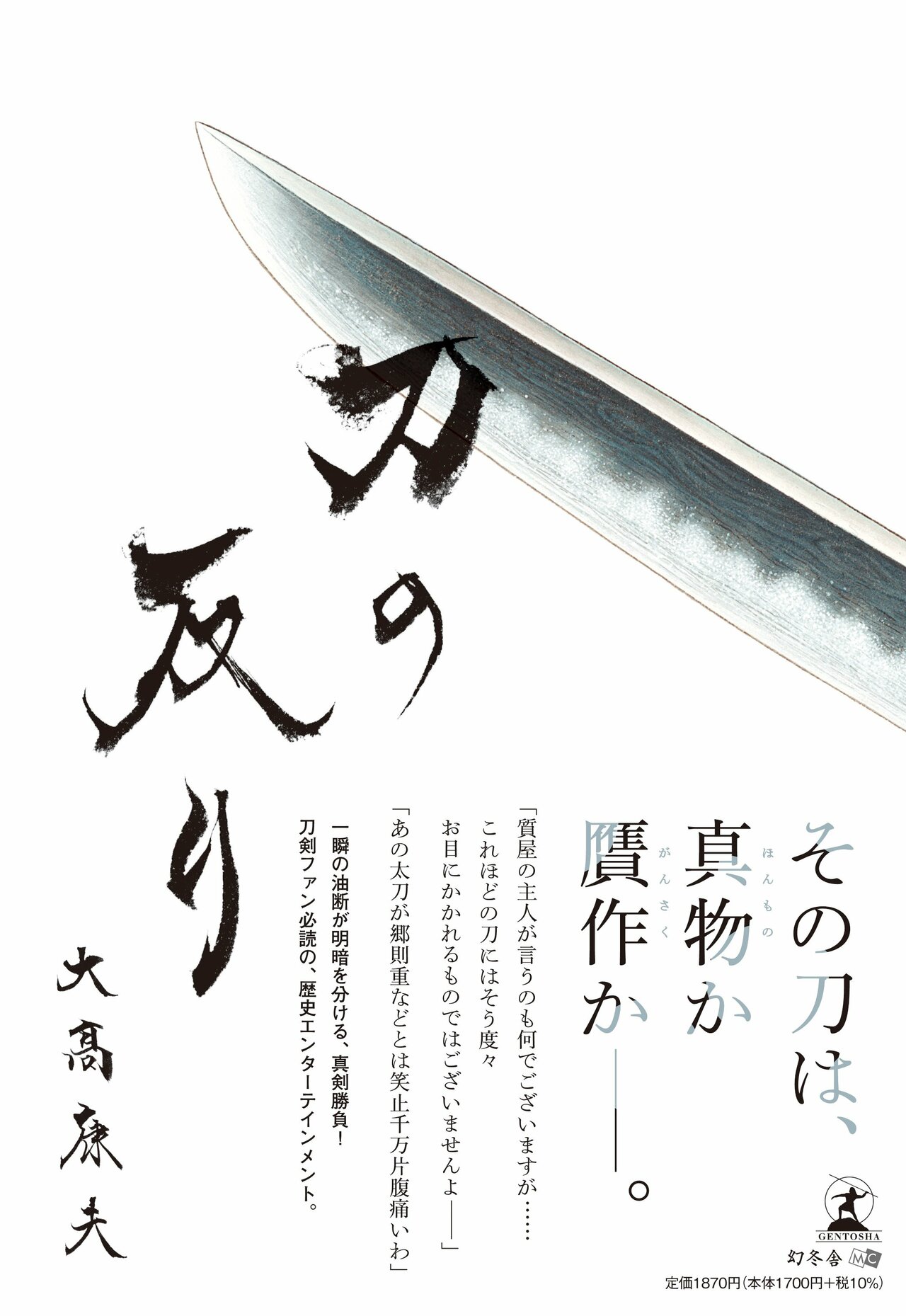【前回の記事を読む】飢えと誇りの狭間に生きる浪人・須田猛之進。江戸の片隅、裏長屋に身を寄せる男が剣に託した一縷の望み
兆し
猛之進は江戸へ出てから己の性格が変わったのではないかと感じていた。国元に居たころは他人の言うことなど聞く耳を持たず、日ごろ誰彼構わず争い事ばかりを繰り返していたような気がする。それが今ではどうだ。長屋を取り仕切る大家だとはいえ、町人の吉兵衛にあのような口の利き方をされようと腹も立たぬではないか。
「わかりました須田様。今日、参りましたのはですね。貴方様のやっとうの腕をお借りしたいというお店(たな)があるのでございます」
吉兵衛は手刀で刀を振り回す仕種をした。
「ふむ……わしの腕とな……」
用心棒でもしなければと思っていた矢先、向こうから話が転がり込んできたようだった。
「はい……玉乃屋というわたくしの知り合いが商いをしておりますお店の用心棒をお引き受けになって頂きたいと思いまして、こうして急ぎやって来た次第でございます」
「ほほう、玉乃屋と言えば両国広小路にある呉服問屋のことかな」
「はいはい、そうですよ。よくご存じでございますな、須田様」
「わしが道場の師範代をしていた頃によく通った道だ。あの辺にはそれがし詳しいのだ」
「さようでございますか。それは話が早うございます。近頃では質(たち)の良くないご浪人様が増えておりまして……あ、貴方様のことではございませんですよ」
吉兵衛は慌てて掌を振ってみせた。透かさず猛之進は……溜めている店賃も払わぬ質の悪い浪人者かの……頭に浮かんだ戯言を言おうとしたのだが止めておいた。狸顔の上に髪に霜を置く大家の吉兵衛にこの手の冗談が通じるとは思えなかったからである。
「昨今、あのあたりも物騒になりましてね。暗くなると歩くことさえままならないようになったのでございますよ」
「それで……わしの腕を必要としておるのはどのような事なのだ」
「はい、実はでございます。玉乃屋に押し込もうとしている連中がいると言うのですよ」
「それは確かなことなのか、吉兵衛」
その話を聞いて猛之進は少し不安になった。
「盗賊一味が多勢で押し込んでこられては、わし一人ではちと厄介ではあるな。それに、そのような話は奉行所に持っていったがよかろう」
「駄目でございますよ。お役人様というのは、いつ押し込んで来るのかわからない連中を待つようなことはいたしませんのです」
吉兵衛は顔の前で打ち消すように大仰に手を振ってみせてから、猛之進の不安を見透かしたように小さな丸い目を無理やり目一杯見開いた。