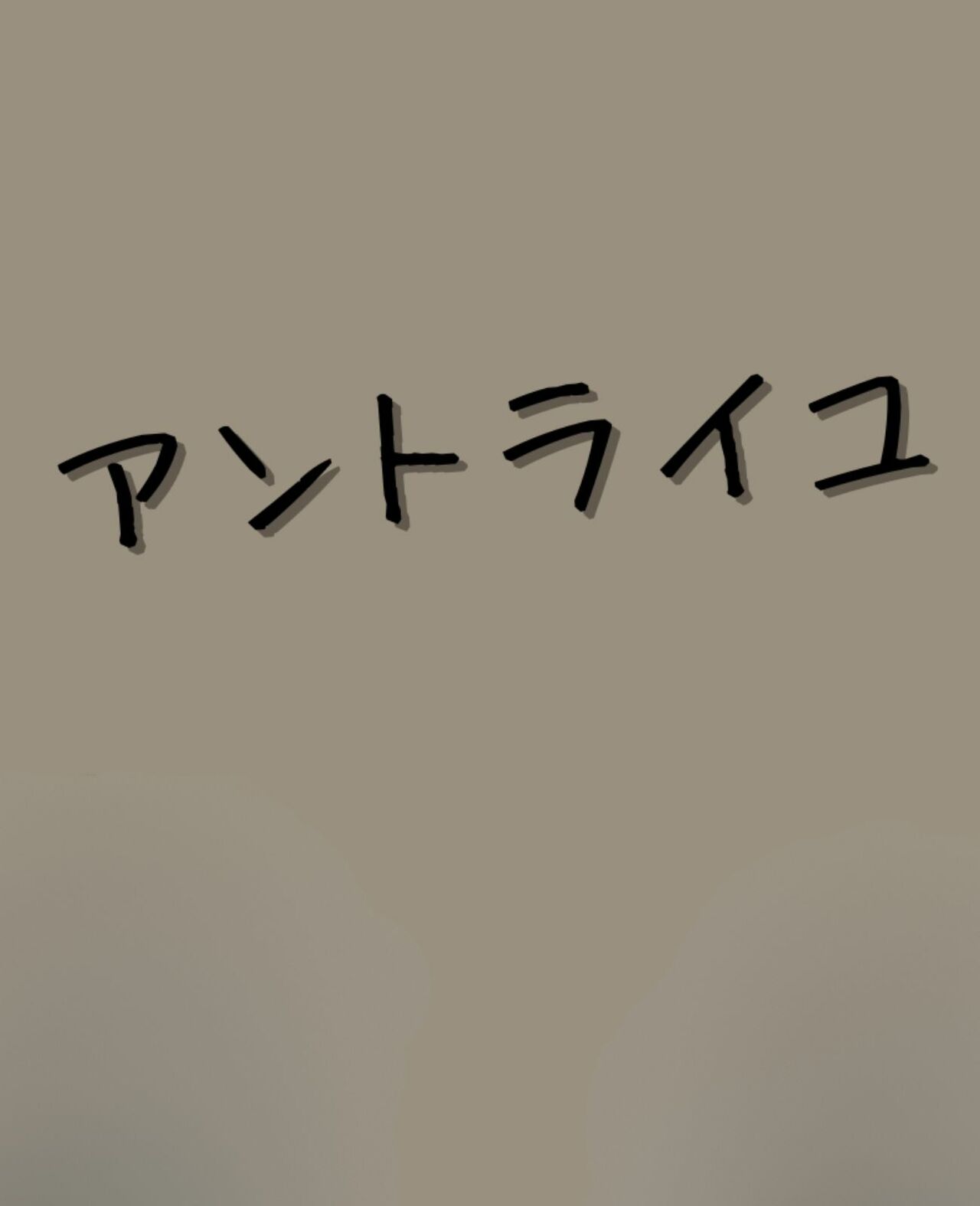3
猫に欠点があるとするならば、小判の価値が分からない所だと思う。でも小判の価値なんて知っていても、持っていなければ意味が無い。猫は小判の価値は分からないけど、知らなくてもフラフラと上手く生きていける。価値が分からないのは私の方かもしれない。
「君はお金好き?」
目の前に現れた黒い猫と睨めっこをしていた。リボンが付いた首輪をしているから誰かの飼い猫なのだろう。毛並みが整えられていて、大切にされているのだと感じる。
「幸せなお家に住んでるんだね」
お金の価値、私より分かってそう。
猫はニャーと一回鳴いた後、家と家の隙間に入って行った。
千春から送られてきたリンクを開くと、マップが表示された。それほど遠くない場所にピンが刺さっている。私は千春がいる居酒屋へ歩みを進めた。
夜の渋谷は照明とネオン管がギラついていて私には眩しすぎる。輝く光の元には人が生きているのだと思うと心が暗い海に沈んでいく。私は小さく惨めな存在なのだと実感した。
男女の二人組がチラリと目に入る。スーツの男性とキレイなオフィスカジュアルを纏った女性。会社帰りのカップルだろう。女性の高そうな香水の匂いが鼻を突く。その甘くて上品で、どこか不快な匂いでさえ、私にとっては羨ましいのだ。
きっと大学を出て、就活をして、入社した会社で出会って月九ドラマの様な恋愛をしているのだろう。私には到底手の届かない人生を妄想して、劣等感に潰されながら彼らを追い越し、少し斜め前を歩いた。
「オフィスラブってやつだ」