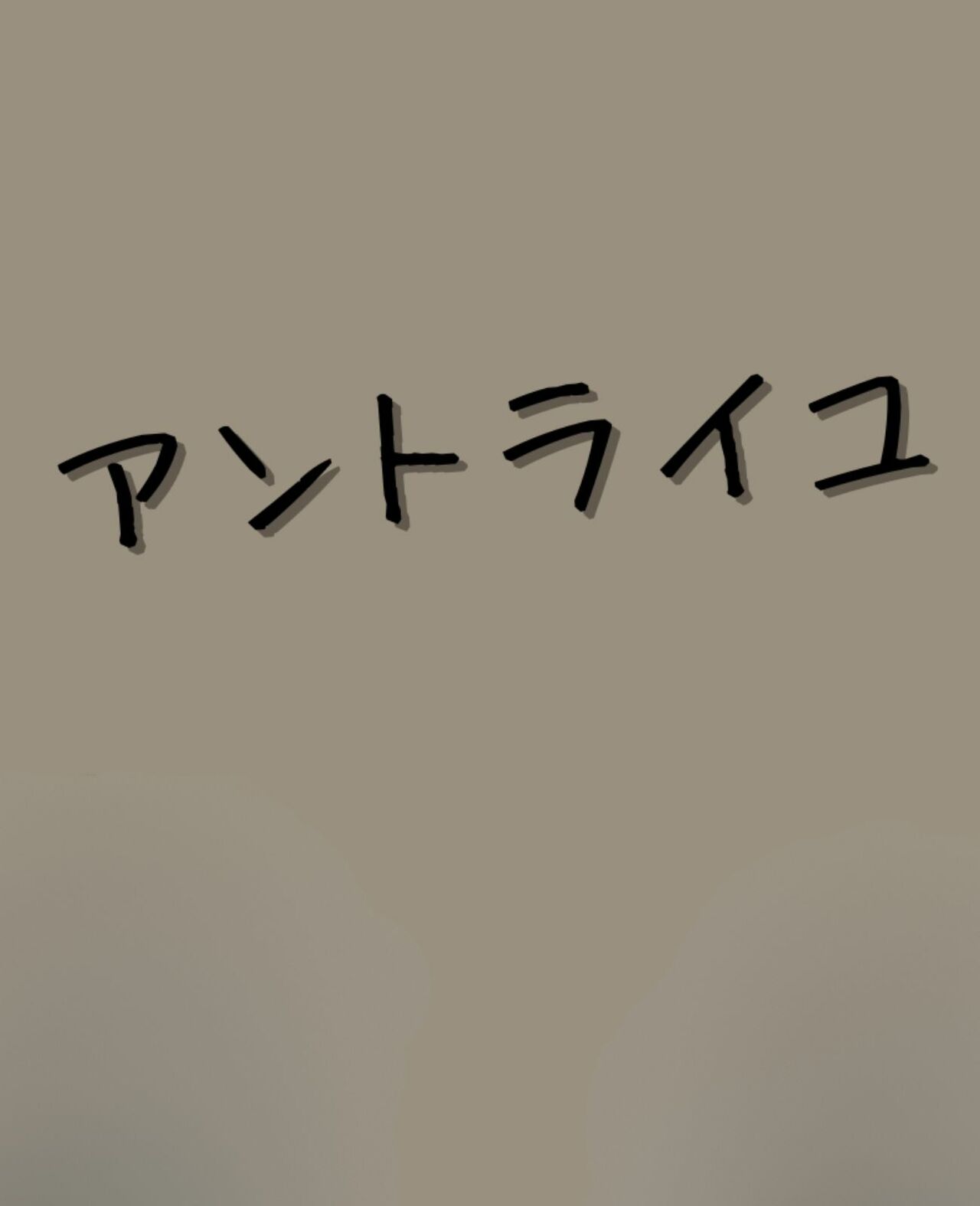【前回の記事を読む】彼はタバコが嫌いだ。お父さんを思い出すから。腕にはタバコを押した痕がいくつかある
アントライユ
3
今度は千春と絡みに行った。肩を抱かれたり、頭を撫でられたりして弄られている。でも千春は嫌な顔一つせず、むしろ喜んでいる様に見えた。二人は普通の父親と息子の様に見えた。私は消え入りそうな声で「良いな」と呟いた自分に驚いた。
しばらく俯いて、スカートの裾をぎゅっと握っては離し、握っては離しを繰り返す。私は彼にこんな顔をさせられない。そう思うと心臓が冷たくなり、止まったような寂しい感覚に陥った。
「行くよ。先輩、ご馳走様でした」
千春の声で先輩に会釈して歩みを始める。
「優しそうな人だね」
千春は頷いてジャージのポケットに手を突っ込んだ。
「良いね。私は、バイト先の人と仲良くないから」
「…あの男、仲良さそうだったけど」
「後藤さんの事? 仲良くないよ」
千春の表情に雲がかかりそうで、私はしばらく口を噤んだ。しばらく、信号と車の軋んだ音しか耳に入らなかった。
「私には、千春しか居ないんだもん」
その呟きは世界の忙しなさに搔き消されて、千春には届かないのだろう。
「千春」
両手を広げてみた。
「は? 何?」
千春は怪訝そうに睨んだ。
「え、頑張ってるって言ってたから、抱き締めてヨシヨシしようと思って」
「ヤだよ」
「そっか」
私は気を取り直して、家に向かって歩き出した。
今夜は少し肌寒い。
「雫」
彼の声に足が止まった。今、凄く優しい声だった。そんな些細なことにも嬉しく感じてしまうなんて、私は意外と幸せ者なのかもしれない。