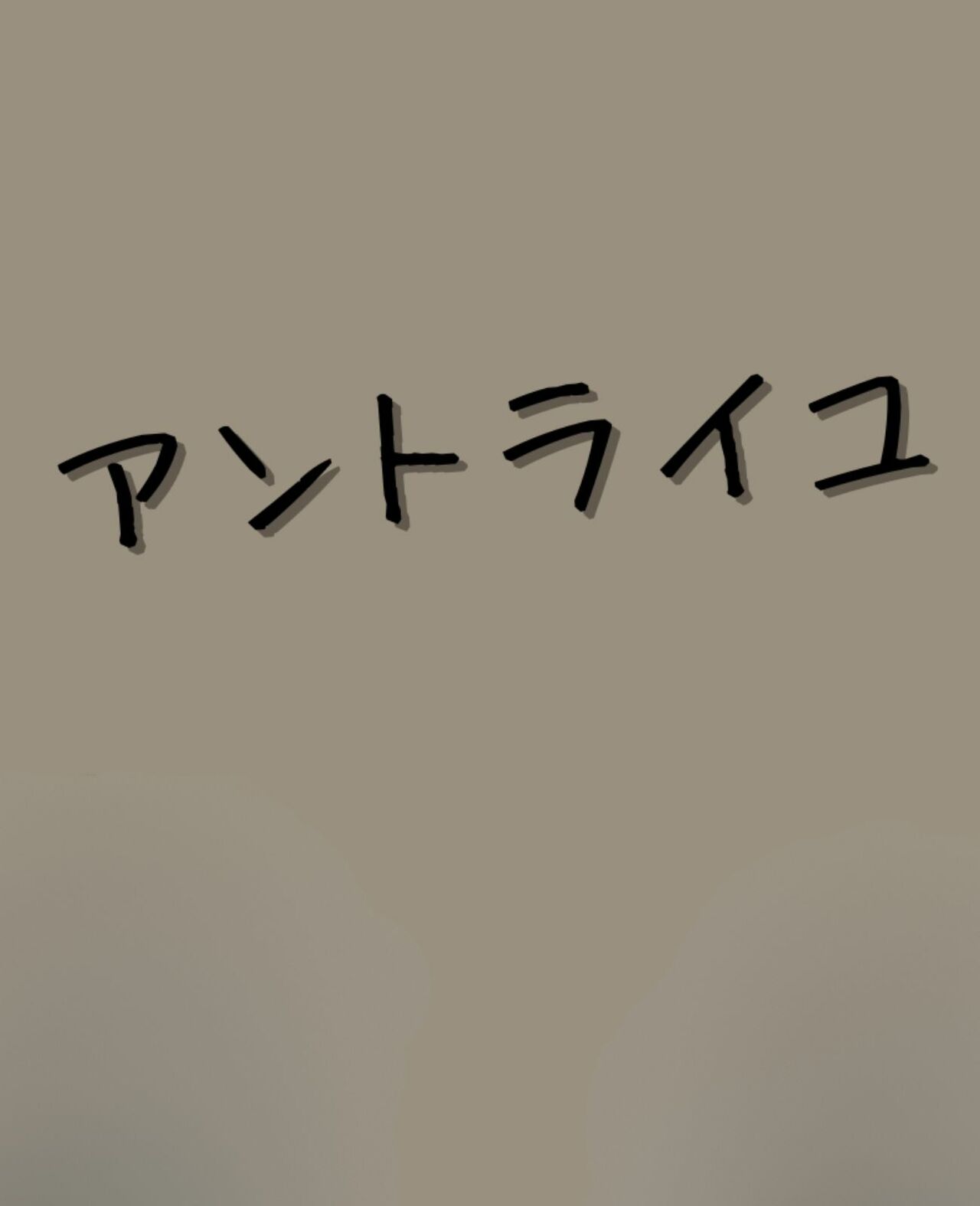「どうしたの」
「いや。生きてて、最悪ではなかったなって」
少し口角を上げる千春は、私の知らない千春だった。今なら言っても良いかな。
「千春。手、繋ぎたい」
千春は黙って手を出した。手を繋いだのなんて、何年ぶりだろう。記憶が曖昧だから、無かったのかもしれない。
差し出された手を軽く握る。すると強い力で握り返された。私はそれに負けないくらいに、手に思いを込めた。彼の脈が伝わって、私の脈のリズムと重なる。その心地良さに脳がフワフワした。
「癌なんだよ」
世界が止まった。瞬きすら忘れてしまった。
「どういうこと? 千春が?」
そう、と言って私から顔を逸らした。私は捲し立てるように続けた。
「どこ?」
「腎臓」
私は思わず手を離してしまった。
「手繋いだだけじゃ移んねぇよ」
「違う。いつから?」
「五年くらい前」
「なんで病院行かないの?」
「偶に行ってた。入院する金ないし、もう良いよ」
「もう良いよって、ふざけてる?」
「マジ」