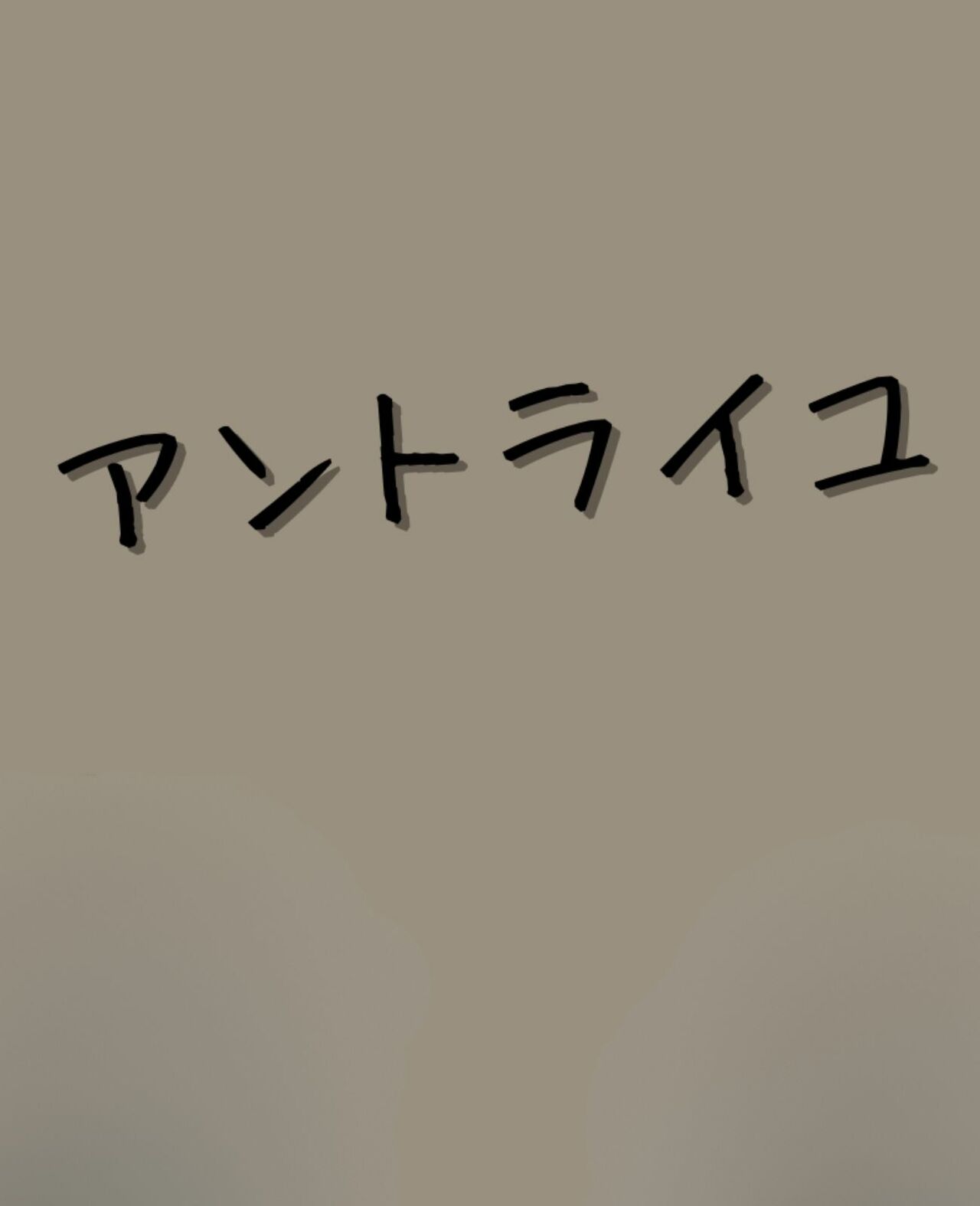千春は私の目をまっすぐ見た。その目は黒いのに鮮やかで、容赦なく私を刺す。
千春のそんな目、知らない。
「何で早く言わないの」
「言ったからって治るわけじゃないだろ」
伽藍堂な頭が体を支配して、上手く動かない。息もロクに吸えなくて、手足が震える。
街の眩しすぎる光が、私たちを照らして離さない。逃げたいのに、逃げられない。
千春が腰を抑えて膝から崩れた。
「救急車呼ぶよ」
「止めてくれ。頼む」
何か知られたくないことでもあるのか、助けを呼ぶことを拒否された。成す術が無くなった私は、膝をつく千春を呆然と見つめるしかなかった。
「ねぇ、今から入院しよう。まだ間に合うよ」
千春は首を縦に振らなかった。眉を顰めて必死に痛みに耐えている姿は、今まで一度も見せなかった。体の内から、心地の悪いモノに蝕まれていく様な感覚に陥り、私は彼のジャージを握った。無惨にも冷え切った空気の中では生きている実感が湧かなくて、彼を抱きしめる。彼の体は冷たくて、急に恐怖を感じた。思わず体を離した。
パーカーの右ポケットに入れてあるスマホが着信を知らせた。慌てて手を突っ込んで、画面を見る。しばらく連絡を取っていなかった、おばあちゃんからだった。
「もしもし」
少しずつ、一歩ずつ、着実に世界は動いていた。
次回更新は8月22日(金)、20時の予定です。
【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…
【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...