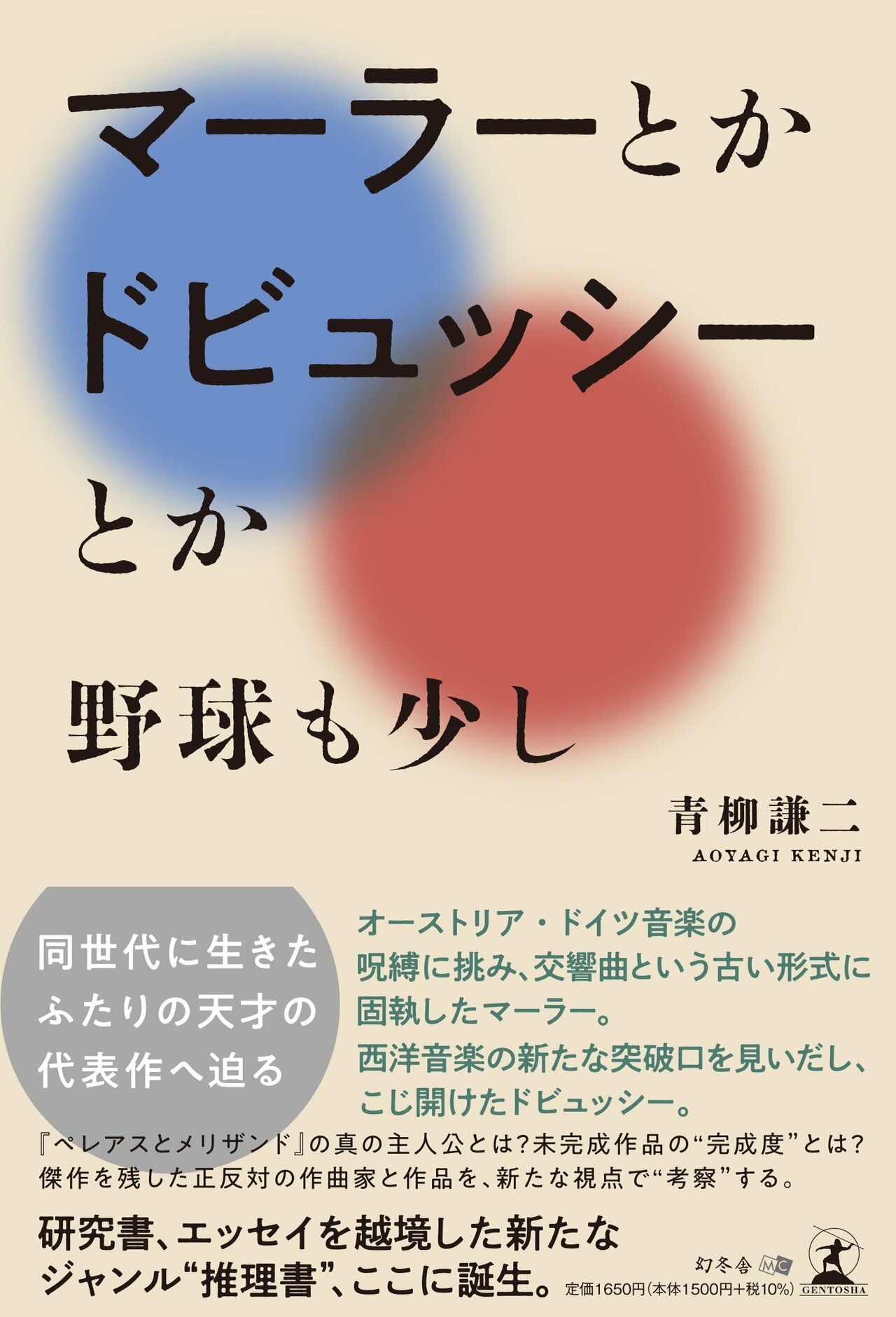構造主義
ここですぐに分節や網のことに触れるのが筋だろうが、少し準備が必要なので今暫くお待ちいただきたい。構造主義的概念に言及したので、構造主義へ少し寄り道をさせていただきたいのだ。
かつては構造主義のまっただ中に、それが過ぎ去って大分時が経つのに我々は現在も未だにポスト構造主義の中にいるようだ。そのポスト構造主義に生きる者として気がかりなことがある。何が構造主義、または何が構造主義的なのか識別がつかない場合があるのだ。
自分が自然に行動しているのに、それを構造主義的と呼ばれても戸惑うばかりだ。自己の判断、意思、行動を構造主義的だとレッテルを貼られるのも、どこか腑に落ちない。自分を俯瞰的に、他者的に眺めることは困難を伴うが、それ以上にどのような思想的背景に自分が置かれ、自分の行動が律せられているかを理解する方が遙かに困難だ。
それに加え、自分の生きてきた時代をこの時点で振り返ると、構造主義のみの時代だったのかどうか、疑問に思う側面もある。
日本で過去の大作曲家の棚卸しのようなことが始まったのも、たとえばシュヴァイツァーのJ・S・バッハに関しこの作曲家を神のように扱っているとの指摘がされたのも、シントラーのベートーヴェン記述が捏造部分多しと最終決定されたのも、考えてみたら一九七〇年代だっただろうか。
時代的には構造主義のど真ん中だ。それでもこれらのことと構造主義との因果関係を証明するものは何もない。構造主義ではなくとも、たとえば実存主義や現象学などの時代でも、これらのことが起こっていたかも知れない。
逆に構造主義的手法を用いて物事を説明しようとすると、ことさら有効なケースがあることも分かった。いきなり大御所を引っ張り出して恐縮だが、レヴィ=ストロースの『悲しき熱帯』などは、構造主義の手法を用いれば、これほどの結果を手に入れられるのか、と驚嘆したものだった。
もちろん読んでいるときは構造主義など一切意識しなかった。あれが構造主義だったのかと気づいたのは読後大分経ってのことだった。気づいた時のショックを忘れられない。人々はその手法や方法に、結果としての出力と同じくらいの驚きを感じたのだ。