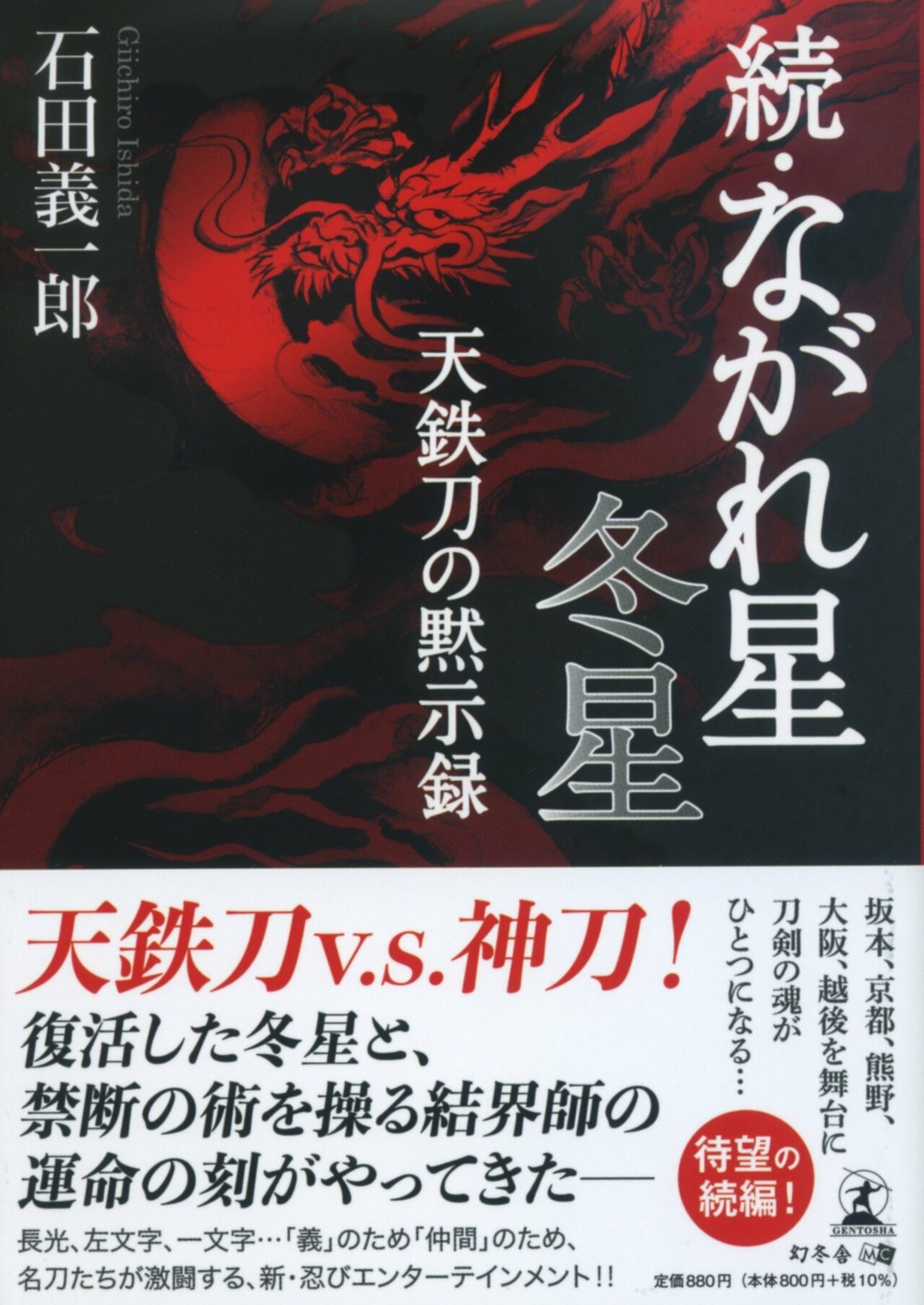女は黒髪の短髪で半纏(はんてん)の上に派手な花衣(はなころも)を重ねている。むき出しの太ももは、異常に盛り上がり筋肉が常人の倍ほどもある。
脛(すね)に深緋色(こきひいろ)の脛巾(はばき)を巻いていた。そして何より大きな目が爛々(らんらん)として、まるで猛禽類(もうきんるい)の大鷲が獲物を捕らえて離さない威圧感を醸(かも)し出していた。
「おまえは何者だ!」
「あたいは蘇摩利(そまり)。まだ錆鴉(さびがらす)の組だけどね。でもこれからまだまだ上を目指すのさ。上からの下知(げち)で来たけど、土産を持って帰らなきゃなんないんだよ。あわよくば敵の首級(しるし)も添えてね」
源三郎は気圧(けお)されながらも、懐(ふところ)にある棒手裏剣(ぼうしゅりけん)に手を伸ばした。
(この女は忍びの者だな。そして……強い)
瞬時に女の〝気〟からすべてを読み取った。
「おまえ山伏(やまぶし)ではないな。山伏は鎖帷子(くさりかたびら)を身につけはしないからな。棒手裏剣なんぞ出しても無駄だぞ。あたいはこの弩(いしゆみ)で的を外(はず)したことは一度もないんだよ」
女の左手甲には小型の弓矢が装着されており、背中に無数の鉄製の矢を背負っていた。
「おい爺(じい)、おまえ軒猿(のきざる)の毘沙門衆(びしゃもんしゅう)の者か?」
「わしは蓮華衆(れんげしゅう)じゃ!」
「れ、蓮華衆とは? 笑止! そんな下っ端(ぱ)とは思わなかったぞ。こんな山奥まで来て三下(さんした)の相手とはやれやれだ。まあいい本題に入るわ。おまえたちはいったい何を運んでいる!」
源三郎はちらりと義近をみた。義近はやっと腰がすわり木の陰に隠れ、こちらを窺(うかが)っている。