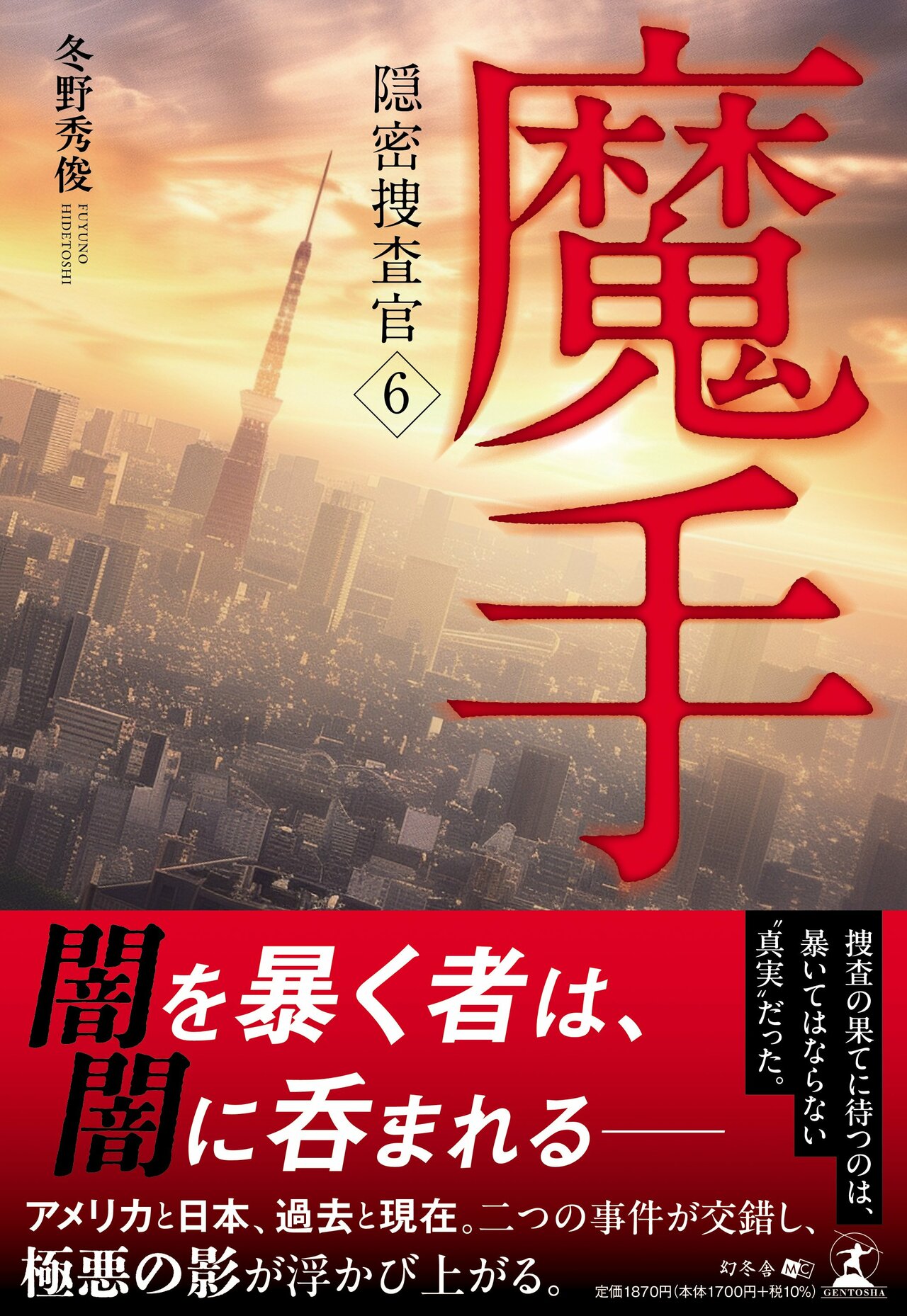【前回の記事を読む】アメリカ・オレゴン州で不審な死を遂げたのは二人の日本人だった。全く関係性の無い二人に一体何が起こったのか
(一)
清一は、証拠が劣化してしまったことで、捜査が進まなくなった苦い経験を何度もしていた。それを防ぐためには、捜査の初期段階で思い込みをなくし、物証を含めきちんと検証しておくことが必要だと分かっていた。
薄暗い店内では、清一たちのテーブルだけに息詰まるような空気が漂っていた。他のテーブルでは談笑が店内に響き渡り、フォークとナイフの音は、さながら効果音のようだった。
木をベースにして造られた建物は、床、階段、天井、どれをとっても客を和ませるもので、建物の中に居ながらにして自然が満喫できた。ここの窓から見える緑はわずかだったが、全体的にみると人工物の方が緑の中で息づいていた。
清一が室内の骨組みに目を凝らしていると、突然若い刑事が立ち上がり、清一も促した。そして、会計、厨房の前を通り奥へと急いだ。
清一が立ち上がって若手刑事の後に続くと、すぐに正面入口の方が慌ただしくなった。次の瞬間、一発の銃声が響き渡り数人の男がなだれ込んできた。そして、その中の二人が、清一たちの後を追うように店内の奥へ向かって駆け出した。
再び一発の銃声が鳴り、吹き抜けになっている天井のランプが粉々に砕け散った。逃げ遅れたスージーとFBIの男は、反撃することはできたが被害者が出ることを恐れ、手出しできずにいた。そして、ここは荒くれ者の行動を見て犠牲者が出ないようなら我慢すべきだと、腹(はら)を括(くく)った。
清一は片手で小枝を払いながら、若手刑事の後を追った。垣根を飛び越え、広葉樹を潜り抜けたところにある駐車場へ出た。しかし、荒くれ者は執拗だった。車に乗り込み急発進させるや金属音がたて続けに鳴った。追いかけてきた奴等のなりふり構わぬ発砲だった。
若手刑事は、坂道を下り本線に合流した。
「大利家戸さん、驚いたでしょう。でも、もう大丈夫ですよ」若手刑事が、肩を大きく揺らした後で言った。
「二人は、無事だろうか」
この事態の分析よりもスージーの安否が気になった。
「多分、大丈夫です。偶(たま)にいるんです。客から金品を巻き上げてとんずらする奴が」
「僕たちを追いかけてきて、発砲したのは」
「それは、逃げるのが早かったので癪(しゃく)に障ったからでしょう。それと、見せしめ。他の客に逃げれば容赦しないことを見せておきたかったんでしょう」
若手刑事は、いちいち気にしていたらきりがないと言わんばかりだった。発砲したのはあくまで威嚇(いかく)、パフォーマンスだというのだ。
「少しの間ドライブしたら戻ってみましょう。奴等だって長居は禁物、捕まりたくないはずですから」
「そうなんだ」
清一は、銃社会アメリカに思いを巡らせていた。わが身は自分で守るというアメリカでは、一見平穏を保っているようにみえるが、しばしば銃による悲劇を生むという歴史をくり返してきた。