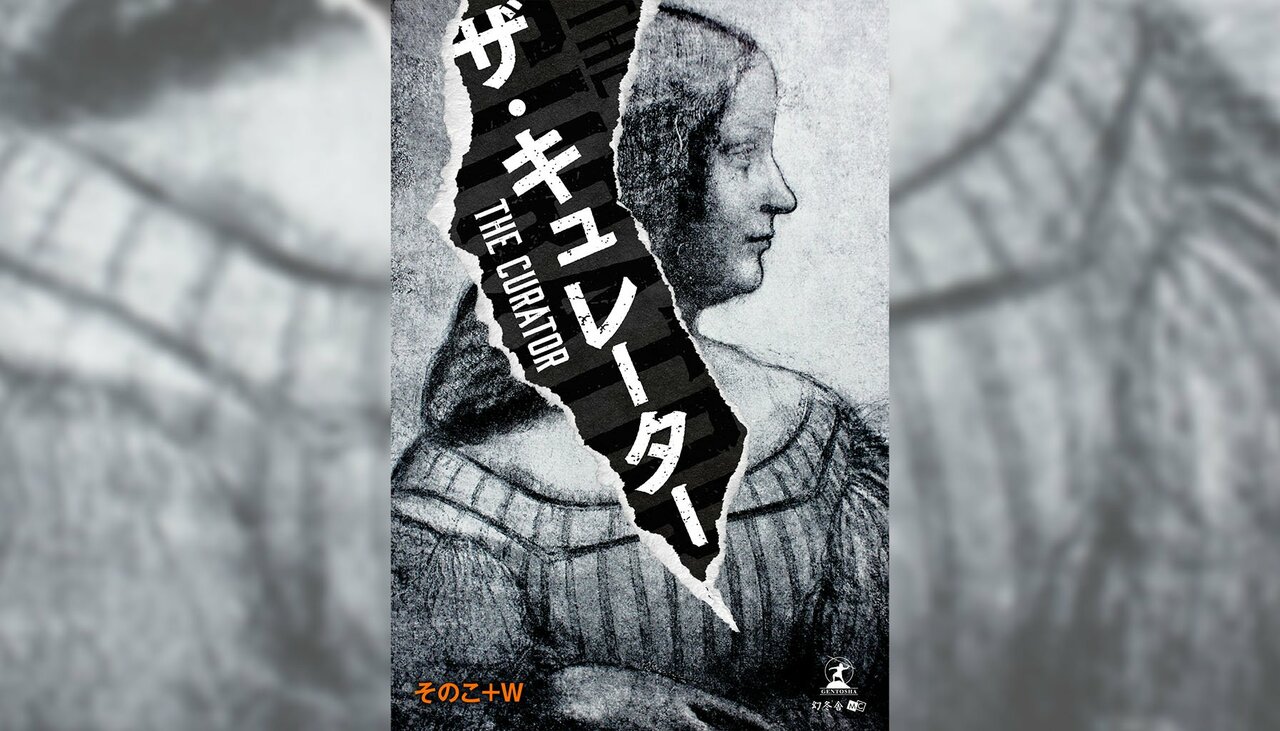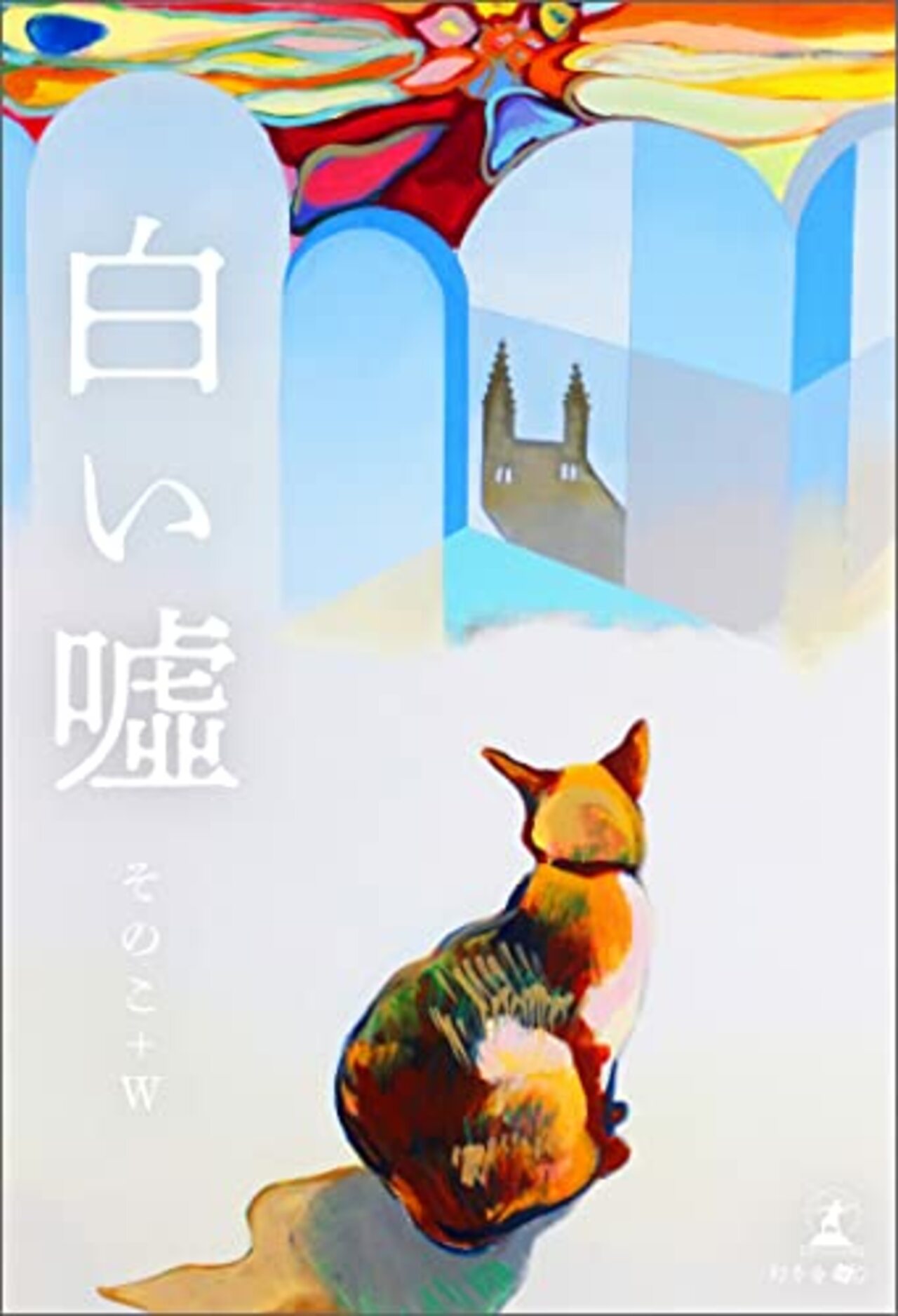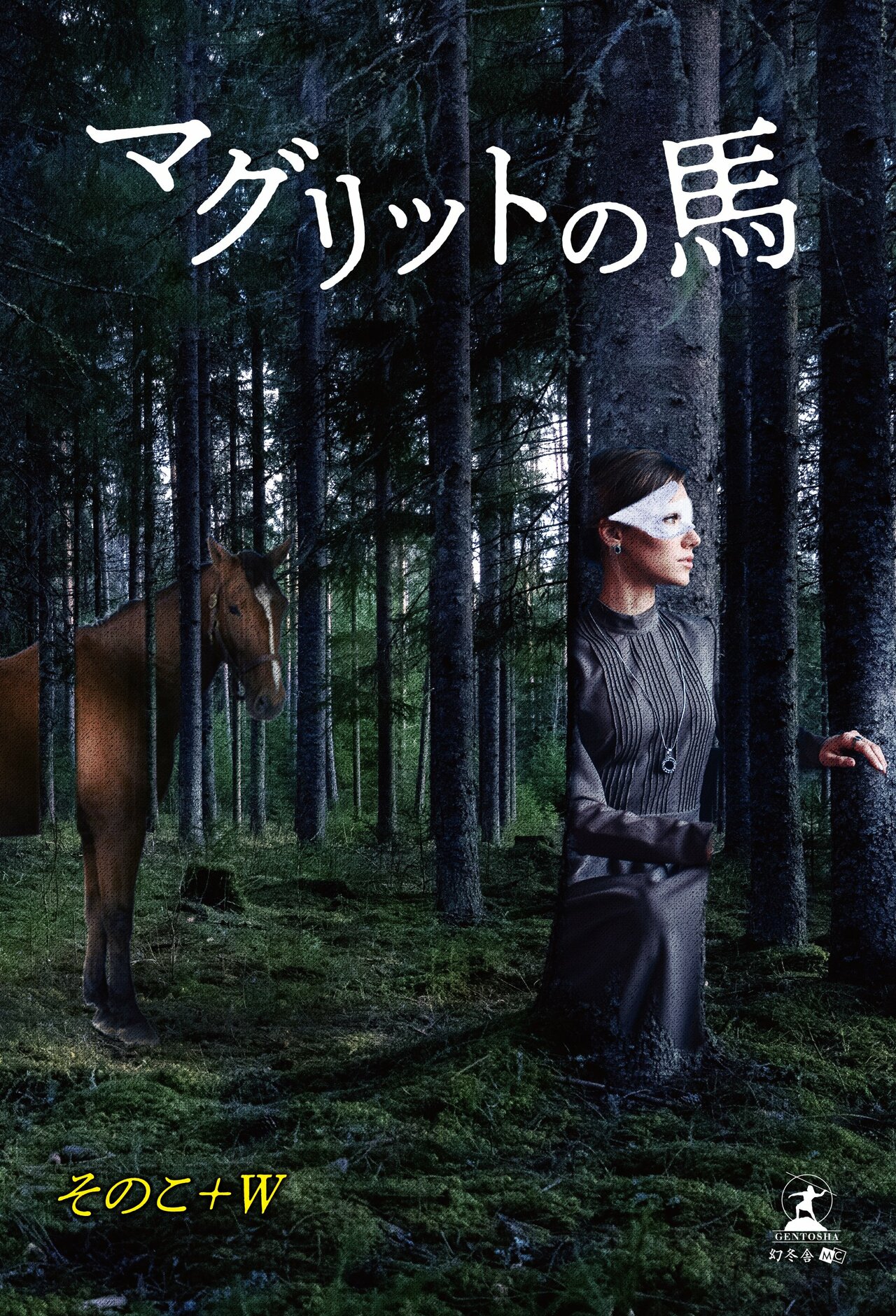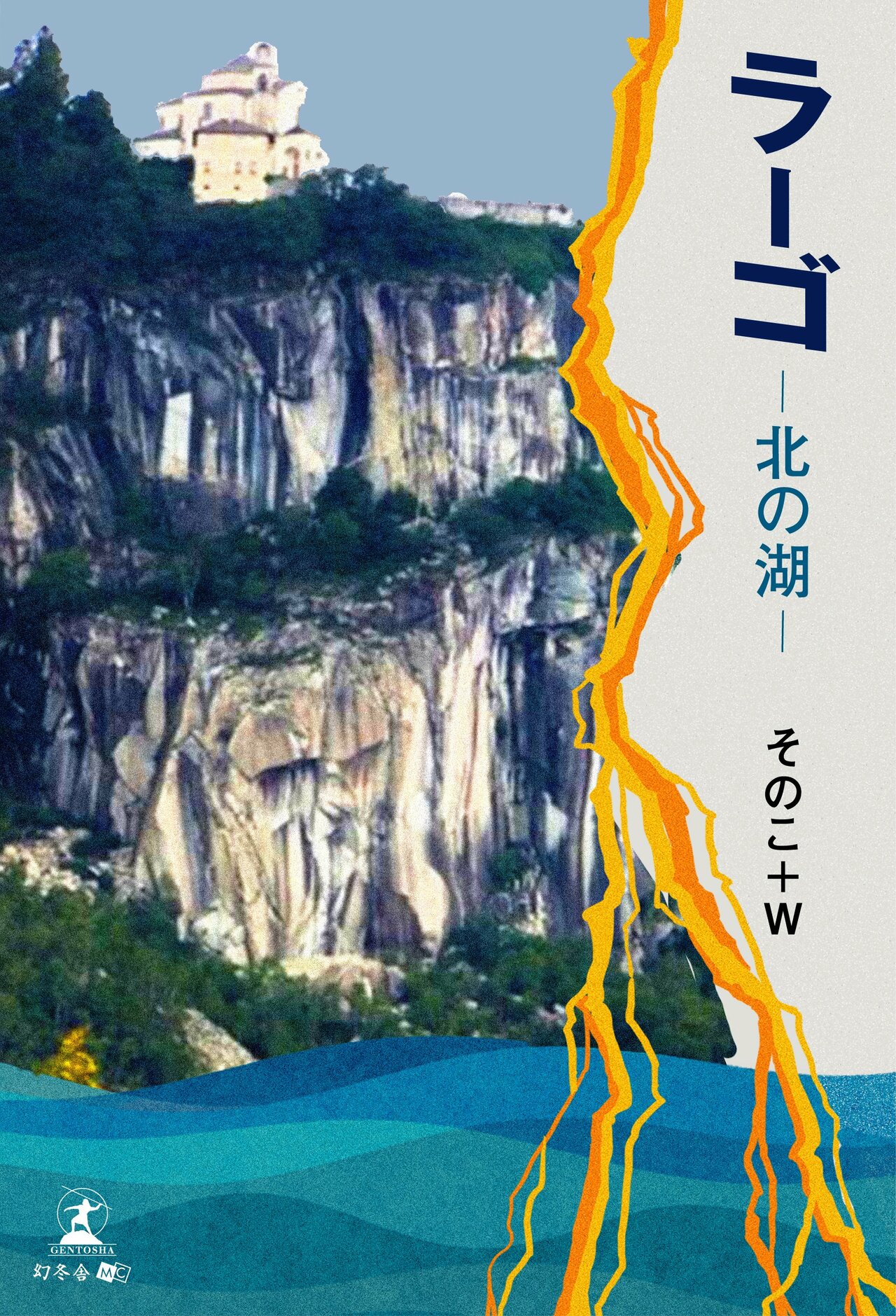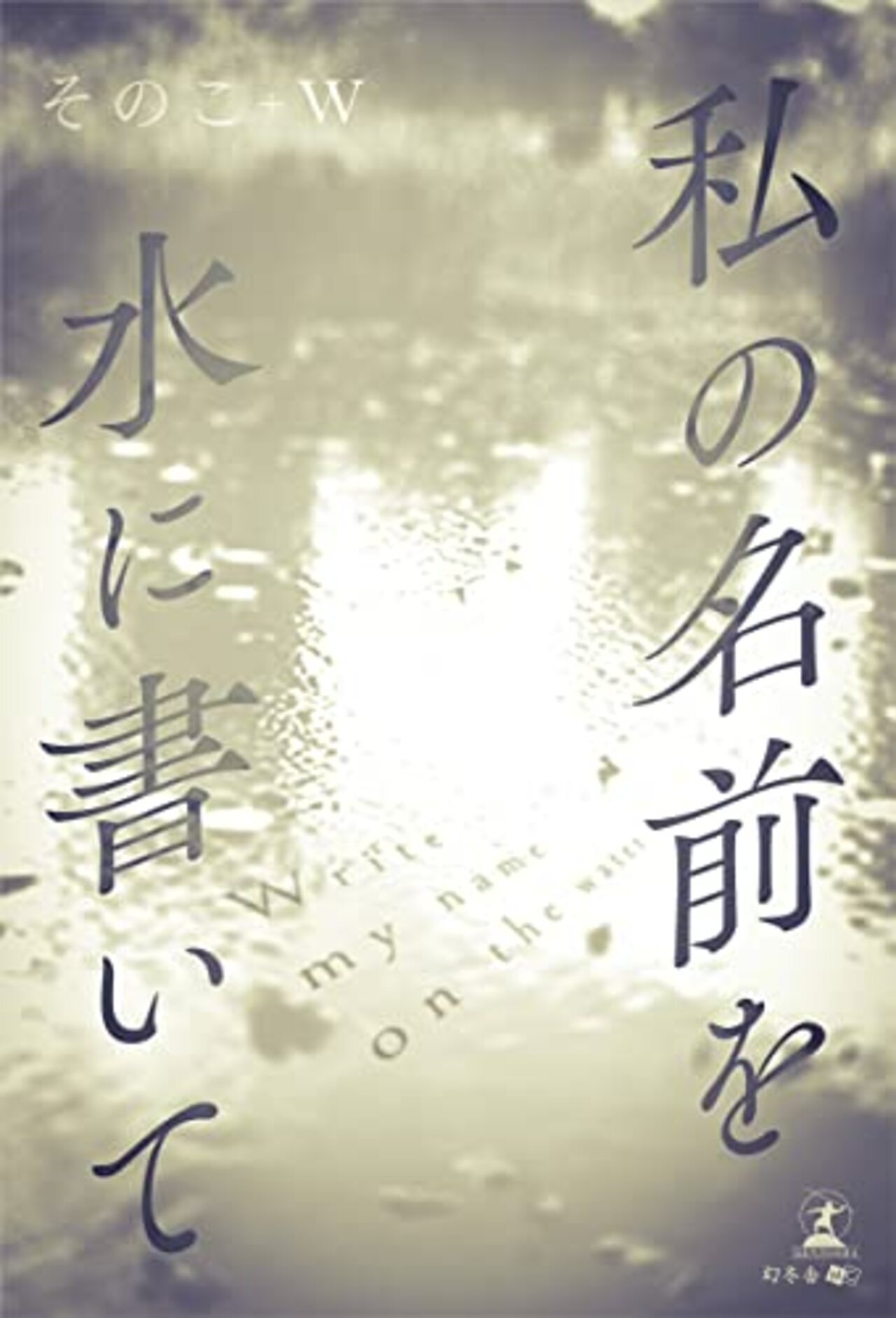【前回の記事を読む】女は「トイレに行きたくなった、ちょっと荷物を見ていて」と有無を言わさず彼女の胸に押し付けて、ホールの奥に慌ただしく姿を消した。
第一章
花の聖母大聖堂
九月六日
忠司はそれも理屈に合っていると思い、同意した。彼自身イタリアは初めてだ。
花の聖母大聖堂(ドゥオーモ)の入り口は九月に入っても観光客で長蛇の列だった。
この聖堂が〝花の聖母〟と名付けられたのは当時のイタリアばかりかヨーロッパの経済、文化、芸術がフィレンツェに集中し、まさに大輪の花のような存在だったからだろう。今でも彼らはフィレンツェ人を〝花の町の人(フィオレンティーノ)〟と呼ぶ。
十五世紀初頭から半ばに掛けて建てられた大聖堂は、コンペティションとして当時のライバル建築家たち、ロレンツォ・ギベルティとブルネッレスキの間で争われ、ブルネッレスキが勝って受注したいわくつきの建物である。
巨大な八角形のクーポラは、当時の四角柱と三角屋根から成り立つゴシック建築から見て、画期的なプランだった。しかもブルネッレスキのクーポラは建築の初期段階に一度崩落している。
その落胆が原因なのか、ブルネッレスキは体調を崩し、その間ギベルティが仕事を続けかけたが、到底手に負えないとブルネッレスキに投げ返したという。
イタリアが丸いクーポラを手に入れるまで、更に半世紀を待つことになる。建築家ブラマンテの設計によるヴァチカン市国のサン・ピエトロ大聖堂のクーポラは、十六世紀初頭にようやくその全容を見せることになるのだ。
三十分待たされてようやく聖堂の中に入った。まず色彩豊かな大理石の床に目を奪われた。彼らはそれらの大理石の産地を詳しく知らなかったが、白大理石はリグリア海岸のカッラーラやピエトラサンタから来る。色の付いた大理石はルネッサンス当時はプラート、シエナから運ばれたが、現代ではこれらの石は採りつくし、中東など外国からの輸入に頼っている。
二人は大聖堂を出て、聖堂脇のプロト・ルネッサンス(前期ルネッサンス)の天才、ジオットが設計したというジオットの塔(鐘楼)に登った。塔の狭い階段を巡って上がって行く。通路は狭く、息が弾んだ。ようやくてっぺんに登るとフィレンツェのパノラマが一望のもとに見下ろせた。家々の赤い屋根が目に入る。
「案外小さな町なのね」