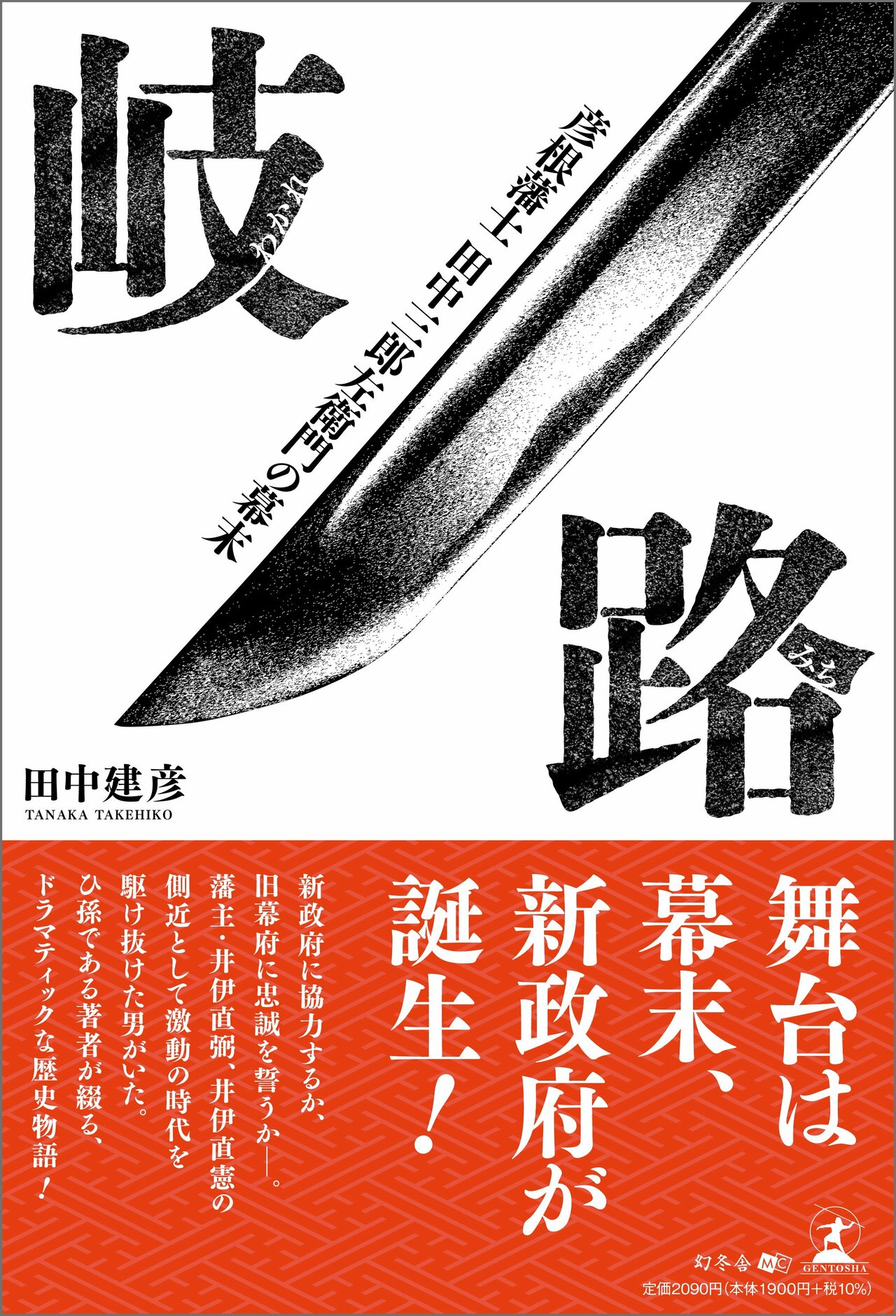小田井宿に差し掛かると江戸方面から「えっほー、えっほー」と威勢のいい掛け声を上げながら、駕篭が進んできた。
その前後を数人の武士が取り囲むように足早に歩いている。徳三郎は道端によってその駕篭が通り過ぎるのを待った。
きっと名のある高級武士であろうと眺めていたが、立派な漆塗りの駕篭の扉は締め切られていて中が見えない。
好奇心むき出しの田舎侍の姿だろうと、我に返って少し恥ずかしい思いをしながら見送っていると、急に胸のあたりに痒さを覚えた。
歩き続けて少し汗ばんでいたのである。半ば無意識にその個所を掻こうと手を胸の中に差し人れた時、彼の手が何か異様なものに触れた。荒ててそれをつかみあげると、それは他人の手だった。
「痛てて……」
その手の主が叫びながら強く引っ張ったので、徳三郎は驚いてその手を放した。途端にその手の主は力いっぱい引っ張った自らの勢いで、後ろに崩れ落ちるように倒れてしまった。
「この野郎!」
気付いた芳蔵が駆け寄ってくると、その男の横っ面を殴りつけ、腕をねじ上げた。足を止めて様子を見ている旅人たちの数が次第に増えてきた。
掏摸(すり)を捕まえはしたものの芳蔵もどうしてよいかにわかに判断がつかぬような当惑顔で、居もしない役人の姿を探してきょろきょろしている。
まだ、宿(しゅく)の入り口に差し掛かったばかりで、本陣は一町ほど先にあり、町の人間もあたりには見えない。
何事が起こったのかわからず、当の徳三郎は一瞬ぽかんとしていたが、ようやく事情が呑み込めてきた。