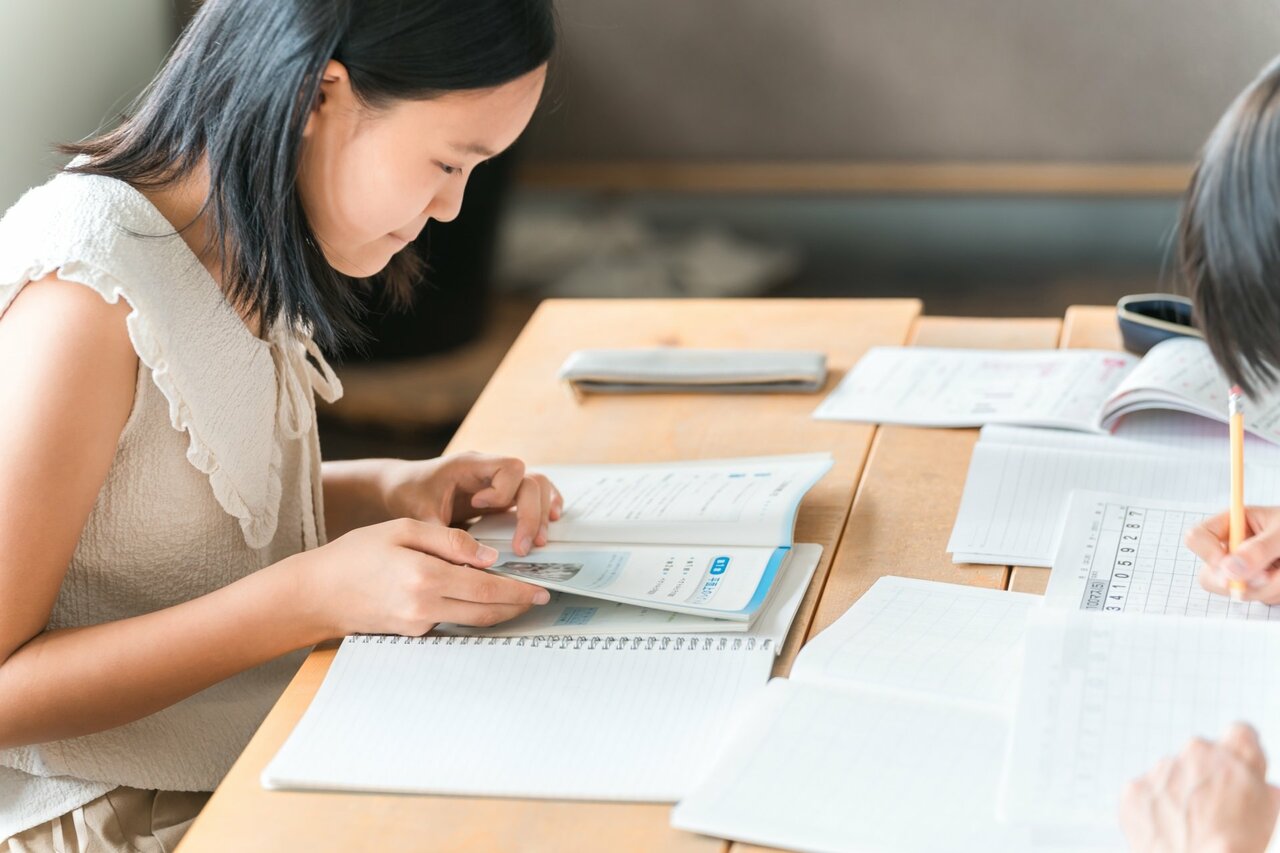③ 発表内容でボーナスがつく
しかも、発表には内容によって『ボーナス点』がつくのです。良い発表内容だと、「分かりやすい」「例がいいし、聞きやすい」などのボーナスを子どもがつけて発表の点数をあげます。だから子どもは発表の仕方も聞き方も工夫し、相互評価の視点も高まっていきます。
ボーナスをつける(査定する)のは子どもですから、他の児童の話をしっかり聞いていないと査定ができません。しかも査定の意見を言った子には、さらに私が評価して『査定の観点からボーナスがつく』のです。
例えば「今の発表については、○年生のときの●●のことと結びつけたことを褒めましたね。Aくんもそれをよく覚えていて褒めたので勉強の仕方が良い。だからAくんにも先生からボーナスです」というようにおこないます。
④ どの子も伸びる権利がある
このような授業ですから、ときには決められた算数の時間だけでは終わらずに次の時間にずれ込むこともありました。でも考えを発表できることは子どもにとっても快感らしく、
「次の時間も算数を続けます」
という指示にも嫌がらず、
「やったあ~」
と言ってもらえることが多かったのはこの勉強法が子どもにもあっていたのでしょう。体育や理科の実験、図工などの時は次の時間まで続けられないことが多かったのですが、時間割通りにしなくても済むというのは小学校の学級担任だからこそできたことなのだろうと思います。
「これでは授業が進まないのではないか」という質問もよく受けました。でもよく考えよく聞くという学習の姿が連続していますので、放課後に残して練習問題をしたり無理にドリルの宿題を出したりしないでも授業時間だけで分かってしまう子が多く授業の遅れはほとんどありませんでした。
“どの子も伸びる権利がある”ということを実行に移すための方法としてこれが最善とは思いませんが、授業時間にどの子もが自分の力を発揮し尽くしている姿を見て、少しは実践できたのではないかと思っています。