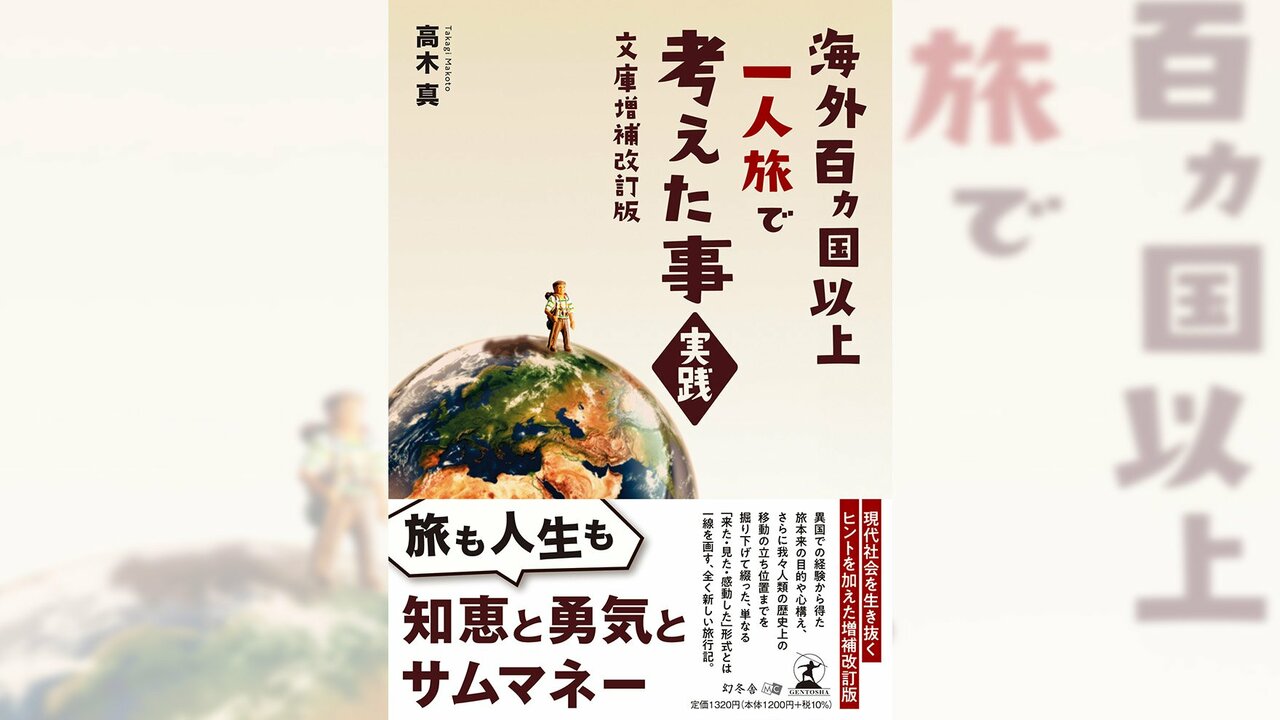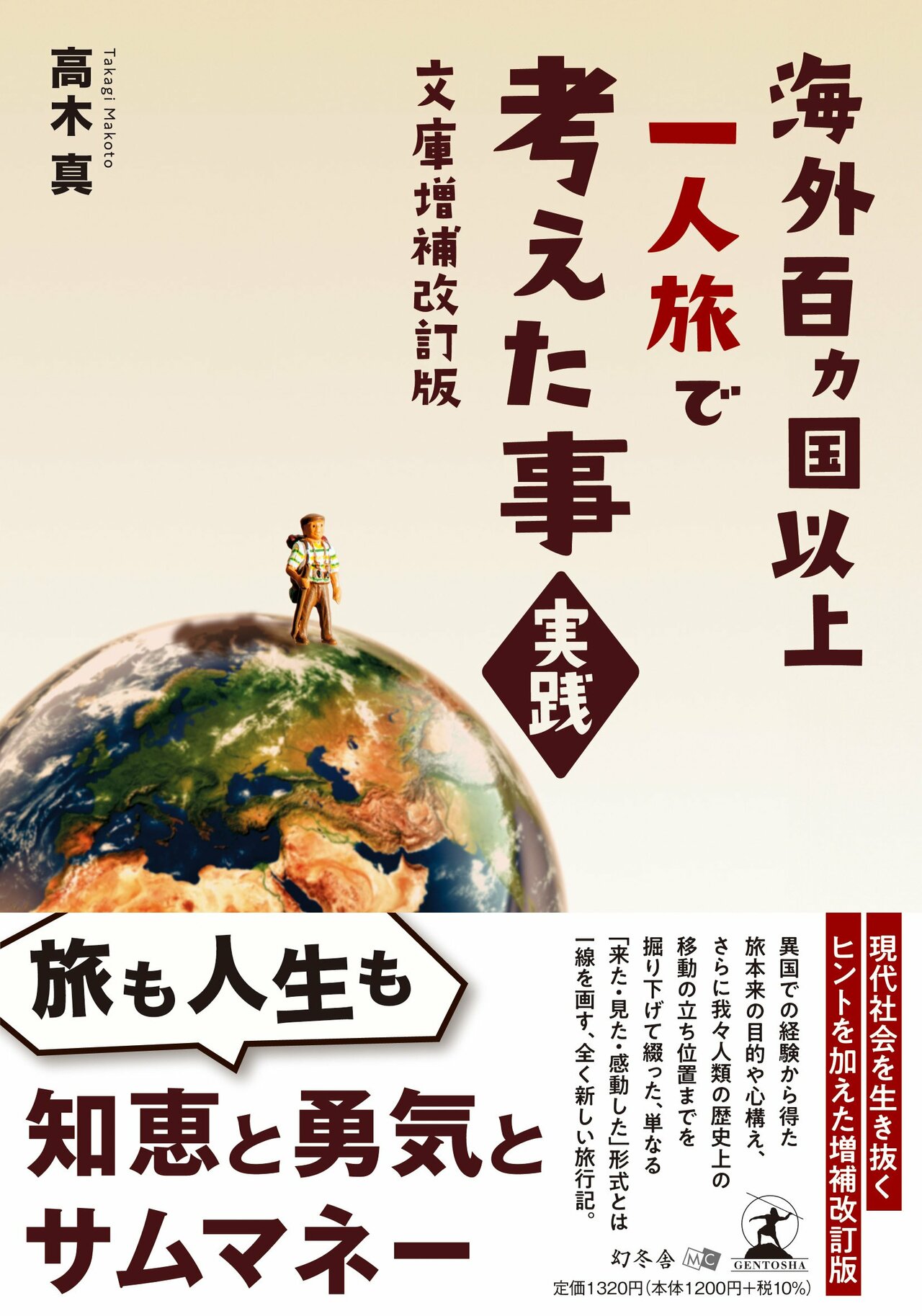【前回記事を読む】マラッカ・ホイアン・アユタヤ──世界遺産に残る日本人町の記憶と、鎖国以前に海外で活躍した戦国商人たちの真実
私の国内外の旅と旅とは何かについて
移民政策としての日本人の海外移住
明治期には、日本の植民地化を防ぎ西洋化するため・富国強兵政策のため、多くの日本人が西欧へ西洋の文化技術を学ぶため留学生(軍人・文人多数いるが、有名な人として、軍医・作家としての森鷗外、夏目漱石ら)として海を渡ったが、
それ以外にも、国の移民政策として、多くの日本人が、海外に船で渡った(富国強兵策といえば、明治期西洋のロマ(ジプシー)のような政府の支配・コントロールに属さない自由民の、サンカ(山窩)・山伏・虚無僧・無宿人のような人々は、
定住させられ戸籍に組み入れられ、中央集権下の富国強兵(兵役・課税のため)を担う国民に組み入れられた。
この事はあまり知られていない。せいぜい山伏が明治期神仏分離令で解体された、数が減った、くらいしか注意・認識されていない)。
明治期以降、日本の貧しい農漁山村の余剰人口・食扶持減らし対策として、北海道開拓と共に、海外移民・出稼ぎ政策が取られた(当時の富国強兵策で、人口確保・兵員確保の観点からは、矛盾するように思われるが、
まだ産業革命・工業化が遅れていたため新産業への人口吸収が出来なかったため、とりあえず余剰人員を移民させたと思われる)。
ハワイ(初回は既に幕末部分開国の時に計画されていたようである)・南太平洋・東南アジア・南アメリカ(ペルー・ブラジル等)・北アメリカ(後年、アメリカで太平洋戦争中日系人の不平等・差別的処遇が問題となった)への移民・出稼ぎが盛んに行われた。
また昭和前期、日本は、清朝最後の皇帝だった溥儀を傀儡皇帝として擁立し、清朝の故郷に満州国を作り、国策として国内失業者・不況対策としての満蒙開拓団が組織され、多くの日本人が、開拓民として、大陸に渡った。
このような明治以降の移民政策のため、移民した世界各地に日系移民の子孫がいるし、中国では引き揚げ時に日本に帰国出来ず取り残された中国残留孤児が問題となった。