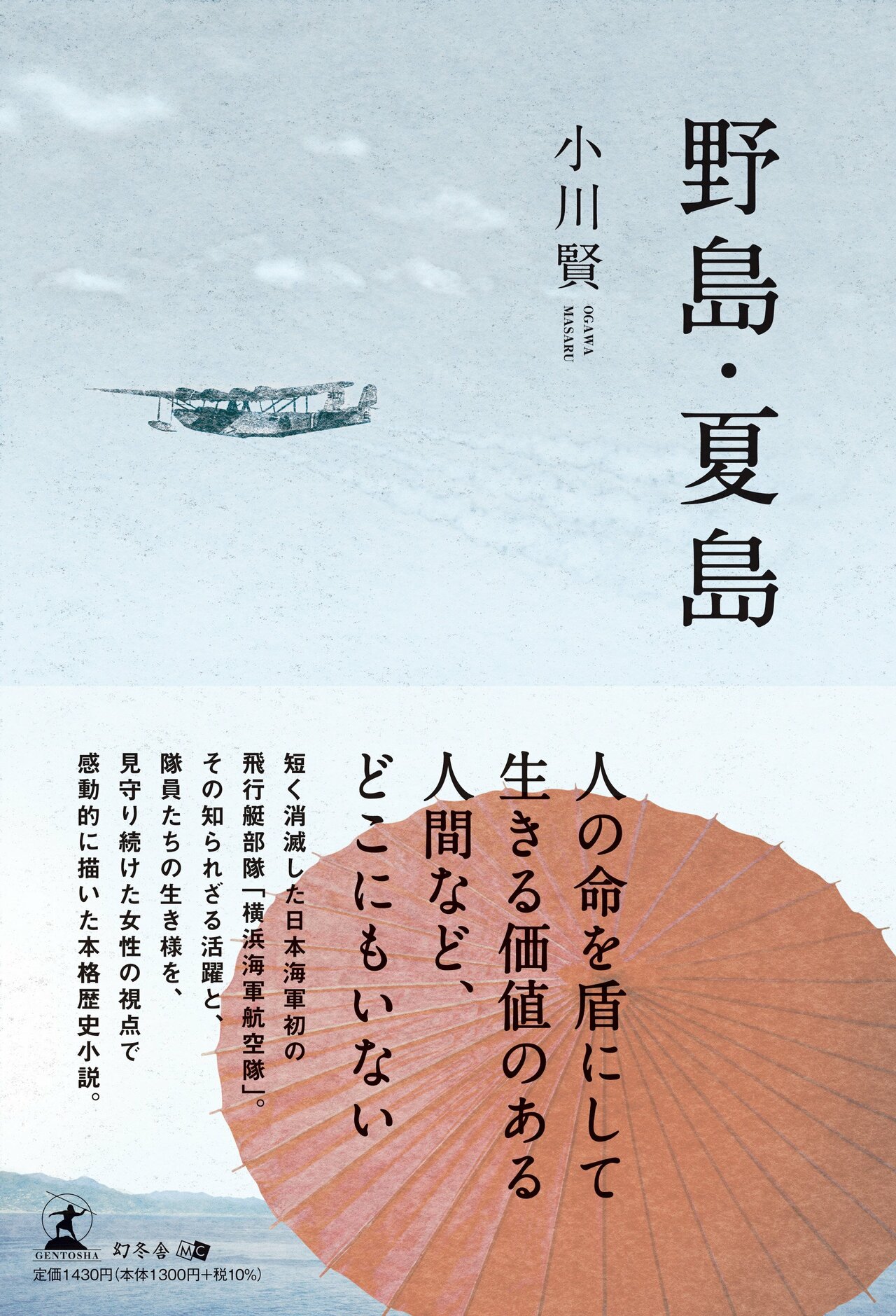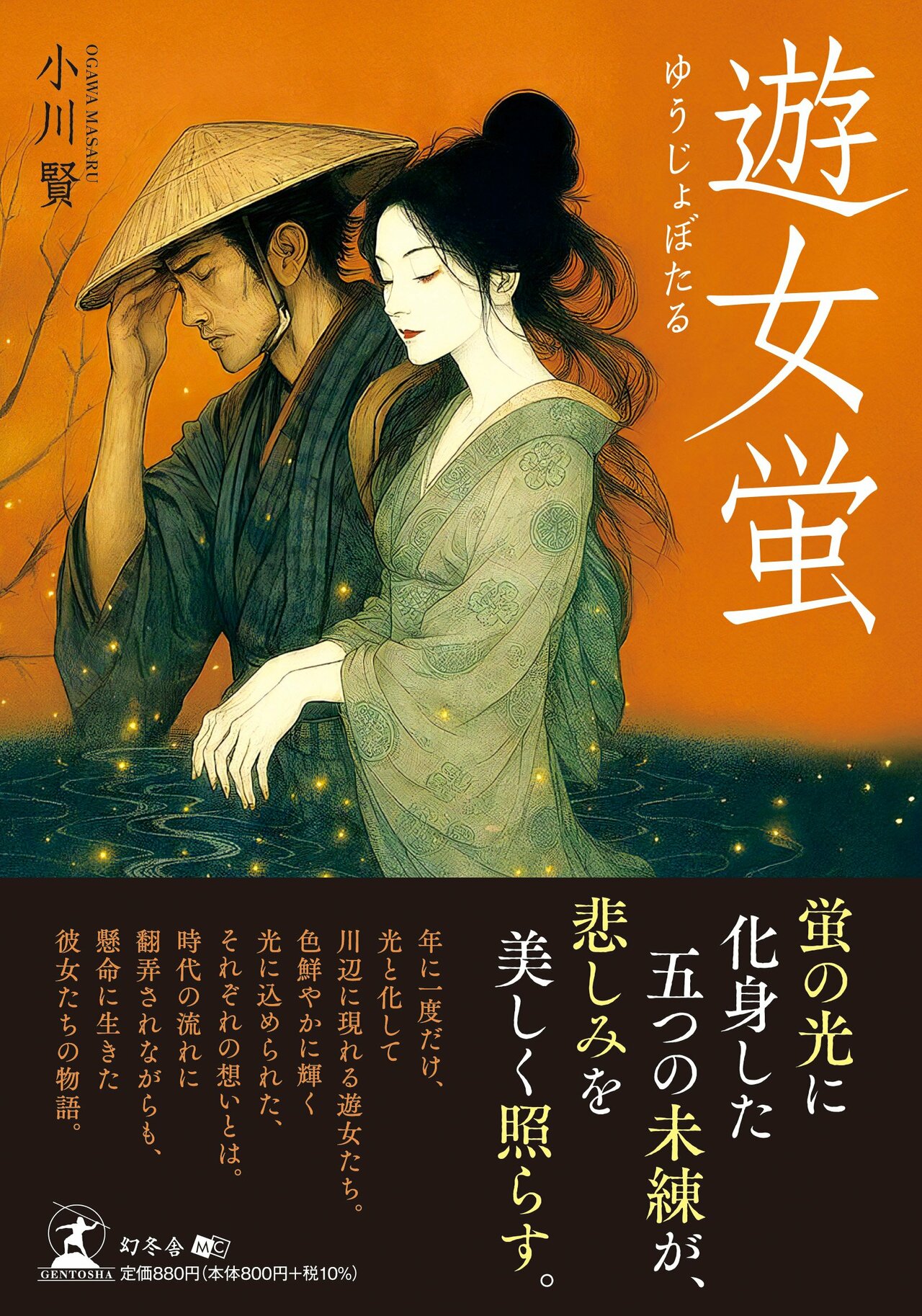横浜で塩問屋をしている叔父から聞いた話によると、この金沢の地は明治時代までは製塩業が盛んで、潮の満ち引きを利用した入浜式(いりはましき)塩田が広がっていたという。
しかし、明治末期に専売局が国内の塩田を整備した際に、規模の小さい金沢の塩田は廃止されたとのことだった。地元の人々は塩田の跡地を農地にしたが、かなりの塩分が含まれていたために、塩分に強い蓮しか栽培できなかったと叔父は教えてくれた。
坂の上から、平潟湾の入口に野島(のじま)と呼ばれる小さな島が見えた。また、一キロ程離れた所に野島より一回り小さい島も見えた。雪が降っても積もらないことから夏島(なつじま)と呼ばれているとのことだった。この二つの島が駅のホームから見えた小山の頂上部と思われた。
奈津が山手の女学校の図書室で調べた郷土史によると、東京湾の南端部になるこの辺りは、房総半島と三浦半島に挟まれており、太平洋の荒波は幅五キロ程の狭い浦賀水道で打ち消されるために、外海の影響をほとんど受けない所らしい。
このために波静かな穏やかな地形となり、古来風光明媚(ふうこうめいび)な名所として、文人墨客(ぶんじんぼっきゃく)のみならず庶民にも愛された土地柄のようだった。
江戸時代には何人もの絵師が金沢八景(かなざわはっけい)として、浮世絵に描いていた。
歌川広重の浮世絵〈野島夕照(のじまのせきしょう)〉では、野島は陸地から離れた小島だが、〈平潟落雁(ひらかたのらくがん)〉や〈乙艫帰帆(おとものきはん)〉では、野島は松並木の生えた砂州で陸続きに描かれている。松並木の砂州は野島道と呼ばれ、潮の満ち引きにより道幅が広くなったり狭くなったりしたらしい。