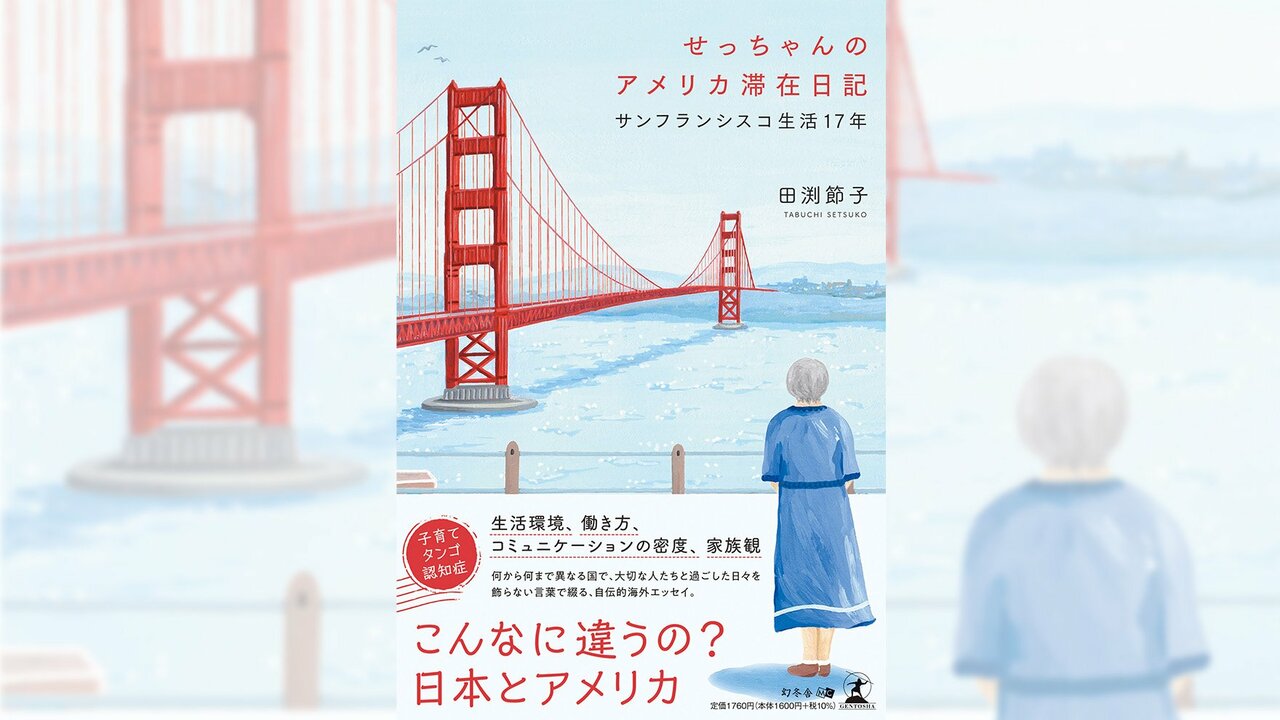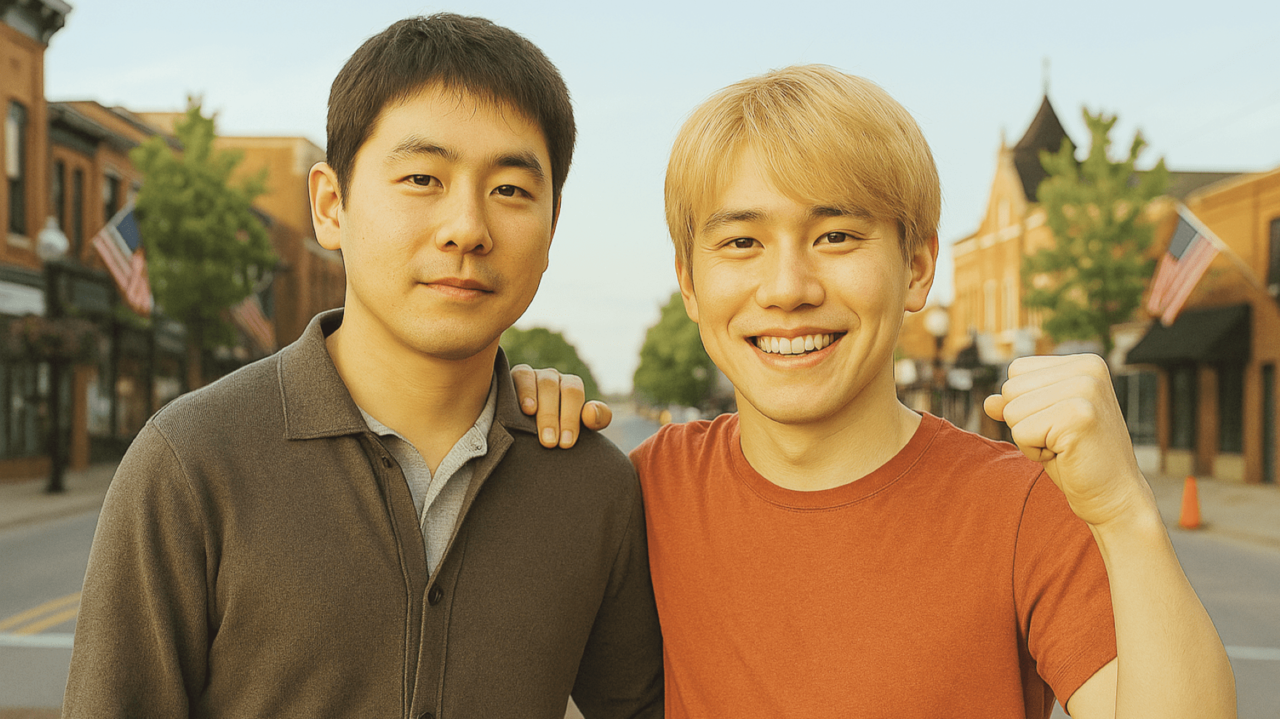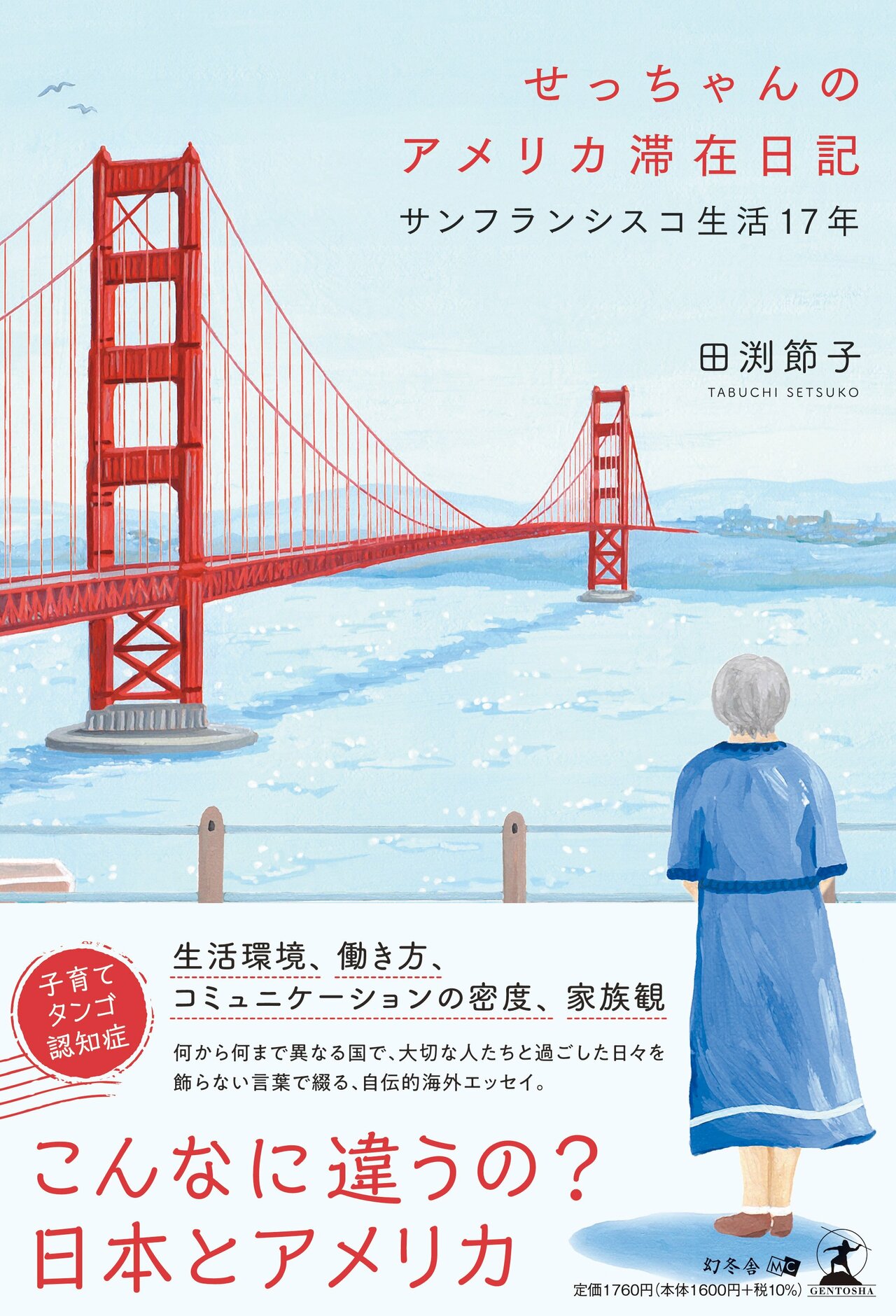【前回の記事を読む】目を見張るアメリカの教育。引っ越しに地団太を踏んでいた息子も、しばらくすると「ありがとう」と言ってくれた。
第2章 充実したアメリカ生活
―息子達の学校生活、夫の仕事と私達の生活、社交ダンスとの出会いからアルゼンチンタンゴへ
カリフォルニアでの息子達の学校生活とアメリカの教育
(渡米後約8年) ―1995年9月
翌日、早速使ってみたのか、私が学校に呼び出され、息子を連れて帰ることになりました。「通じた、通じた」と喜び、私と手をつないで帰宅することが何度かありましたが、家ではお腹の痛い様子は見えません。
ある日先生に「お腹が痛いと言って度々家に帰るが、家での様子はどうですか?」と尋ねられたので、「確かに痛むのでしょうが、家では何ともないので、精神的なものだと思います」と答えました。
しばらくすると次男は「頭が痛いって英語で何というの?」と聞いてきました。ハハーンと思いましたが、今回も「ヘッデイク」とだけ教えました。翌日早速試してみたようです。
家に着くと「今日学校でヘッデイクと言ったのにミセス・ヨシオカはナイス・ジョークと言って家に帰してくれなかったよ」というのです。「そう」と返事をすると、私は不憫やら可笑しいやら、また先生の対応に感心するやらで、涙を流しながらお腹を抱えて密かに笑いこけたのでした。
20名前後のクラスのため、先生の目もよく行き届き、息子が風邪を引いて具合の悪い時にはちゃんと見ていてくださり、息子の帰宅を許すのです。何かあるとすぐ学校から電話がかかり呼び出されるので、しばらくは家で待機する日が続きました。
今ではその次男も15歳、ハイスクールの1年生で、かつての面影は微塵もなく、心身ともに大きく逞しくなっています。髪の毛を金髪に染め、ロックミュージック、エレキギター、アメリカンフットボール、スノーボードが大好きなアメリカンと言った趣です。
そんな経緯もあり、6年半もの長い間ボランティアとして1年生のクラスでお手伝いを続けています。
先生が教室を所有しているアメリカでは、受け持つ学年はいつも変わりません。1年生が可愛いらしいのは万国共通で、次男がこんな小さい時に私達のここでの生活が始まったのだと思いながらお手伝いを楽しんでいます。
金曜日を除き毎朝2時間は国語の時間です。毎朝、最初に国旗に忠誠を誓って授業が始まります。クラスを能力別に3つのグループに分け、グループごとにリーディング、スペリング、ライティングの課題があります。教室の隅には大きな丸いテーブルと四角いテーブルが置かれて、それぞれに担任とアシスタントが座って指導します。
私はもう一人の母親と一緒に、黒板に書かれた文章の続きを書かせたり、手を挙げて質問する子に答えたり、宿題をチェックしたり、トイレに行く順番を指示したり、鉛筆を削ってあげたり、手作りノートを作ったりする雑用をこなします。最近では子ども達の目の前で堂々と辞書を持ち出してスペルを確かめたりする余裕もできました。
また、各クラスに一台は必ずコンピューター(その当時はまだ珍しかった)が備えてあり、時間の余った子が使用しています。マイペースでそれぞれの課題に取り組み、またそれを許せるゆとりのある環境で、自分の考えたことや思ったことを大切にする教育を直接見たり聞いたりしていました。