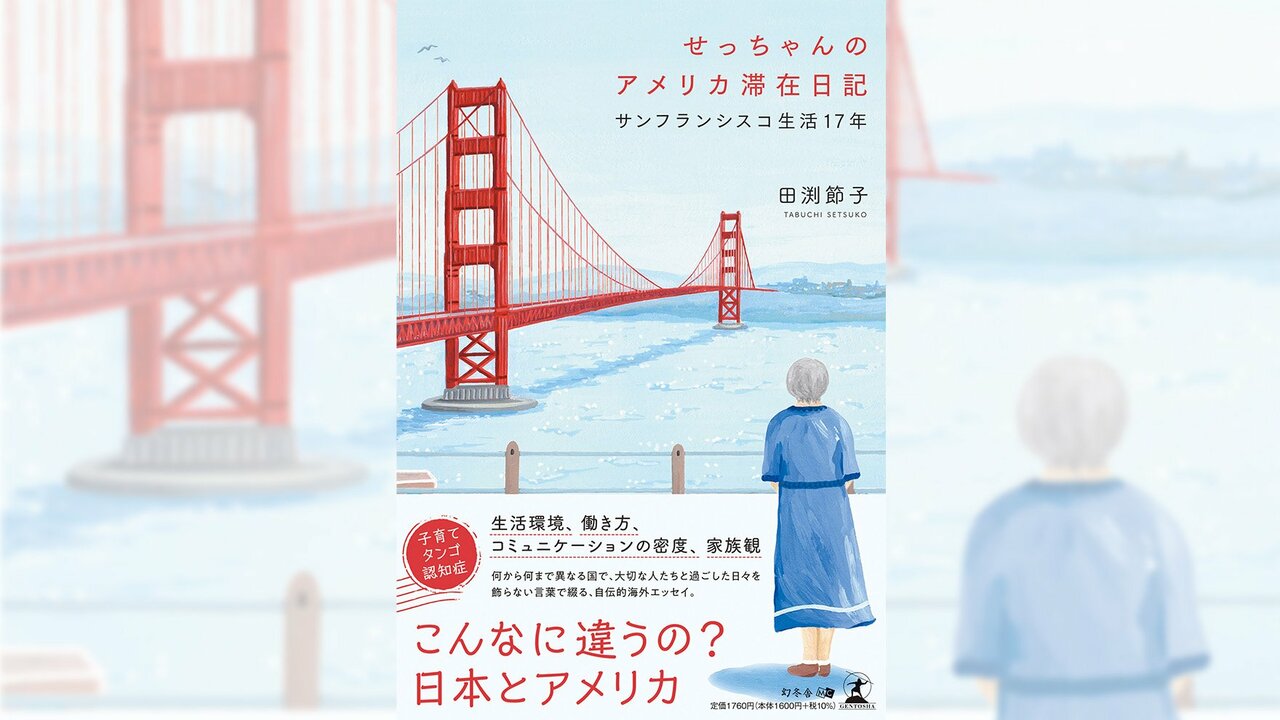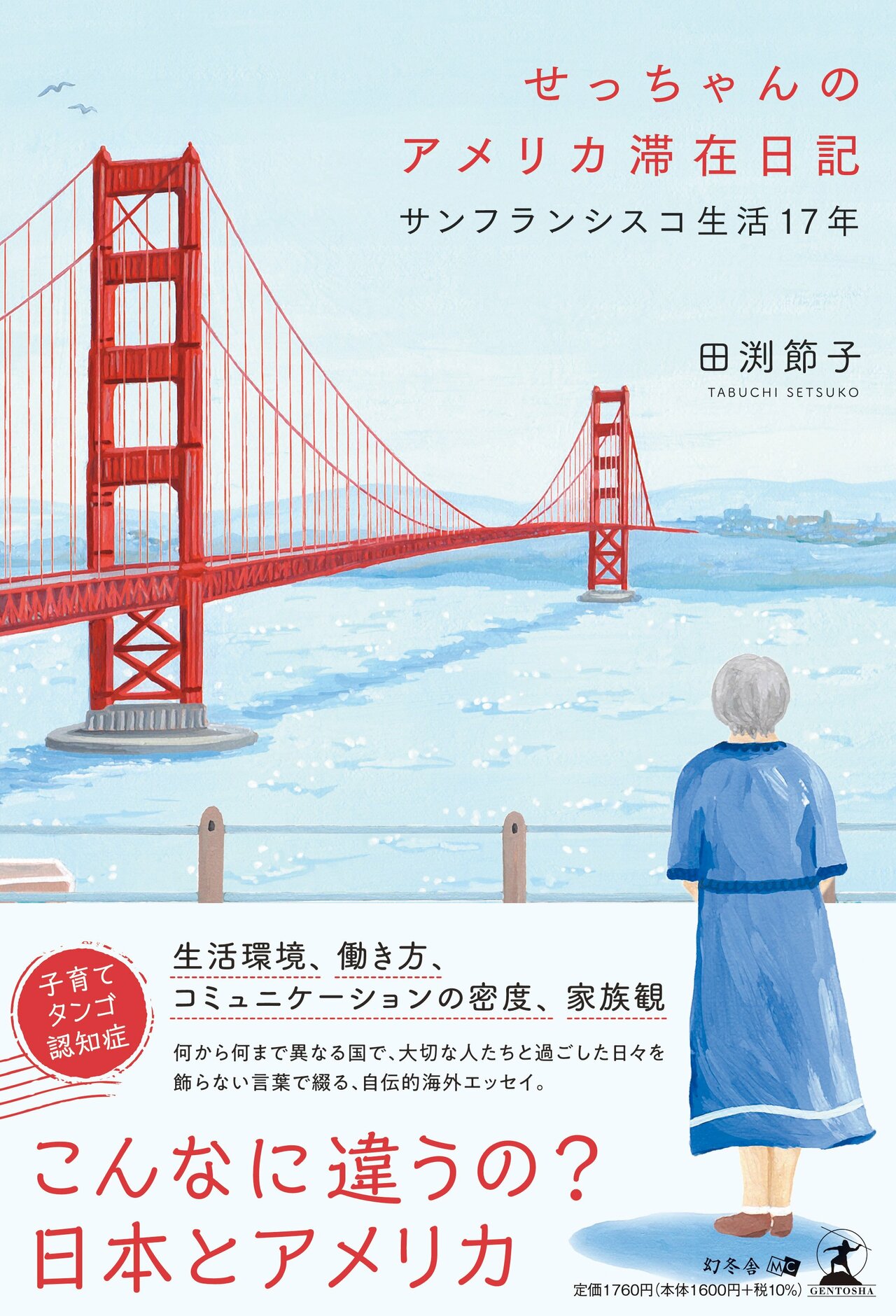【前回の記事を読む】アメリカ生活・育児・ダンス──日本人母の視点から綴る、サンフランシスコ湾岸での異文化体験
第2章 充実したアメリカ生活
―息子達の学校生活、夫の仕事と私達の生活、社交ダンスとの出会いからアルゼンチンタンゴへ
アルゼンチンタンゴとの出会いと、人と人とのコミュニケーション
―2021年11月11日
さて、素敵なタンゴダンサーを紹介いたします。今生きていれば102歳になる彼は、5歳から15歳まで日本で育ち、父親は新宿中村屋の基礎作りに貢献したという高給取りのパン職人でした。一年間アルゼンチンに滞在後、祖国ロシアに帰国するためにフランスに渡ったという81歳になるロシア人のI氏です。
第二次世界大戦のため帰国できず、滞在先のフランス軍の義勇兵としてドイツと戦いました。奥様はフランス人で仏流のタンゴを踊られます。
英語、フランス語、ロシア語が日常会話、日本語とスペイン語が少し話せるI氏は味のあるダンサーで、ダンスを一緒に楽しむことで、私の心が癒やされることも度々ありました。いつも若々しいI氏ですが、その若さは「タンゴ」のおかげだと言っていました。
日本人のコミュニティーに浸っていたら、経験できないことでした。
第3章 アメリカ生活破綻の兆し
保夫さんの若年性認知症の始まり―2001年頃
1998年、私達家族の生活の基盤であるアメリカ銀行がネーションズ・バンクに合併され、銀行仲間が集団で、サンフランシスコに本店があるユニオン・バンクで働くようになってしばらくした頃です。
その銀行のロサンゼルス支店からの誘いがありましたが、なぜかその時保夫さんは、指定の場所に車で一人で行き着くことができませんでした。顔見知りの上司も不思議に思われたことでしょう(保夫さんの焦りが目に浮かびます)。
仕事の内容も、元の企業の信用調査から監査の仕事になりました。同僚を評価したり、非難したりするのは自分の性格に合わないと悩んでいました。私も一度ロサンゼルスまで行って、保夫さんの様子を見ようと、一緒のホテルに泊まり、市内見学をし、新居を探したことがあります。