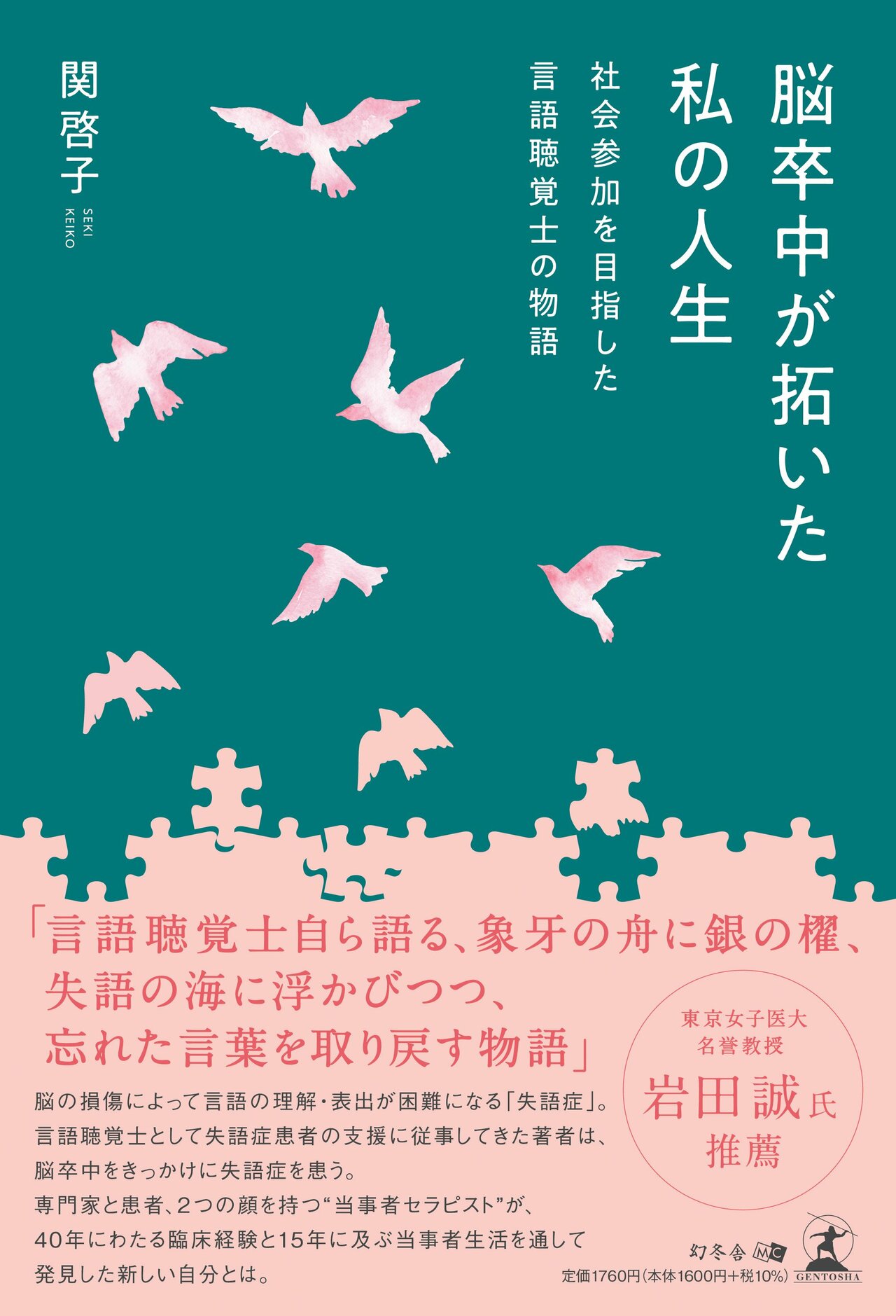一人前のSTを目指した養成校での修行の日々
新婚時代、通学に電車一本約30分で通える便利な場所に新居を定めたのに、入学前に思いがけず養成校が遠方に移転という大番狂わせもありました。
が、無事入学後、往復3時間をかけたマイカー通学で早朝から深夜まで時間割が授業でびっしり詰まった専門分野の勉強にどっぷり漬かった1年間(現在では未だ過密ながら2年間のカリキュラムが確立)を過ごし、何とか専門職への道を歩み出しました。
当時は養成課程に関する「指定規則」(監督機関が定めた当該専門職用カリキュラムのこと)も「臨床実習」制度もなく、日本語で書かれた教科書すらなく、「基礎医学」として「解剖学・生理学」、「臨床医学」として「内科学」「小児科学」「精神医学」など、さらには「耳鼻咽喉科学」「リハビリテーション医学」「心理学」に至るまで各専門領域に造詣が深く高名な先生を授業にお迎えし、わかりやすく丁寧に教えていただきました。
その後、私も学院の非常勤講師に加えていただき、発症後も「高次脳機能障害」の授業を継続しています。
そして、学生は小さな部屋に集合して自習用として指定された英語で書かれた論文や教科書などの資料を参考に、それらを和訳しながらひたすら勉強したことを覚えています。そのためか、授業料は申し訳ないくらい少額でした。
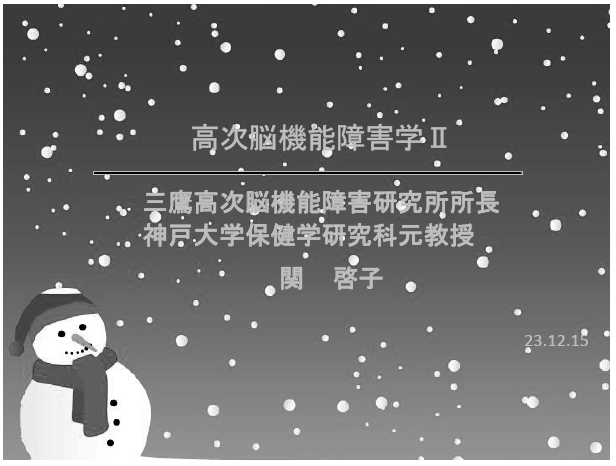
国立障害者リハビリテーションセンター学院(略称国リハ学院)授業スライド
翌年の1983年に晴れて課程を卒業し、就職を希望した都立の医学研究所(東京都神経科学総合研究所〔略称 神経研〕)に入った私は、脳梁離断症候群など言語情報の脳内処理に関する先端的研究により大脳の左右各半球と言語機能の関係を理論的に解明した偉大な神経心理学者S先生の研究部門に配属され、さっそくご指導いただきました。