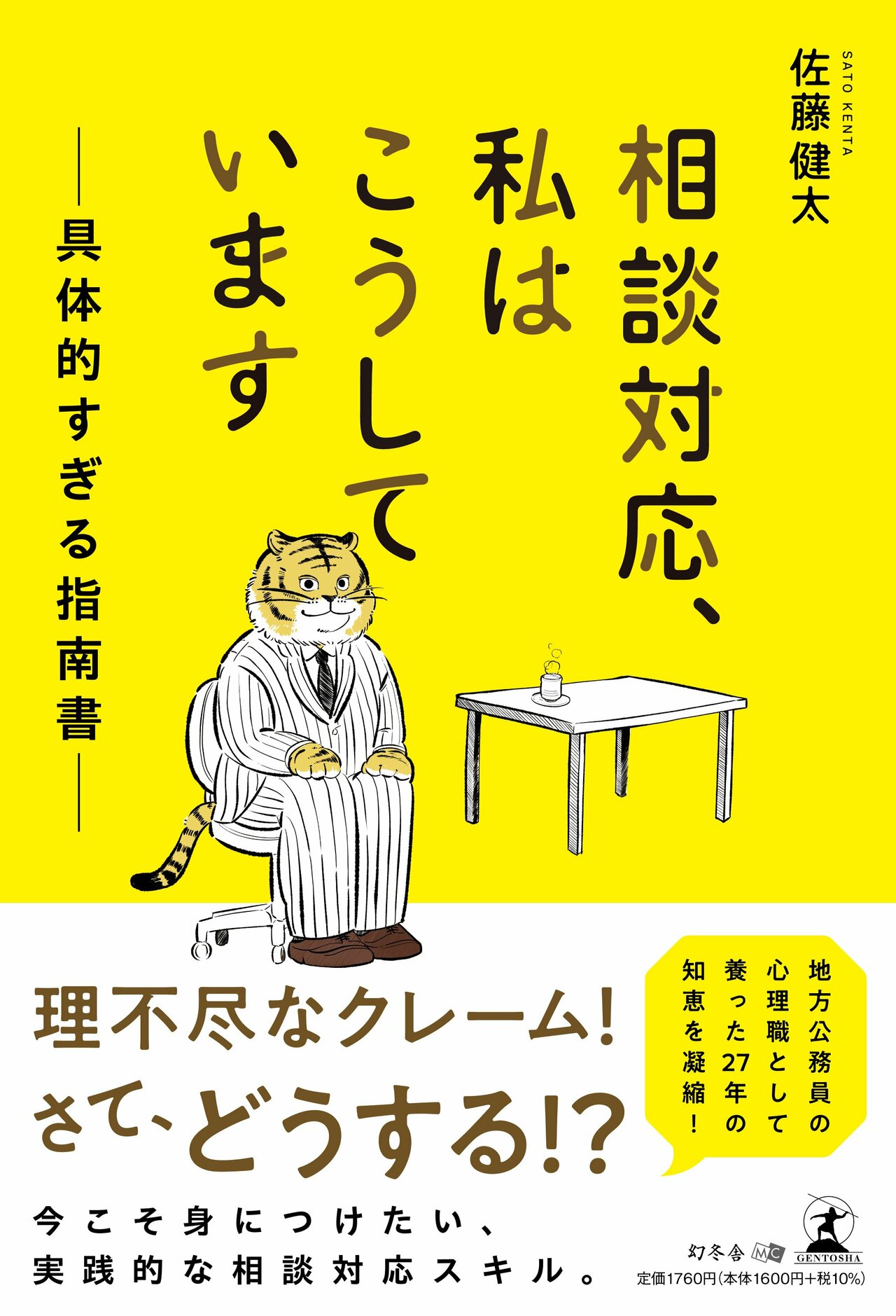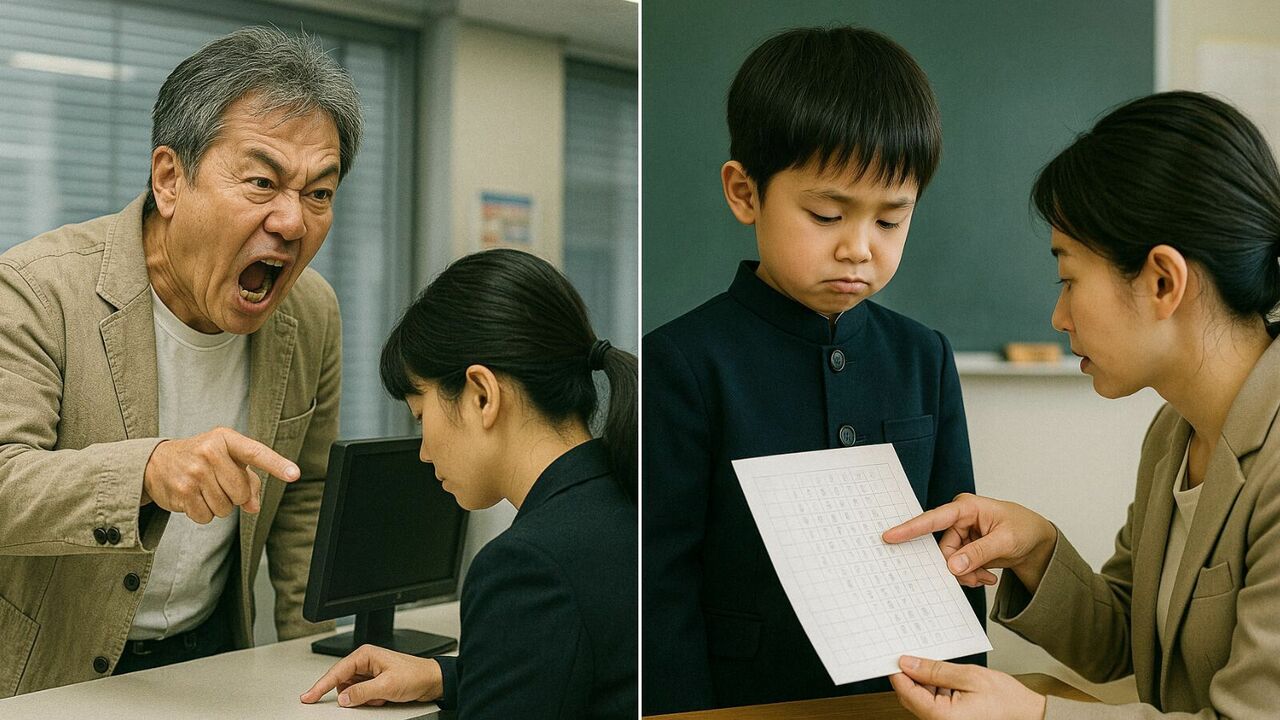・こちらに落ち度がある場合
不当な言い分や要求ではなく、例えば「組織としての対応のまずさ」に起因したクレームであれば、お詫びを含めながら相談者の言い分を十分聴く必要があります。落ち着いて話ができる場所に移動するなど、冷静に話せる状態に導きながら、「今どんなことを話せたら良いか」という話題にたどり着くように話をつないでいきます。
ただただ怒りをぶつけたいという状態でなければ、このような姿勢で聴くことにより、相談者が本当に話したいことを話すことができて、話の方向性がうまくまとまることもあります。
最初は怒っていた相談者と、最終的には冷静に話ができたこともしばしばあり、話の終わりに「興奮して申し訳なかった」「聴いてくれてありがとう」などと、お詫びやお礼を言われたこともありました。
・カスタマーハラスメントに該当する場合
最近、テレビなどでカスタマーハラスメントを略した「カスハラ」という言葉を見聞きする機会が増えました。私が苦労して対応していた頃も、この「カスハラ」という言葉は既にあり、「今のはカスハラに該当する」と思いながら仕事をしていたことが度々ありました。
ただ、今ほどクローズアップされている状況ではなかったので、組織でどう対応するかという議論にはなっていませんでした。そのため、苦労しながら一人で何とか対応するということが幾度もありました。本来であれば、「一人で対応するのではなく、係長級以上の人を呼んで複数で対応しよう」など、担当内でルール作りをして、それを共有して備えるべきであったと考えます。
例えば、電話対応の最中に「殺す」など脅迫に当たるような言葉を向けられた場合、「恐怖を感じるので電話を切らせていただきます」と伝えてこちらから電話を切るというルールがあってもいいでしょう。
切ってもしつこく電話がかかってくるようであれば、上司が電話に出て、「ここは○○の相談を受けるところなので、冷静にお話ができる状態になってからまたお電話ください」と伝える、それでも状況が変わらなければ、「冷静にお話しできないのであれば切らせていただきます」と伝えて電話を切る、という話の流れをフローチャートにしてもいいでしょう。
これに、感情を入れずにブロークンレコードテクニック(コラム①参照)を用いて伝えるとか、必ず録音するといったこともルールとして考えられることです。
最近は、「社内で共通のルール作りをしている」といった報道も見聞きする機会が増えましたので、昔のように一様に「お客様は神様」とする時代が変化してきている印象を強く持っています。
また、労働者を守るという風潮が高まり、働きやすいルール作りが促進され、仕事へのモチベーションが損なわれないような環境に変わっていくことを願っています。直接現場で対応する方が疲弊しないように、このような取り組みがあちこちで促進され、「やってもらって当たり前」ではないという価値観が相談者側にも根付いていくことを期待しています。
次回更新は4月29日(火)、8時の予定です。
【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...